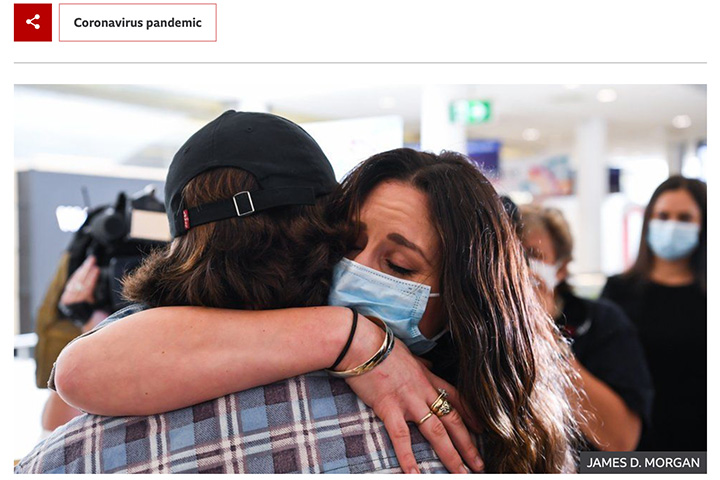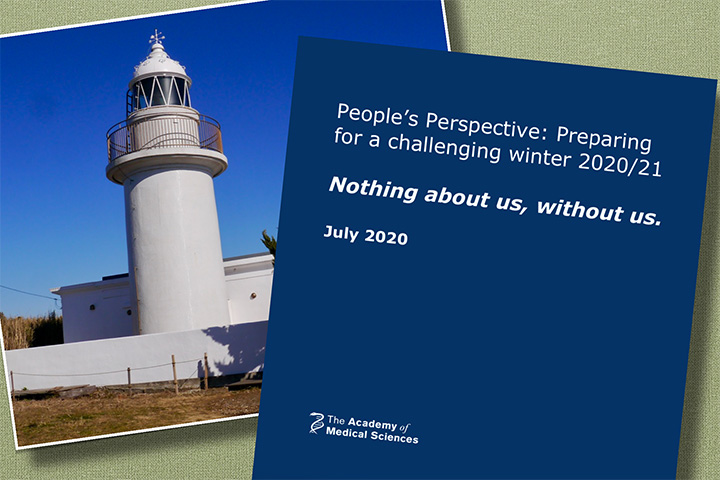▲連続テレビ小説は、多くの人にとっては半ば習慣化した朝の時間だろう。舞台は東北の豊かな自然に囲まれた地域の物語。福祉の力とはそうした風景にも秘められている。(写真:NHKおかえりモネ公式サイトより。宮城県登米市の森の風景)
朝の連続テレビ小説、「おかえりモネ」をついつい視てしまう。
私にとって朝ドラというのは、朝刊、トースト、コーヒーとともに出てくるモーニングセットのような生活習慣で、いつもなんとはなしに見始める。だからこの朝ドラも「おかえり!」というほどの歓迎があったわけでなかったのだが、初回に登米(とめ)という地名が出てきたので、思わず身を乗り出した。
というのも、それ以前から宮城の介護、医療、行政などのネットワークで、新型コロナウイルスの事態での「介護崩壊を防ぐため」という議論と実践の場に参加していたのだが、確かそこで、この登米市の高齢者施設の状況も話し合った記憶があった。
「おかえりモネ」の舞台は宮城県登米市と気仙沼。
登米市は、宮城県内陸部に位置し、ドラマではその豊かな緑の風景がみずみずしく映し出される。絵葉書のような単に綺麗な景色というのではない。梢や木々の葉の輝きや揺らぎといった光や風を描写するような新鮮な映像なのである。
登米はいいところだなあ、と素直に引き込まれる情景が至る所に現れる。朝ドラの宮城県登米は森の豊かさと、文化と歴史を抱く林業の土地柄として描かれている。
「おかえりモネ」はどうやら、永浦百音(モネ)というひとりの気仙沼の高校を卒業したばかりの少女の成長物語のようである。健気でまっすぐなモネの姿や行動自体の好感度が大きいのだろうが、実はこの朝ドラ自体は、現代をその深部から問い直しているようだ。
ここまでで見えてきたことは、このさわやかな少女や周囲の人々、家族の背景には常にある重い現実が流れている。それは登場人物の誰もが、「あの日」、と語るだけでただうつむくしかない現実を背負っている。どんなにモネが溌剌と明るくふるまっても、ふいにその「あの日」のことがモネを立ちすくませる。
誰もが、「あの日」を「何もできなかった自分」として思い返している。
泣くこともできない重さの現実もある、ということも、じっと森を見つめるモネの横顔が語ることもある。胸に迫るような静かなカットが、そっとはさまれて物語は進む。
「あの日」が、あらわに人の気持ちをわしづかみに揺さぶったシーンがあった。
「あの日」に妻を亡くした気仙沼のカリスマ漁師が以来、酒に溺れる。そのことを諌めるモネの家族に、うつむきつづけていた彼は初めて顔を上げ、絞り出すように言う。
「5年は長いのか(ドラマ設定では、あの日から5年後)。5年経っても何も変わらない。どん底のままだ。オレは立ち直らない。立ち直るものか」
彼は、亡妻の最後の伝言が録音された携帯を握りしめ、肩震わせ、周囲の人は、ただ声を失う。
どんなに無垢の善意であろうと弾き飛ばされ、立ち直ることを拒否する心情でしか、自分を支えられない「あの日」のことが、朝の、私たちの日常性の中に伝えられる。
この朝ドラの異色は、見方によれば、日常の中のぬぐいきれない苦味をにじませて進行する。しかしそのことはこのコロナの日々にあっては、目を背けてはならない私たちの現実でもある。綺麗事で言いくるめるのでなく、立ち尽くす地点からモネは、たぶん、模索や失敗や葛藤をたっぷりと味わいながら、歩み出していく。そのモネに私たちは伴走する。いや、モネに導かれるのかもしれない。
この朝ドラのもう一つの主題は、「自然」である。
自然は時に「想定外」の猛威を奮って命と暮らしを奪う。しかしこの朝ドラでは、あえてそれを災害、禍、脅威などの言葉で前面化して語ることはない。家族を奪われた漁師もその息子も、厳しい冷え込みに海面から立ち上がる霧、けあらしを見つめながら「海に恨みはない」と言い、その息子も「海は嫌いになれないんだわ」とつぶやく。
自然は、時にあまりに大きな試練を与えるが、それは同時に試練を力に変えることができるか、という私たちの共同体への厳しい問いかけなのかもしれない。
ここにあるのは、自然につつまれ、生かされているという、古来からの風土にはぐくまれた自然観である。
「私たちは生かされている」、この通奏低音は朝ドラの全体を流れている。
登米の林業は、第一次産業の経済からすれば衰退産業だが、描かれるのは豊かな自然の恩恵と、地域の「能」伝承が示す文化であり、またそこで働き暮らす人々の尊厳に満ちた姿である。
林業に携わる高齢者や、山主の不思議で謎に満ちた人格のサヤカも、いわゆる高齢者像の枠を超えて、地域の活力を生み出す主体者と位置づけられている。
何より、ことあれば集い、身体ぶつけて笑い合う登米の森林組合での底抜けに明るい日常は、多くの人が自分たちの地域社会の姿と重ね合わせただろう。私たちの日常は、地域や自然から実に多くの力を贈与されながら「生かされている」。
気仙沼の海の人々、登米の山の人々、誰もが自然や地域に深々といだかれて生かされている。
地域福祉であれ社会福祉であれ、福祉は制度などでつくられる側面もあるが、空気や水のようにそこに「ある」ことによって、命や暮らしを成り立たせている力もある。私たちが気づかないだけで、豊かな自然は根元的な福祉力だろう。
自分と自然を結びつけるのは、モネの場合、「気象」である。
海の水は雲を湧かせ雨となり、山を潤し流れとなって海に注ぎ生命を育む。循環する自然に押し出されるようにしてモネは未来に歩み出そうとする。
「何もできなかったと思っているのはあなただけではない」
気象予報士の言葉にモネは、自分の中に響き続けている何かに気づく。
この朝ドラがこれまでといささか趣を変えているとするなら、ここで進行するそれぞれの物語の全体像はあらかじめ示されることがない。この社会の不完全な姿をそのまま引き受けるようにして、それぞれの登場人物の抱える哀しみの断片は小出しにされながら、やがてどこかでつながったり、別の場面に飛躍するようだ。
それは、視る側の受け止めによって様々な小さなエピソードを辿り、ジグソーパズルをはめ込むようにして、やがてそれぞれの私たちの物語に合流していく。そんな感じがする。
私たちの社会課題は、常に人間社会の枠の中で提起され、整理され、その解決が語られている。でももしかするとそれは人間界の思い込みやおごりなのではないか。人間社会のフレームを一旦外して、自然とともにある自分というものを見つめ直してみると、私たちは違う風景を見ることができるのではないだろうか。
もちろん、朝ドラとしてそんなに小難しい理屈を振りかざしているわけではない。朝ドラ伝統のお約束として、ここには悪い人は出てこない。もちろん対立や小競り合い、喧嘩やすれ違いなどはあっても、それぞれが懸命に生きる人々であり、悪人はいないという安心できる調和はしっかりと確保している(はずである)。
毎回どこかで、胸に込み上げてくるシーンがあって、すっかり涙腺が弱くなったこちらの年を実感しながら、「弱さを語ってもいいのだよ」、そんなふうにモネに語りかけている。
モネのまなざしは、自然とともにある私たちの現実の厳しさやつらさと、だからこそ、その回復のかけがえのなさを見つめている。
いつの日か、このコロナの日々をくぐり抜け、モネに向かって「おかえり」と微笑むことが出来るといい。