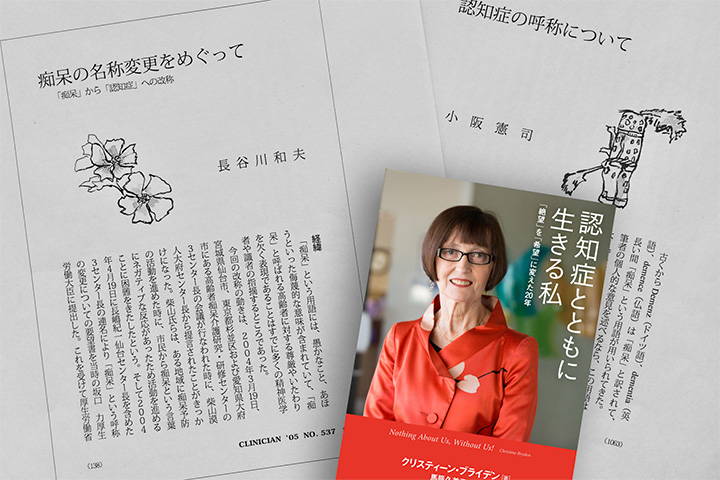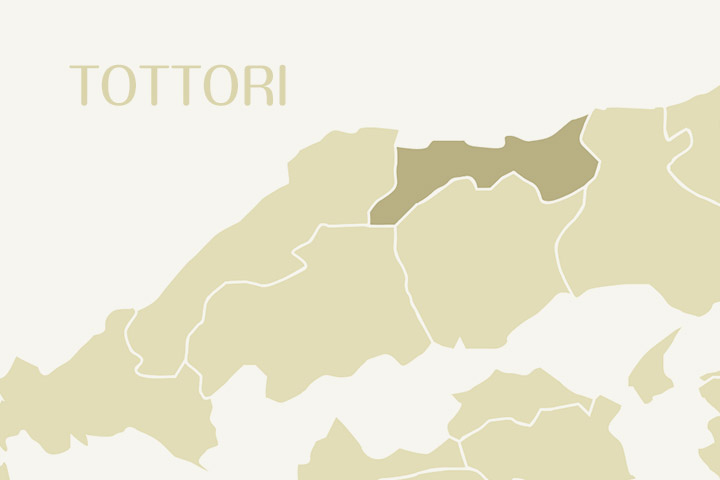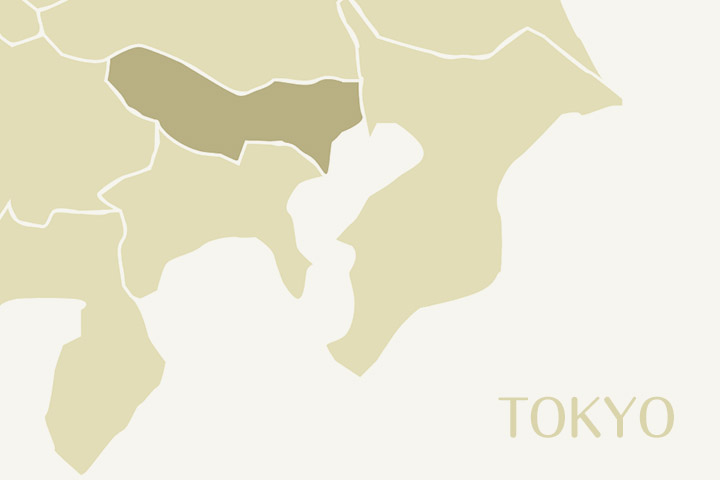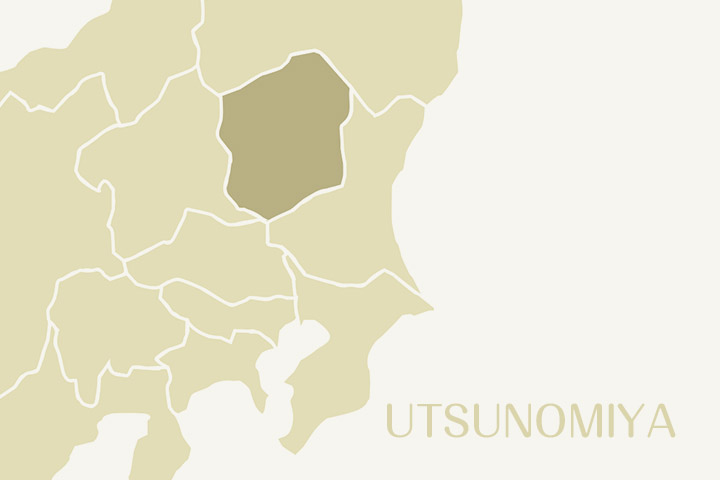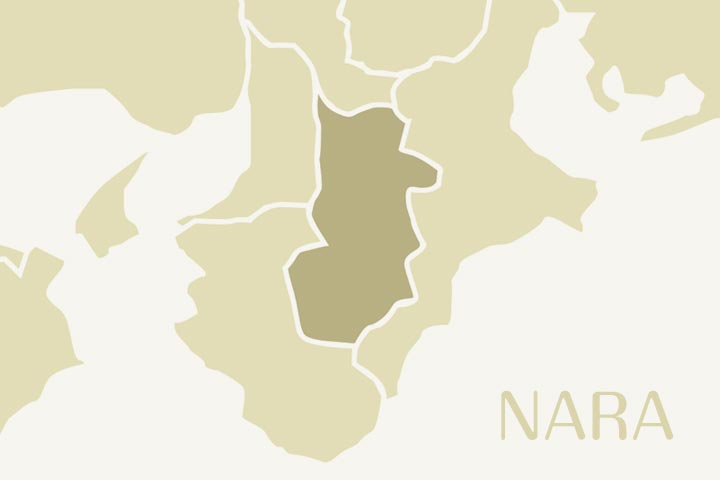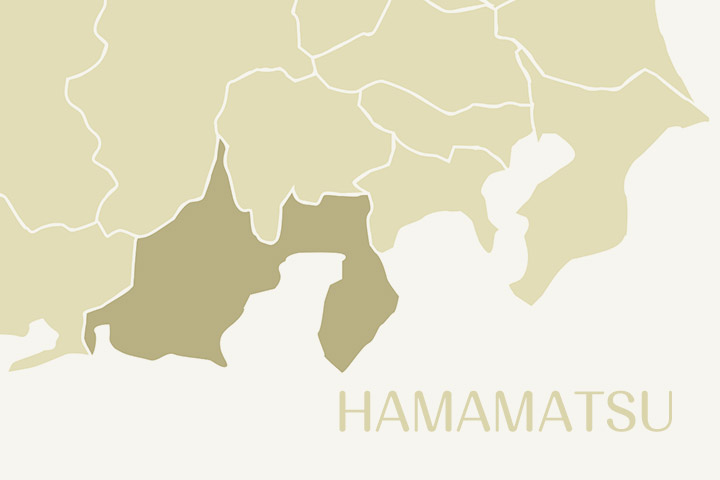▲この径(みち)は、いつかきた径。わたしたちの人生の旅路は、誰もがかならず、いつか行くだろう径をたどることになる。同伴するのは記憶である。その記憶は、次々と引き継がれて後を歩む人を励ますだろう。
記憶とは一体、どんなことなのだろう。
私たちは、通常、何気なく昨日という過去を今日につなげ、「おはよう、今日もいい天気」と言い、夕方には「じゃ、明日またね」と、今日と同じような明日という未来を信じているが、そこをつなげているのは「記憶」があるからだ。
そして、この社会が成り立っているのも記憶の力である。もしも、記憶というものがなくなってしまったら、それは背後の大地からいきなりガラガラと崩れ落ちるようなもので、私たちは危うい現在に立ちすくむしかない。
認知症、とりわけアルツハイマー型認知症の人にとっては、記憶は切実な要素だろう。
多くのアルツハイマー型認知症の解説には、それは不可逆的な脳疾患であり、記憶障害を伴うと記されている。つまり、治らない脳の病でありその症状は記憶が失われていく、ということだ。
私たちは、記憶を手にとってまじまじと眺めることはできない。ということは果たして記憶はどんなものなのか、確かめることはできないということだ。せいぜい確かめるすべとしては、認知症医療での、記憶を司る脳の中の海馬が萎縮することで、記憶が障害されるとする説明に拠るしかない。
記憶が失われる。その言葉が持つ圧倒するような絶望はどこから来るのか。
物忘れであるとか、記憶できないという生活上の支障以上に、認知症の人が直面するのは、実は、深い自己の内面の闇にある。
それは、自分の存在が喪失するということだ。
クリスティーン・ブライデンは、認知症の診断を受けた時の衝撃として、まず自己の喪失をあげている。それはアイデンティティの危機であり、「私は誰になっていくのだろう」という底なしの絶望であったと語っている。
記憶を失う。自己の存在を失う。これはすでに医学の領域を離れている。脳の中の海馬の働きで説明は出来はしない。記憶は、哲学や心理学、社会学の領域でかろうじて対応できるかもしれない。
「認知症とともに生きる」とするわたしたちの共生モデルは、記憶の喪失にどう向き合うことができるのだろう。
この社会では、幼い時から「忘れてはならない」という「しつけ」が繰り返されている。
保育園、幼稚園という生育の過程で、絶えず「忘れ物しないように」と刷り込まれる。忘れることは「いけないこと」であり、それはそのまま社会に歩み出したときに、「忘れない」は社会人の能力査定欄の一番上に格上げされていく。
有能な人とは、忘れない人であり、それは生産性と効率という能力主義を補強していく。
記憶に、私たちができることは何か。
暮らしの中の忘れることに限定するなら、方策はないわけではない。そのひとつにはこの社会に通底する価値観の見直しということがある。
具体的には、「忘れてもいい」とするわたしたちの側の工夫である。それは細やかな心情を添えられて実践されている。例えば、電気のスイッチを切り忘れても「ほらあ、またあ」ととがめない。忘れても、そっとあなたが消せばいいのである。
あるいは、スマホ、パソコンなどのICT機器を駆使することで、記憶の外在化を推進することである。記憶は本人が持たなくても良く、ハードディスクといったメディアに持たせておき、指の操作ひとつで記憶を呼び出せるようにする。これは認知症当事者にも実践者が多く、かなり可能性が高いかもしれない。
その一方で、この社会の隅々までを高度情報社会のIT技術で、記憶の外在化を推し進め、超高齢社会を設計し直すと提言する少壮の学者もいる。これは「ともに生きる」からの逸脱の感なきにしもあらずなのだが、マ、検討に値するかもしれない。検討してもいい。
本来、社会学での記憶の外在化とは、かつてのなつかしい校舎などで呼び起こされる記憶として位置づけられ、あくまでも個人の回想につながるものとされている。
それをデジタル装置によって、チャチャっと記憶の外在化というのは、果たして本来の記憶という情動のすこやかな移転になりうるのかどうか。あるいは、そのあたりもAIによってバッチリ可能であるのかは、古い奴だとお思いでしょうが(鶴田浩二・談)、よくわからない。
ただ、私がこの「忘れてもいい」という手作り感に満ちた実践の礼賛にいまひとつノリが悪いのは、そこには、認知症ではない側の無意識の、この社会からの「お目こぼし」感覚がつきまとうからである。
「忘れてもいいよ」って、ともすれば上から目線になりがちである。いや、申し訳ない。こうした意地悪なことを言ってはいけないのは重々承知なのだが、それはどうも「共に生きる」が「共に生きてあげる」善意限定になっているようにしか私には思えない。
もちろん、家庭内や地域でのこうした取り組みは、この社会の新常識として是非、定着してほしい。しかし、認知症の当事者が求めているのは、この社会のパラダイムシフトである。それは端的には、私たちが変わることなのである。
認知症につきまとう記憶の喪失は、実は、物忘れの次元を突き抜けて自己の存在の喪失であり、アイデンティティの危機である。「認知症とともに生きる」ことを語るとき、実はこのことに私たちは答えていない。答えられていない。
喪失とは、ひたすらの悲しみである。悲しみはその人の内面に沁み込む哀しみとなって、その人は世界から切り離される感覚に溺れていく。
私たちのこの社会には、共有化できない哀しみに満ちた孤独というものが存在することに気づかなければならない。声をかけることもできない他者の孤独と哀しみに、私たちはたちすくむことを求められている。
認知症の人々が向き合う喪失のつらさ、哀しみ、絶望の重みに釣り合うだけの希望を、私たちは、あるいはこの社会は、生み出すことが出来るのだろうか。
「認知症とともに生きる」の心地よさに隠された欺瞞と偽善の希望を振り落として、彼ら彼女たちの喪失の悲しみに、私たちは打ちのめされるところから始めるしかなく、そうしてはじめて、私たちは気づく。
喪失は私たちにも訪れる。喪失は誰もが避けられない。死を誰もが避けられないのと同じように。そして、やがて誰にもやってくる死を思うことは、今の生を輝かせることにもきづくはずだ。
喪失とは、消え去っていくその瞬間だけに焦点を当てがちだが、実は、そこに至るプロセス全てを辿るようにすれば、喪失とは、奪い去るものではなく、洗い流すようにして人生の結実としての大切なものを生み出す確かな力があるのかもしれない。
インスタグラムで自分の作品を発信し続けている認知症当事者の下坂厚さんの写真を見つめて感じることがある。
どの写真も全体的な説明的な写真ではない。風景の一画、暮らしに流れる時間、樹々の葉のそよぎの光と風、と言ったものが、何気なく切り取られていて、その何気ない中の真実が、見るものに自分の中の懐かしさやいとしさ、そして切なさを呼び起こす。
ファインダーで被写体を切り取るということは、言い換えれば、周辺を切り捨てる選択である。下坂さんの作品は、喪失の輝きなのではないかと思ったりする。ファインダーで、なにかを切り捨てていく作業を続けながら、だから、この世界から彼の想いこめて切り取った一瞬の風景が輝く。切なさが、心を打つ。
彼は、認知症になってからの作品が変わったという。それは、記憶をとどめるための記録が、いつしか自分だけの表現に変わってきたと、彼の著作「記憶とつなぐ」に記している。
彼の人生の表現に、喪失は影を落としただけではなく、より深く自分という人間を掴み取らせているのかもしれない。
その下坂厚さんと、地域のフォーラムで一緒になった。
著作「記憶とつなぐ」の最後には、最愛の妻佳子さんにあててのメッセージが記されていて、それは、自己の喪失の自認であると同時に、そこから新たに歩み出す彼の決意のようだ。
「いつかは、あんた誰や、という日が来るかもしれない。でもよっちゃん(佳子さん)のことは決して忘れることはない」、そこには、こう綴られている。
それは、ある意味では、記憶は失われても、忘れることはない、という背反した心情なのである。
私はここにあるものこそ、記憶の力なのだと思う。私の記憶は、あなたの記憶であり、それは喜びや悲しみや愛情、時間と風景の全てを込めて、受け渡し、引き受けるという最も深いところからの人間存在の交流なのである。
「あなたを忘れない」
記憶はそのようにして、家族や仲間やふるさとの山河に引き継がれ、生きることの切なさに生を輝かせていく。
私は会場で、この下坂厚さんのメッセージを紹介しながら、不覚にも心震え、声を詰まらせてしまった。
|第211回 2022.5.27|