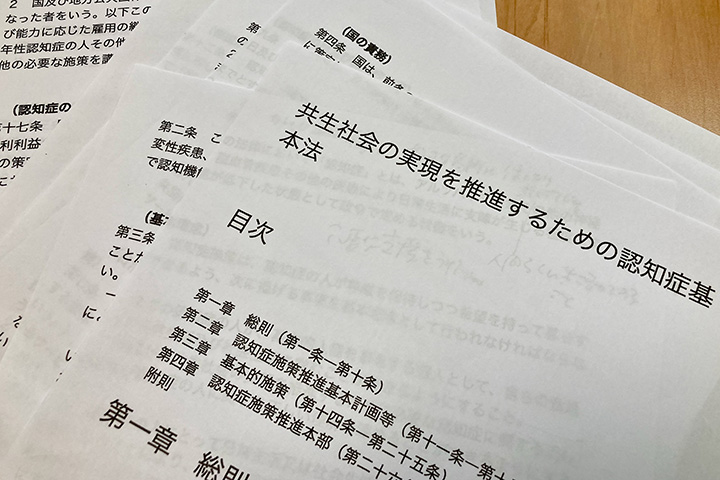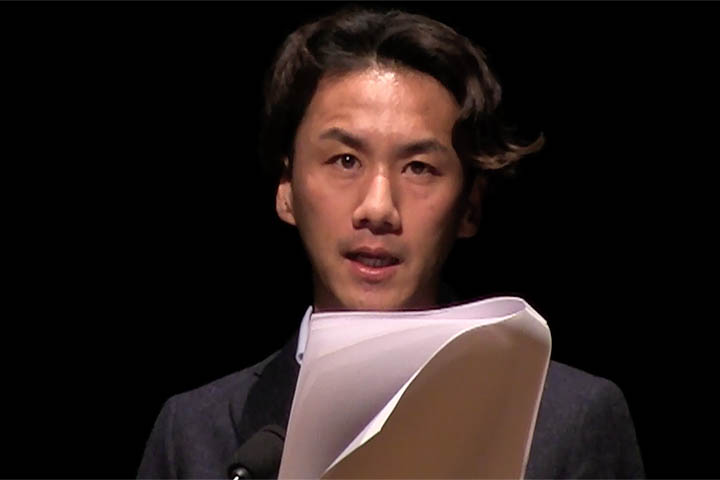▲ボディランゲージとしての腕組みというのは不安のあらわれだそうだが、どうも私の場合、必死に何かを理解しようとしている場合が多いように思う。その蓄積が何らかの思いや動きにつながっていけばいい。コロナの日々の不安の向こうに、腕を解き放す新たな時代は来るか。
以前ラジオ深夜便に出演したときに、ディレクターの佐治真規子氏から、「マチナガさんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」と直球を投げられて、随分と面食らったことがある。
熱心、という言葉はどうも自分にはおこがましく、しっくりこない。熱心な人々はたくさん知っているし、コト、認知症に関して熱心な人々と言えば、私の周辺には当事者をはじめ、医療者やケアの専門職や地域福祉に関わる人々がひしめくようにして活動をしている。
そうした人々は、皆一様に「現場」を持つ人々である。
そうした中の一人が、コロナの事態が起こりつつある予感の時期に、「施設の高齢者はこの事態に逃げることができない。だから、私たちは逃げるわけにはいかない」と、静かな口調ながらまなじりを決するようにして語ったことがある。以来、彼ら彼女たちは、このコロナの事態の、地域医療やケアの崩壊最前線で、土俵際にのけぞりつま先立つようにして現場を支えてきたのである。
それを熱心と言えば、熱心なのかと思ったり、あるいは使命とか責務と言ってもいいのだが、同時に、それはどの形容にも収まりきらない個々の「やむに止まれぬ想い」なのではなかったのかと思ったりしている。
コロナの歳月のせめてもの奇貨として、地域の現場の一画で浮かび上がったのは、こうした「やむに止まれぬ想い」といったことではないか。そしてそれは施策や職能的機能を超えた地点で、医療や介護の現場のみならず、まちづくりといった地域活動に携わる人々が持ち続けた力ではなかったろうか。
東日本大震災の時、市職員の4人に一人が亡くなるという被災自治体最多の犠牲となった陸前高田市では、安否確認や救援物資配送を、かろうじて生き残った市民たちが担い、助け合いながら命をつなぎ止めた。
「やむに止まれぬ想い」というのは、ギリギリの自己審問であろう。
既成の価値観や機能からではなく、自分が自分自身であることに啓示のように気づき、ある時には咄嗟のようにして人は突き動かされることがある。
福祉力の源泉は、そうした個々のやむに止まれぬ思いから湧き出している。わたしたちの中には、そうした「想い」が熱く底流している。
コロナの事態をかいくぐるようにして見えてきたのは、明らかに時代の行き詰まりである。
施策、政体への不信を嘆き尽くした果てに、しかし、何かが動き始めてはいないだろうか。それは、個々の胎動の時代なのかもしれない。
覚醒といった明示的なものではなく、何かの予感のようにして「やむに止まれぬ想い」を抱く一群の人々が動きはじめようとしている。
これまでの社会運動というものは、言ってみれば、社会構造上の不正義や問題を、多くの人の集団的行動によって解決しようとする活動である。しかし近年、人々の不安や不満というのは多様多岐にわたり、マイノリティ、女性、平和、住民、消費者といった「個」の側から発生している。となれば、集団として「問題」を一括りし、その「解決」を目指すスキームでは対応できず、そこから新たな価値の創造につながる取り組みに変化している。
つまり、「新型コロナウイルスは問題だ!」とこぶしを振り上げ、プラカードに「コロナ、絶対反対!」と大書きして練り歩いてもほとんど意味をなさないのと同じで、見るべきは、この事態をひたすらしわ寄せされた高齢者や貧窮者や事業者たちといった小さな「個」の側の事態と声なのである。
思えば、認知症当事者は早くからその道筋を示してきた。認知症を「問題」とし、「ならないこと」を解決とすることから離陸して、個々の認知症当事者は、「認知症とともに生きる」という新たな社会価値への変換と創造を呼びかけてきたのだ。
「ともに生きる」という共生モデルへの問い直しというのは、ともに生きるとする個々それぞれの主体を問うことである。ある人が主体的であろうとすることは、当然ながら、一人では成り立たない。絶海の孤島に一人流れ着いたものが、「よし、この島で主体的であろう」と力んでも、通りかかるウミイグアナが鼻で笑うようなものだ。
主体的であるということは、必ず他者との関係性で意味を持つ。それぞれの主体を認め合うことから、主体は初めて成立する。
共生とは、同化することではない。それぞれの個々の主体を認め合うということは、それぞれの個の違いを明らかにし、ある時にはぶつかり合い、軋み、対話を交わし、そのような圧を繰り返し、そうしてやっと「ともに生きる」という社会モデルが成長していく。
私たち誰もが認知症から「逃げることができない」。しかし、そのことを、当事者はむしろ「逃げるわけにはいかない」と、踏みとどまるようにして能動的、主体的に引き受け直したのだと思う。
当事者は、逃げずに認知症を受け入れ、そして認知症と自分の人生との、宿命的な因果関係を断ち切ったのである。
「認知症だから」とか「認知症なのに」といった自分を規定するものを次々と自分から取り外した。医学モデルの認知症のくびきから自分を解き放し、自分は自分であること、つまり、認知症であるとする、当事者という主体を確認したのだ。
そこにあったのは、たぶん、当事者たちの自分であるための「やむに止まれぬ思い」があったのだと思う。それが、「認知症とともに生きる社会」をさらに押し進めた「安心して認知症になれる社会」への深化なのだろうと、そんなふうに思っている。
そうそう、話は冒頭に戻って、認知症に「とても熱心な私(^^;)」である。
熱心というより、メディアにいたこともあって、関心を持ち続けてきたと言う方が私の感覚には馴染む。私の細々と持続する関心は、美しい誤解もあって傍目には、「熱心」と映ってくれたのかもしれない。
しかし、私の立場というのは、ありていに言えば、「逃げられる」のである。
「現場」を持たないというのは、不逞な無責任へと逃避できる。
しかし、ここにわずかな私なりの矜持があって、「逃げられること」が、私に「逃げるわけにはいかない」ことを課すのである。うーむ、言い訳めいてややこしい。
宵の明星を眺める時、「逃げてもいいのだよ」と、堕天使ルシファーが耳元にささやく。
その時、私のひ弱な「やむに止まれぬ思い」が発動して、逃げるわけにはいかない自分を取り戻させる。ここで逃げたら、わたしはなにものであろう、と。そのように怯え迷いつつ、なんとかここまで歩んできたのかもしれない。
幾重にも逆説を重ねるようにすれば、私はちっとも熱心ではない。そんな自分だから、関心を持ち続けることができたのかもしれない。
逃げることができる、という私は、だから、逃げるわけにはいかない。認知症が教えてくれた。
|第212回 2022.6.8|