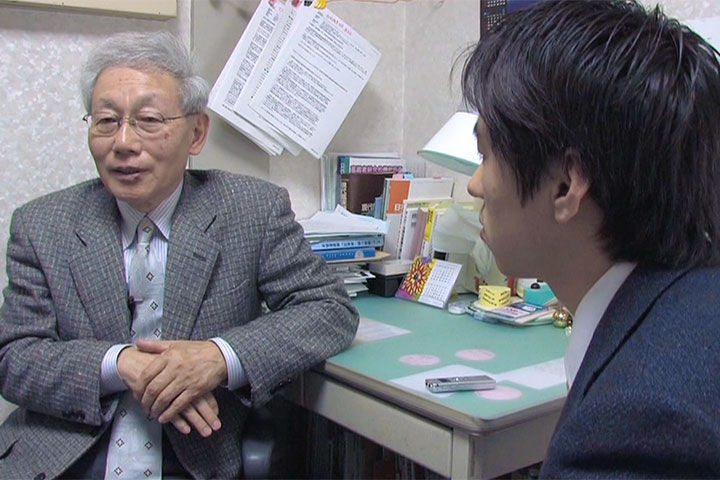▲茅野市の尖石縄文遺跡の原野。この集落に人々が暮らし土器を大量に生産した。共同体のふるさとをバックに国宝の土偶、仮面の女神とアリストテレスの政治学の文庫。
昔々のそのまた昔のような話から始めるのだが、かつての、のほほんとした東京下町の高校生(僕のことだ)が大学に入って、さて、かと言って青雲の志に燃えるというタイプでもないし、女の子には見向きもされなかったし(その頃の政経学部には女子はほとんどいなかった)、講義に出ようにもキャンパスはバリケードに囲まれていて、つまりはアテドもないキャパスライフが始まったのだった。
そのうちにあちこちのバリケードの中で読書会や集会が開かれて、殺伐な光景のバリケードの内が意外に牧歌的で自律的な学びの場となっていたりした。バリケードの中から、リヒターのバッハの音楽の捧げものが聴こえたりしていた、とは確か、立松和平か村上春樹だかが書いていた記憶がある。
僕もその頃仲間といくつかの読書会を掛け持ちしていて、ホッブスやウエーバーとかお決まりのマルクスの資本論の勉強会にも顔を出していたのだが、変な先輩がいてヘルメットとゲバ棒をそばから離さないのに、愛読しているのがリルケという理解に苦しむ人格で、その先輩がある日、「やっぱりアリストテレスだあ」と岩波文庫を振り回して言うのである。
それは僕たちの専攻科目の最初の必読書と言われていたアリストテレスの「政治学」で、先輩はその冒頭にいたく感激してしまったのだ。その冒頭にこうある。
「すべての国家(ポリス)は共同体であ り、またすべての共同体は何らかの善のために構成されている。(中略)すべての共同体は何らかの善を目指しており、あらゆる善のうちで最も有力な善を何にもまして目指すことこそが、国家と呼ばれるもの、つまり国家共同体(ポリス)にほかならない」
ポリスと呼ばれたギリシャの都市国家は、今の僕たちの考える国民国家とはずいぶんと風景が違う。それは城塞に囲まれた親密な共同体で、そこで詩や文学を朗唱し、文化や文明を育むアゴラという広場を持っていた。そこでひとえに目指すのが「善」なるものなのである。
これはどことなく当時のバリケードの中の雰囲気と相通ずるところがあった。だからあの変な先輩はアリストテレスの善なるものとしてのポリスに衝撃的共感を抱いたのだろう。
「いいか、アリストテレスは、政治学でも倫理学でも善を目指し、「よく生きること」を善なることの実践、人間の共通の目的と掲げているのだ。シンプルで高潔ではないか。それこそが俺達が目指す国家という共同体なのだ。それがどうだ、今のこの国のていたらくは。エーゲ海のあの青空と善なるものはどこに行ったのだ」
「先輩、エーゲ海行ったことあるんすか」
「いいか、国家がどうあったらいいのかとは、俺達の共同体はどうあったらいいのかということと同義だ。ポリスから生まれたのが、俺達のポリティクス(政治学)なんだからな。見ろ。この国はすっかりだめになっちまった。俺はもう、汚れちまった悲しみだ」
「先輩、それ、中原中也ですよ」
あれから遥かに時代は流れた。
あの頃は臆面もなく「善」をめぐっての議論を交わすことができた。流れた時間は、わたしたちの汚れちまった悲しみの青春だけではない。大きく時代を広げれば、国家はいまや、権能と権益絡み合う肥大したグロテスクなモンスターだ。ギリシャの時代では、国家共同体では人間の善が息づき、アリストテレスは政治も倫理も「よく生きること」を目標とした。
国家とは「人間」の共同体であるとは、そのまばゆさはなんであろう。
それから遥かに時代が流れ、今僕たちは、僕たちの共生社会を目指すとしている。それはエーゲ海の青空に輝いたポリスという共同体とどうつながるのだろう。
社会のありようを論じるとき、常にその哲学的基礎はこのアリストテレスのポリス、共同体に置かれる。今語られている「共生社会」もその源流を辿っていけば、やはりこのポリスに行き着くのである。「よく生きる」ことが出来る社会、人間はそうした社会なくしては存在できない。
では今私たち(ここからは人称がなぜか僕から私となる)が語る「共生社会」と「共同体」とはどのようにつながっているのだろう。アリストテレスを現代にお招きするにあたっては、その理路を整えておく必要があるだろう。
私は初夏からのシーズンに何度か蓼科の高原に滞在することをささやかなライフイベントとしているのだが、ここに茅野市の尖石縄文考古館がある。
ここには国宝の縄文のビーナスと仮面の女神の二体の土偶があり、その考古館一帯に縄文の発掘跡の原野が広がっている。ここに立つと、共同体の原始を見る思いがする。
縄文時代というのは1万年続いた。古代世界史から見ても稀有な安定的社会相であったらしい。
かつて、人は生存のために群れをつくり洞穴から原野に歩み出し、やがてそれは家族ごとの集団へと進化した。しかし家族制集団が連結するだけでは脆弱なままだった。家族はその中に赤子や老人を持ち、その弱さがつねに集団全体の不安定となった。
それが縄文時代になって定住と稲作が始まると集落化し生産が安定し、余剰生産物の蓄積は不安定な家族生産制を補う互助システムを生んだ。共同体の誕生である。
この国の共同体には、1万年に及ぶ祖先の記憶が張り付いている
私たちはこの共同体という風土をふるさとと呼びならわし、なつかしさの装飾を施してほとんど体質化した。
共同体の「貧しくても豊かである」とするおよそ経済思考ではありえない語法や、本来危うさが先行するはずのつながり合うことへの無条件な傾斜は、1万年の記憶の蓄積があるからかもしれない。困っている人がいれば、自分に困難があってもつい手を差し伸べてしまう。そのような共同体の底力のおかげで、私たちの社会は生き延びている。
だが、時代は流れた。
世界の共同体は大きな変化の時代を迎えた。アメリカの個人主義の台頭などから、あらゆる共同体に先立つ主体としての個人がクローズアップされた。個を共同体に埋没させるのではなく、主体として夫婦や企業や地域との関係性が検証され、組み直されていったのである。
そこから見えたのは、例えば地域共同体という家族のようなつながりの美化の陰で、家父長制の残滓が居残り、家族内の家事、育児、介護といった福祉労働は、いわゆる嫁とされる女性の無償労働に押し付けられてきたのである。
あるいは、地域共同体はその家族的同質性から、異質を排除してきた負の歴史をも併せ持つ。村八分と言われる因習である。またかつて、認知症の人は地域に出ることなく、地域によっては鍵をかけた離れに閉じ込める座敷牢の状態にもあったとされる。私たちの共同体は、抑圧の装置としても存在していたのである。
もちろん、全体から見ればこの国の共同体の居心地の良さは、豊かな文化や景観、福祉力も培ってきたことは評価されるべきだろう。しかし、その共同体は、今、過疎と高齢化、人口減少の急速な進行で消失可能地域となっている。
今、共同体を組み直すようにして改めて共生社会が言われている。
しかしその共生社会は、アリストテレスの「善なるもの」「よく生きる」ことの歴史の芳醇を継承しているのだろうか。
今の共生社会の提起は、少子超高齢社会での社会保障の財源限界を、生活者に押し付けようとしている口実に使われている。もはやカネはない。あとは皆さんで支え合いつながり助け合う社会を目指してください、と言わんばかりである。
更に言ってしまえば、認知症基本法の前句の「共生社会の実現を推進するため」の捉え方の浅薄も気になる。これを読み上げるだけで、もはや条文を読まずに分かったようなことを言う論調が目立ちすぎる。本来は、まず認知症基本法の内容を読み砕いてのちに、この前句の「共生社会」にようやくこのようにして立ち戻るプロセスが必要なのだ。それを「共生社会」と最初に答えが置いてあるので、そこで基本法をわかったつもりにさせてしまう。
今となっては議員立法の、大向うのウケ狙いのあざとささえ伺えるタイトルのような気さえしてくる。きちんと読み解き対話する私たちの側の手間ヒマを手離さないことだ。
アリストテレスは、「人間はポリス的動物」としたが、これは個人は本性によって共同体をつくって生きる存在、つまり社会なくしては個人は存在しないということだ。アリストテレスは、人間のありようから共同体のポリスを論じ、それを「善」を目指す人間の実践とした。そのような人間存在の原点から立ち戻っての共生社会の語りを、私たちは持っているのだろうか。
私たちが言い交わす「ともにいきる」「よく生きる」あるいは「ひとりでは生きていけない」とするフレーズは、紀元前4世紀のギリシャのひとりの哲人がアテネ市民に説いていた言葉の数々から継承されている。
共生社会を一片の紙っぺらの中の言葉でなく、歴史の継承の豊かな言葉として語りたい。