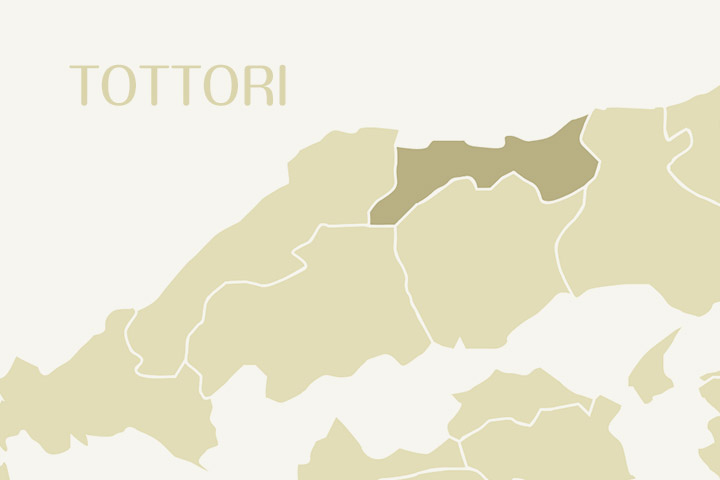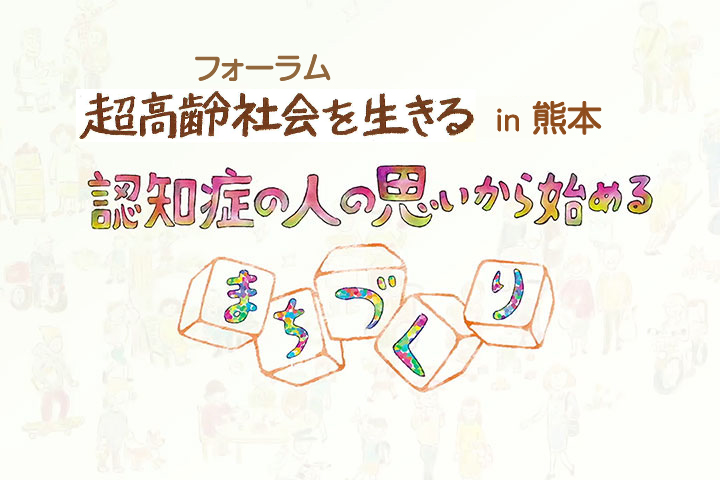▲あけましておめでとうございます。この社会をつくるのは、その成員一人一人の意識とふるまいです。新しい年もまた、この国の地域の人々の想いを汲み上げる一隅の井泉としてのコラムをめざします。本年もよろしく。
「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とは、ヘーゲルの「法の哲学」の中の一節である。
初めてこの言葉に接した時は、詩的で映像的で、神話に託された不思議な世界観にただ魅せられた。
ヘーゲルの哲学の省察に記されたこの文章は、ひとつの時代が、迫り来る黄昏という解体期に至って初めてその時代の本質が現れることを示している。
ミネルヴァの梟は、ある時代が終わった黄昏に、初めてそのことを私たちに告げるようにして羽音高く飛び立つ。コロナの時代とは迫り来る黄昏という時代の転換期だったことを、私たちはフクロウの羽ばたきにようやく知らされた。
そのようにして新しい年2022年が明けた。新しい時代が明けたのである。
コロナの日々の不安というのは、ひとつの時代の黄昏の中にたたずみながら、次の社会の姿が見えていない不安だった。それは新型コロナウイルスの不安というより、ここではないかどこか(Anywhere But Here)へどう歩み出していけばいいのかわからない社会にたちこめる不安だった。
去年の師走に第5回の「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式を開催した。
コロナの日々の中で全国各地での「認知症とともに生きる」ことの実践を取り上げたものだが、そこで気づいたことがある。
ひとつは、取り組みの紹介映像での人々の笑顔がまぶしいほどに輝くのである。そしてもうひとつは、「認知症」だけに意識や実践が集約されずに、自然に認知症が地域に溶け込んで、しかも明らかに変化や力の源になっている「共生」の地域が見えたことである。
暮らしというものは、どんな困難の中でも続けていかなければならない。それはいのちに関わることだからである。だから暮らしにはつらさがあり、喜びがある。SDGsが言われているが、まずもって持続可能でなければならないのは、いのちなのである。
暮らしの中の地域の人々は、コロナの日々につながりが途絶えたと嘆いているだけにはいかない。つながることが暮らしであり、それが生きることであることを生存の知識として持っている。コロナのせいにしてつながりをあきらめることは、暮らしをあきらめることであり、いのちをあきらめることである。
おそらくそんな思いが込められていたのが去年の「まち大賞」だった。
だから、ひときわ笑顔が輝いた。よく、介護研修などの場で年若い介護職が「お年寄りの笑顔が生きがいです」と、自身も満面の笑顔で報告する時、以前の私ならそのような発言はよくある定型の感想程度のこととし、聞き流していた。
しかし、この事態で言い交わす時、笑顔とかぬくもりと言った言葉には、その向こうに切実な「人間」への想いが深く響いている。
介護職の彼女が、高齢者の人とのケアを通じて獲得した人間の姿。認知症であるとか、高齢者であるとかを突き抜けて、互いに見たのはまぎれもなく、互いの「人間」の姿だった。そこにそれぞれのいのちが共振し、互いの輝く笑顔を生み出したのに違いない。
それが私の起点だ、と年若いあなたは、笑顔に託してそのように語ったのだ。
寒くなるとぬくもりが恋しい。
子供達が幼かった頃、フワフワのセーターで着ぶくれた上にマフラーをグルグルと巻き付け、さらにボアのついたコートの大きなポケットに両の手を突っ込んでは、ただ「ぐふふ」と笑み崩れていたっけ。
あれは単に「あったか」というより何か大きなぬくもりに包まれ守られているという安心が、無条件に幼な子の笑みを誘ったのだ。
寒くなると人のぬくもりが嬉しい。人恋しい。人がぬくもりを求める時、それは必ず他の人を想う。しがみついて親のコートのポケットに小さな手をねじ込む幼な子の真っ赤なほっぺ。
時代がぬくもりに恋している。ぬくもりは福祉の原点だ。
コロナの日々の迫り来る黄昏は時代の終末であるとともに、実は笑顔やぬくもりという身体言語によって、いのちのギリギリの地点から蘇生する人間の力を、時代の残照に浮かび上がらせた。
丹野智文氏が「いつも笑顔で」と言い、長谷川和夫氏が「ぬくもりと絆」を語り続けたのも、ともに人間回復への思いの結晶なのである。
思えば、コロナの日々はこうした「笑顔」や「ぬくもり」「絆」といった言葉をなぎ倒して進んでいった。「この事態なのだから」という、その「事態」は地域にうずくまる認知症の人や子供たちや困窮の人から暮らしを奪い、いのちを脅かした。いのちを脅かしたのは、コロナであったのか、政体であったのか。
私たちはこれまで笑顔やぬくもりや絆といった言葉が発する声を聞き逃していた。
この社会を語る選ばれた人々のシニカルなまなざしには、笑顔やぬくもりやきずなは、地域の片隅での情緒であり、散文の甘さとしか映らず、そのことを語ることは自身の鉄壁の論理をヤワにする恐れがあった。
かくして彼らの論考の演繹と帰納からは、笑顔もぬくもりも絆も全てふるい落とされ、数値と推計と論理によって、この社会がいかにダメなのか、なるべく先鋭な異議申し立てをすることに競い合っていった。ふるい落としたのは、笑顔やぬくもり、あるいは絆とともに、当事者の存在とその視点であることにきづくことはない。
コロナの日々は、時代の分岐点に私たちは立たされていることを実感させた。
その分岐点の一方は黄昏に沈みこむこの社会であり、もう一方は私たちの「ともに生きる」社会であり、それはまた少子超高齢社会というイバラの道でもある。
近所の公園に毎日、まるでカルガモの親子の行列のようにして保育士に連れられて保育園児たちがやってくる。揃いの帽子で、道路を渡るときには手をあげて右見て左見て、私たちの未来がやってくる。私たちの未来はデータの中にあるのではなく、いのちの連続の中にある。
新しい時代に向かって、私たちは今一度「人間」に立ち返るしかない。一人では生きてはいけない私たちは、人と人の間を生きて人間となっていく。そして、いのちをつないでいくしかない。地域共同体とは、横につながるとともに、時空を縦に、いのちをつないで物語を紡いできた。
笑顔やぬくもりや絆とは、私たちの暮らしの願いであり物語であり、そして、ひたすらの祈りである。
いのちをつなぐ。まだ見ぬいのちたち。未来のどこかで、はるかな君たちの笑顔がこのふるさとの地に満ちるなら、涙を振り払って、今できることがきっとある。
新たな年に「笑顔」や「ぬくもり」や「絆」を取り戻す。
希望を取り戻すようにして。