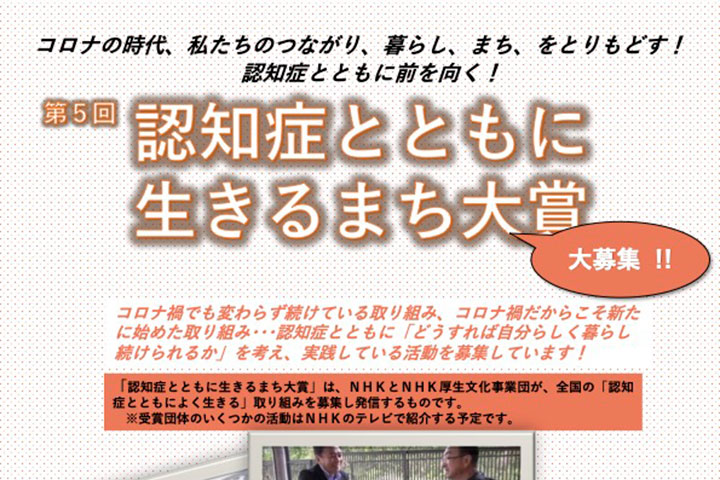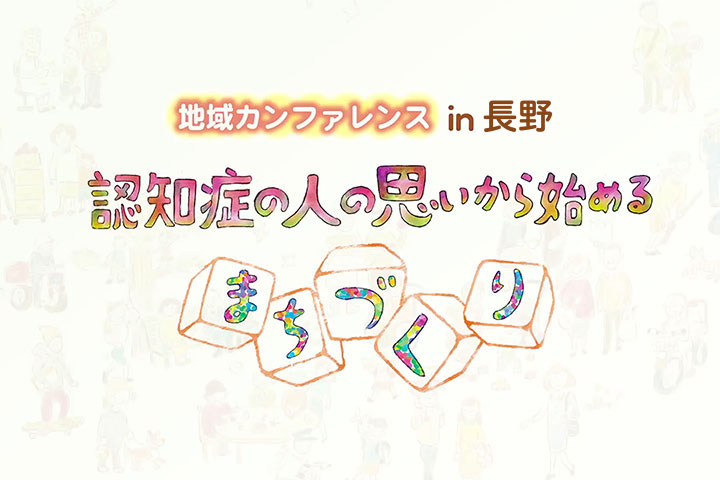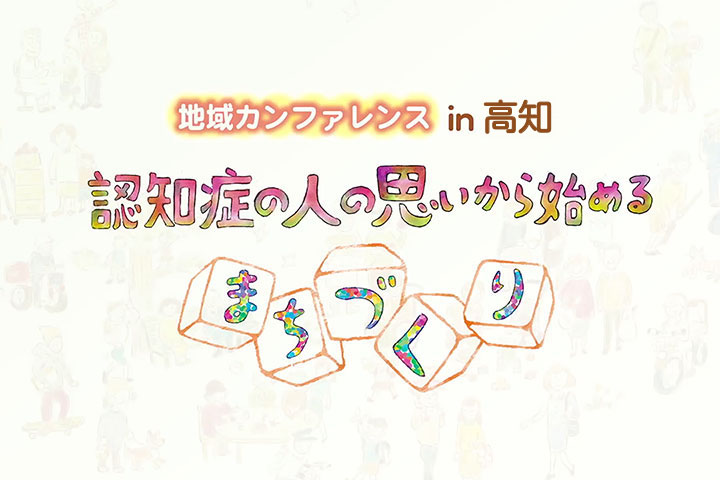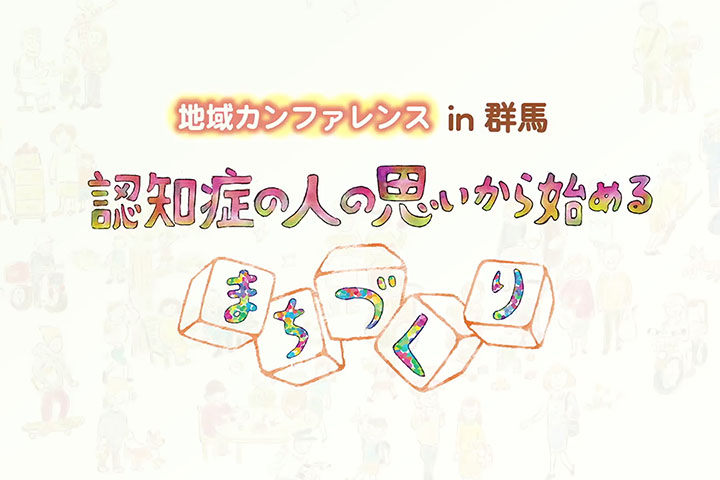▲桜の季節は旅立ちの季節でもある。認知症とともに生きる日々も、ここで大きく深呼吸し、花吹雪の中を歩み出したい。ささやかな認知症論の連載がスタートする。ご一緒していただければ…
桜の季節が近づいていますね。思えば、わんさと連れ立って花見に出かけられたのは2019年まででした。以来2年間にわたって新型コロナの日々が続いたわけですが、皆さんはどんな風に過ごしてきたのでしょうか。
なんとなく「疲れちゃった」と言うのが正直なところで、このパンデミックに何をのんきな、と言われそうですが、実はそんなにのんきな話ではなくて、これは案外と深刻な事態を方々に及ぼしていると思います。と言うのは、この社会というのは制度や政策で組み立てられているように思ってしまいがちですが、実は一人ひとりの毎日の暮らしの心情や実感の総和が決定づけているのです。世論といった表面に浮き上がっている現象よりもう少し深く潜航したレベルでのことといってもいいかもしれません。
「疲れちゃったな」と思わず口にするあなたの深層に何かが起きているのかもしれません。こうしたことには誰もあまり目を向けなかったり語られたりもしないのですが、当たり前の日常が奪われた中で、ただ徒労感、疲弊感が澱のように誰もの心深くに降り積もってしまった経験と記憶は、これまでなかったことと言っていいでしょう。
コロナの日々は果たしていつまで続くのかわからないのですが、それでもこの「疲れちゃった」一方で私たち一人ひとりが、これまでにはないまなざしで社会を見る、そんな機運も生まれてきています。生活者はしたたかです。めげるわけにはいかないのです。言ってみれば、これまで見逃していた大切なことをこの事態を透かすようにして見つめ、気づいた、そんなふうにも思うのです。
このコロナの事態を、次の時代を駆動する奇貨とするためにも、ここで深呼吸するようにして、今一度認知症とこの社会を捉え直すことが必要なことなのかもしれません。いい機会です。できれば、この事態を通じて、認知症を考える視点を今一度、皆さんとともにたどるようにして語ってみたい、そんな風に思って記すことにします。さて、どんな振り返りができ、それがこれからのどんな道筋につながるのか、では出発しましょう。
まずは、ここで中心的に考えたいのは「認知症とともに生きる」ということです。
これまで「認知症とともに生きる」という言葉はかなり浸透、定着していたところがあります。多くの自治体での高齢者施策の標語には必ずといっていいほど取り上げられています。言葉だけで実態は何も変わっていないと言われればその通りなのですが、ここではまずこの「認知症とともに生きる」というムーブメントの源流をたどることにします。
認知症の施策が大きく転換したのは2015年の認知症国家戦略・新オレンジプランでした。冒頭の宣言と言っていい部分を改めて読んでみます。そこにはこうあります。
「認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる社会の実現をめざす」
これがスタートラインでした。そこから「認知症とともに生きる」はありとあらゆる自治体などの冊子の文言として踊り、地域包括ケアや地域共生社会と言った施策に注ぎ込まれていったのです。
全国各地で、認知症は新たな時代を拓いていきました。まずは地域活動としてまちづくりや認知症カフェの実践が展開しました。それは小さくささやかでも確かな前進でした。それまで少子超高齢社会といった宿命的な課題に対しては、その不安と怯えを隠すようにして常にシニカルな「高齢者が増えることはマズイ社会」の論調が席巻していました。その中で全国の地域の一角で、新しい市民性を帯びるようにして「認知症とともに」が動き出したのです。
少子超高齢社会といった大きな言葉から考え下すのではなく、自分たちの生活感覚から「私たちの町はこうあったほうがいいんだ」と声を掛け合うようにして、スモールステップを刻むようにして前に進んできたのです。
この社会の課題は、ともすればすぐに制度政策予算といったレベルか、あるいは観念論での空中戦論議になりがちな中、自分たちの生活感覚から離れることなく、まちづくりに代表される「ともに生きる」取り組みは実践されてきたのです。
それまで「認知症」は、常に社会の課題、問題という文脈で語られてきました。そこから大きく転換させて、地域社会の隣人として受け入れることへの歩み出しが「ともに生きる」と言うことでした。言い方を変えれば、認知症を問題としてではなく、所与のものとして地域社会の未来を考える文脈に置き換えたのです。私はこのことはきちんと評価しておいた方がいいように思います。
が、しかし、なんと、どうしたことか、と、いくらでも悲嘆を込めた逆説を並べたいのですが、そこに新型コロナウイルスが襲ったのです。誰もが逃れることができない事態でした。そして、ウイルスは感染リスクとともに、実はこの芽生え始めたかのような「ともに生きる」ということをも襲ったのです。どういうことか。
感染流行の当初、こんなことが言われました。
このウイルスには誰もが感染しうる。それは言い換えれば誰もが当事者になるということだ。総当事者の時代と言っていい。一方、認知症もまた誰もがなりうる。だとすれば、ここに「誰もがなりうる」という共通の当事者性が成立し、「認知症とともに生きる」の基盤が確立するのではないか。
「認知症とともに生きる」と言った共生モデルの前提は、認知症を「自分ごと」として引き受けることです。しかしこれは、言うは易し、の典型で概念だけは流布してもなかなか実感として根付かせるのは難しいところです。そこにこのウイルスの事態です。誰もがなりうる事態に巻き込まれた以上、それは誰もがなりうると言う「自分ごと」を経験することになるわけですから、まさに当事者性を誰もが持ち、ここに「認知症とともに生きる」は自分ごととして強化されるであろう、そんなふうに語られました。
しかし、そうはなりませんでした。ウイルスは私たちの「ともに生きる」の、その基盤のもろさを暴き立てたのです。
新型コロナウイルスの事態で何が起きたのか。
それは感染した人や感染者を出した施設などへの誹謗中傷、そして差別があちこちで起きたのです。SNSの根拠のない情報がそれに輪をかけました。そうした誹謗や中傷をした人々は、別に差別的な言動をしていた特定者ではなく、私たちの地域での誠実な生活者でもありました。そうした人々が自らのせっかくの共生感覚を突き崩してしまったのです。
それは私たち自身も体験したことです。電車に乗ればマスクをした乗客誰もが感染リスクに見え、街を歩けばマスクがずれていたり、大声で連れ立って話すグループを険しい目でなじる自分がいたはずです。
誰もが感染しうることが、ともに生きる当事者性になるどころか、異質を排除するこの社会の負の側面をあらわにしたのです。
私自身も感染しないように律儀にマスク、手洗いとうがい、密を避けると言う行動をとりながら、いつしか感染者を含めた異質の存在をひたすら排除する側に回っていたのではないか、そんなふうに思うことがあります。なにか、ウイルスの底意地悪い嘲笑が聞こえるようです。
残念ながら私たちの「ともに生きる」はもろかったのです。
このコロナの事態で、「認知症とともに生きる」取り組みは打撃を受けたと言われます。地域でのつながりが途切れ、会うことも語り合うことも避けなければならない日々は、確かに地域活動に取り組む人々にはつらい事態であったことは確かです。しかし、同時にこの機会に私たちは、私たちの「ともに生きる」と言うことを今一度検証する必要がありはしないでしょうか。
なぜかくも私たちの「ともに生きる」と言う共生モデルはもろかったのでしょう。
それはたぶん、「ともに生きる」ことが獲得したものではなく、与えられたものとしてのスタートをしているからかもしれません。
少し遠回りをするようですが、なぜ「共生」なのか、その流れをたどることでより明確に「認知症とともに生きる」ことの再検討の視点が見えてくるように思います。
「認知症とともに生きる」には先行モデルがあります。それが障害者運動で、これは闘いの長い歴史を持ちます。戦前からの視覚・聴覚障害者やハンセン病、身体精神障害者などの社会運動から2006年に国連で採択された障害者権利条約に至るまで、それは奪われた人間を取り戻す闘いの歴史でした。こうした歴史が権利擁護の柱となって、それ以前からの世界のブラックピープルや女性の現在までの差別との闘いと合流してきたのです。
認知症当事者が掲げる「私たち抜きに私たちのことを決めないで」のスローガンは、実は障害者権利条約を検討していた国連の特別委員会での世界盲人会連合会長のキキ・ノルドストロームさんのスピーチで語られた言葉です。この時会場には、障害者委員たちの歓声と拍手がわき起こり、いつまでも鳴り止まなかったと伝えられています。今の認知症当事者活動は間違いなく、世界の障害者運動を引き継いでいます。
こうした全体性からコロナの日々の現実を見るとき、思えば次々と繰り出されたあの自粛要請の中でもついに地域の生活者のどこからも「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の声は聞こえてきませんでした。私たち抜きに、当たり前の日常が奪われて2年経ったのです。誰もが、この事態だからしょうがないよね、と見過ごす中で、認知症の人や子供たち、施設の高齢者の暮らしにコロナのリスクはひたすら皺寄せされたのです。
ともに生きる私たちはどれだけ認知症の人の暮らしや思いを代弁できたのでしょうか。「ともに生きる」は仲間内だけのことだったのでしょうか。
例えば、自治体などの冊子での「認知症とともに生きる」にはほとんどイラストが載っていて、そのほとんどは、認知症や高齢者のご夫婦が中心に置かれ、その左右に老若男女の地域住民が、手を取りあわんばかりに、誰もがニコニコと笑顔で並びます。こうした図柄にケチをつけるのはまことに大人気ないのですが、ここに私たちの「ともに生きる」ことの限界があります。
さまざまな見方があっていいのですが、私は「ともに生きる」ということはそんな牧歌的図柄で描かれるものとは限らないと思います。そこにあるのは同質で均質な私たちの地域社会を前提としていますが、すでに同質均質な地域社会の姿は失われています。今や多様性と共生を併存させながら押し上げていく地域社会の創造へと、「ともに生きる」は挑戦しなければならないのです。
認知症とともに生きるということは、認知症の人とだけ仲良くするということではありません。
コロナの日々に、感染者を数値と匿名の中に閉じ込め、接触しないことを掲げる感染対策のもとで、彼らを異質な存在とし、排除の対象にしたのは私たちです。
そこには、かつて痴呆の人々を収容、隔離、拘束していた暗黒史といっていい歴史と重なるところがありはしないでしょうか。誰もがなりうることを共生ではなく、恐怖の中に捉えてしまった歴史の継続の中に私たちは生きています。
ともに生きるということは、痛みを覚えながら自分が変わることです。そのことをどう自分の中にはぐくめるのか、どう考えればいいのか。
と、ここまで記したところで字数がつきました。せっかくいいところまでたどり着いたのに、あとは次回に続くのです。
そう、このコラム、連載なのです。お楽しみに、と言っていいのかどうか・・・
ではでは、to be continued.(つづく)
|第203回 2022.3.8|