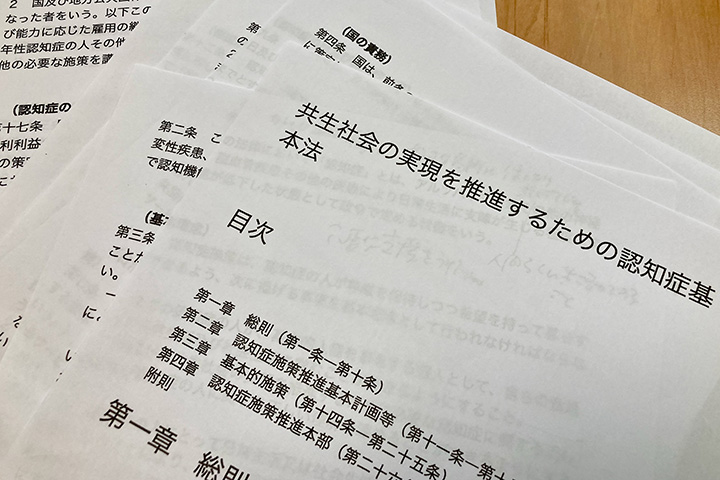▲私の職能としては、語る、伝えるということがあるのだが、そのためには聴くことの蓄積が必要。実感としては、100のインプットがあって、ようやくひとつのアウトプット。聴く力を鍛えるしかない。
認知症を考える時、私たちはまず「認知症とは」と語り始めます。
認知症当事者は、「わたしは」と語ります。
私はこの立場の違いの認識が重要だと思います。共生とはそもそも、同質均質な中に緩慢にたゆたうものではなく、異なる価値観を背景にした人々同士が、その異質をすり合わせることで生まれる緊張とエネルギーで社会を駆動していくものだと思います。
その共生モデルである「認知症とともに生きる」ことを社会実装するための確実な手がかりは、私たちの側の「聴く力」です。
認知症の当事者発信が社会を変える力を備えたとするなら、それは聴く人がいたからです。
聴く人がいたから、当事者発信が成立し、そして当事者発信が聴く人を育ててきました。この相互性が共生、共に生きるための起点であり、そして原型だと思います。
改めて聴くこととはどういうことなのでしょう。この社会の人との関係の健全性が問われているとするなら、それは「聴く社会」となっているかどうか、と言いかえられます。
世界には途切れることなくパルスのようにして、SNSなどの情報が飛び交います。そのことの有用性を否定するものではありませんが、そのためには「聴く社会」が基盤として存在していることが必要です。
にぎやかにSNSのやり取りをする若い世代が、ふとひとりの自分を感じた時、深い不安や孤立を感じる時があります。絵文字やピースサインの笑顔が行き交う自分の時間が途切れた時の絶望を、この社会は生み出しています。交差点の人混みの中で信号を待つ時、ふと、群衆の中の孤独を感じる若い人には、聴く社会が不在なのです。
語ることが発信であり、聴くことが受信であるという機能で分けると、当事者発信の意味は捉えられません。
語るという発信は能動で、聴くという受信は受動と考えがちですが、当事者の声を聴くこととは、その声を引き受けることであり、自分に問いかけ、能動へと循環運動につなげていくことです。たとえば、まちづくりとはそうした循環がもたらすと考えてもいいのかもしれません。
とは言え、こうした理路を整然とすることにはあまり意味はありません。
ここでは聴くことを現実の自分の感覚に馴染ませるようにして、ひとつひとつをたどることが必要なのだと思います。
当事者の話は、どのように聴いてもいいと思います。初めからこう聴くべきだ、と言った規範性に縛られると、当事者の声を聴くことの本質を損ねます。当事者の声に過剰な意味づけをすることなく、素直な自分の問題意識で経験することが一番です。
とは言え、せっかく当事者の声に接するなら、なにかしらの補助線を引くようにして、ここでは、あらためて私なりの聴くことをたどってみたいと思います。
私は認知症当事者の話を聴くという経験には、不思議な力があると思っています。
それは、聴く人の中で自分との対話が始まるような経験と言ってもいいのかもしれません。当事者の話を聴く時、認知症であるかどうかは後景に退いていきます。「認知症」の話ではなく、「その人」の話を聴くことにいつしか集中していきます。
最初から認知症の話を聞いてやるぞ、と意気込んでしまうと、変な言い方になりますが、実は「認知症」を聴いたことにはならないのです。
「認知症の話」をわかろうとしすぎるきらいがあるからです。わかろうとするのは、結構アブナイところがあります。それは自分の中の認知症観を基準にしてわかろうとするからです。
つらいことやできないことの克服という物語があなたの中にあらかじめ組み込まれていて、当事者の話をその物語として聴いていくなら、それは「良い話」「感動の話」として、わかったつもりになってしまうかもしれません。それはあなたの中の認知症観を変更無用であるとして無意識に温存させてしまいます。だから感動の話とすることで、自分を安心させているのです。
私はむしろ、わからないことを確認することが大切だと思っています。
そもそも、あなたは「認知症であること」がわかるのでしょうか。認知症の人の話を聴いて、もうそれで「認知症はよくわかった」と言ってしまえるのでしょうか。
もちろん、よくわかりましたと笑顔で答える人がいるわけですから、それはよかったですねというしかないのですが、私は認知症当事者の声を聴いても、それで認知症の人のことがわかりえたとはとても言えないのです。
わかりえない他者と出会うことは、こちらを不安定にします。ですが、認知症をわからない自分がいること、それはそのまま自分を検証することにつながります。認知症の人をわかりえないことによって、初めて、自分の中の認知症に出会うのです。だから、「わかりえない他者」がいることをわかる、つまり認めることが極めて大切なのだと、私は思っています。
誰もが経験する思春期、反抗期に親に向かって「父さんには、オレのことがわかるはずがない!」と叫ぶ時、実はその叫びで、それまで自分でもわからなかった自分を発見するのです。親にはわかり得ない自分を見つめ、自我を抱きしめるのです。親を、わかりえない他者としてみつめること、それは庇護の翼に守られてきたか弱いヒナの自立の時で、それが成長というプロセスです。
認知症の人はそのプロセスの先行者です。自分でもわからず、周囲にもわかってもらえない自分を見つめ、そしてわかりえない他者とともにこの認知症社会を拓いてきたのです。
「認知症とともに生きる」を共生の本義とするためには、わかり合えるという立場より、わかりえないという前提に立つことが必要だと、私は思っています。
認知症をただ、表面的にわかろうとするのは、えてして、いわゆる「健常」の側に取り込んでしまうことにつながります。それは自分達に都合のよい認知症者像だけを受け入れることになってしまいます。
認知症をわかりえないとすることは否定や排除ではありません。いや、丁寧に言えば、否定や排除に傾いてしまうかもしれないざらついた理不尽やリスクを抱えることで、より包摂をはぐくむ方向を強化させることになると思います。
共生モデルが仲良しクラブではなく、多様性を包み込んでのイバラの道であるとは、そういうことです。ただ、その多様性とは、わかりえない他者とは限りません。
多様性は、私たち一人ひとりの内面にもあります。ひとりの人の中には、たくさんの自己がいます。健康な自分もいれば、病いや障害の自分も考えられます。そして、認知症の自分もまた、どこかに存在します。誰もが人生の時間軸に沿って、そうした多様性を自分に内在させているのです。
認知症当事者の声を聴くということは、自分の中の多様な当事者性の発見であり、そこに自分と自分の認知症との出会いがあるのだと思います。
と、ここまで語ると、「えー、認知症の人とわかりえないなんてえ、悲しすぎませんか」とか言われそうです。そうですよね。わかり合えた方がいいですよね。でもね、だからこそ、わかりえないと思い定めることを前提にしたいのです。
それに、こんなことは本当は言いたくはないのですが、当事者発信に対するやたらな正統化や無誤謬化の受け止めを回避して、フラットに素直に聴くことを、あなたの側で成立させるための手順でもあるのです。
どうも、認知症に意識が向きすぎなのかもしれません。認知症を聴くのではなく、その人を聴くことが必要です。わかりえないということが、認知症の人にとって悲劇的な事態と受け止めてしまっていませんか。
恋人同士、だとか、長年連れ添った配偶者同士であっても、完全にわかり合えるものなのでしょうか。愛情表現のメタファーとして「わかりあってるふたり」とのろけるのは勝手ですが、本来はわかりえない中だからこそ、際限なく語り合い、耳を傾け、つながるのです。わかりえないことの前提でつながる関係を、愛することと言います。それを私たちは育てることができます。それは共同体を創ることであり、そこにあるのは確かな「聴く社会」という関係性です。
認知症とともに生きる、ということを特別な関係性として切り分けるのではなく、生きることをともにする地域社会がまずあって、そこに認知症の人がいる、というふうに考えられませんか。
当事者が発信することで、「聴く力」は、医療やケアの人々によってリレーされ、今ようやく私たち地域生活者にバトンが渡されました。
それはまた、「認知症の力」が手渡されたのだと、私は感じています。
つづく
*「認知症とともに生きる」ための深呼吸 のタイトルを、「認知症とともに生きる」ノート に改題しました。
|第208回 2022.4.21|