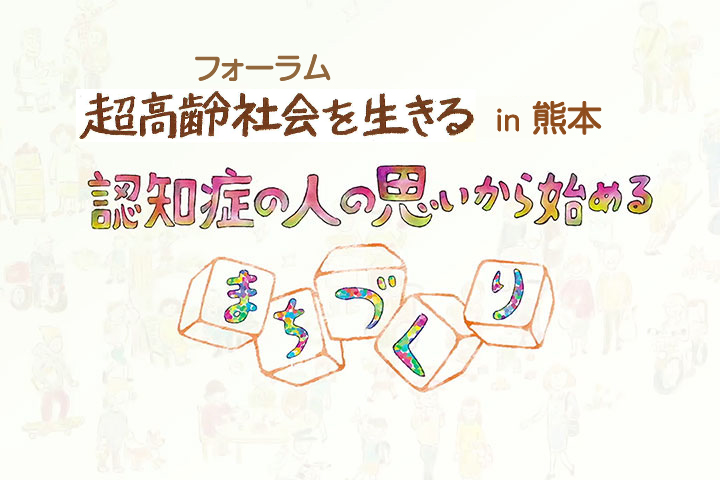▲「認知症とともに生きるまち大賞」表彰式の様子。上段、2018年、下段、2019年の受賞団体の皆さん。コロナの事態でこうした風景は見られなくなったが、各団体の取り組みはEテレ、ハートネットTVで放送される予定。
今年もNHK厚生文化事業団の「認知症とともに生きるまち大賞」の受賞団体が決まった。
その詳細はNHK厚生文化事業団のHPに掲載されており、またNHK Eテレのハートネットテレビでも放送の予定なので、全体はそちらに譲るとして、このコラムでは、このコロナの事態に改めてこの「まち大賞」が何を問いかけ、何を引き受けようとしているのかを見つめてみたい。
そもそも、ここで言う「まちづくり」とはどういうことか。
ここでの「まちづくり」とは都市計画や建築というのではなく、「まち」とは、そこに息づく人々の暮らしの舞台の風景と言っていい。
暮らしの舞台としての「まち」はもちろん具体的な「町」や「街」であると同時に、「働く」ことや「商い」であったり、あるいは命が生まれ、育ち、老い、そして亡くなる一連の人間の営みをも含んでいる。
かつて、「まち」はそのような風景として誰もが当たり前に思い浮かべることができた。
「まち」とは、ともに暮らす共同体であることは自明の前提だった。
しかし、その牧歌的な共同体は、この社会の大きな動きに呑み込まれていく。地方から都市への人口の大移動。地方の若年は流出し、逆に人口集中の都市部では、雑多な集合住宅と大規模なニュータウンの林立となり、まちはタウンと名付けられ、そこに暮らす人々は壁一つで隔てられていながら互いの距離は果てしなく、住民は長距離通勤、長時間労働に適合するスタイルとしての核家族を選択し、毎朝マンションの鍵をガチャリとかければ近隣の煩わしい人間関係を置き去りにして通勤できた。
地方はそのフィルムを反転させたネガの風景で、過疎地に取り残されたような高齢者たちは、息子娘たちの幸福を思い、これでよかったのだと日々をよるべなく過ごす。
失われたかつての街や村の風景には、経済成長の再配分としての補助金や福祉施策がつぎ込まれたが、それは人々が手塩にかけるように思い込めてつくり上げたふるさとの解体につながっていった。
今の「まちづくり」はそのようは背景を持つ。
このまちづくりは、どこかの官庁や建築事務所の会議室から始まるのではない。まちに住む人々が夕焼けを眺めながら、これでいいのかしらという気づきから始まるように、主体はそこに住む人々の暮らしの感覚が心中にかすかに打ち鳴らす警鐘から始まった。これでいいのかしら。
自分のこれからの人生をここで過ごすことになるとしたら、これでいいのだろうか。何より子供たち次の世代に、このような地域を彼ら彼女のふるさととして手渡すことができるのだろうか。
でも、どこから手をつければいいのだろう。
そこに「認知症」があった。
「認知症とともに生きるまち大賞」の源流は18年前の2004年の「痴呆とともに暮らす町づくり」にあった。その実行委員長があの長谷川和夫氏、選考委員長がさわやか福祉財団理事長の堀田力氏だった。まだ、痴呆と呼ばれていたときにすでに「痴呆とともに暮らす町」という共生を標榜する先駆的なイベントが始まったのだ。
痴呆から認知症への呼称変更の年に、社会に向かって打ち出された認知症の人との共生モデルは、経済繁栄の中で失われた誰もの「共に暮らすまちづくり」の再生につながった。
そして、その2004年という時代は、介護保険制度が始まって間もない時期である。
介護保険制度の施行は、福祉の基盤を大きく変えた。それまでの措置から契約の制度となり、与えられる福祉から、権利として利用する福祉への転換だった。すでにここに現在の当事者性につながる権利が埋め込まれていたのである。
そうした新しい時代への機運の中で「認知症」が語られ始めたのがこの頃であった。
もちろん依然として課題とし問題化する認知症観は色濃かったのだが、しかし、「認知症とともに生きるまち」は、超高齢社会の未来を市民の側に託し、どこか祈りをこめるようにして構想された。
しかし、「まちづくり」とはなまやさしいものではなかった。地域の人々が主体としてのまちづくりにお手本はなく手さぐりが続く。
最大の難関は、地域に認知症がいないことだった。
もちろん、いないわけではない。認知症の人が地域に出て来られない現実があり、なんとかそこを切り拓き、認知症の人の存在を可視化する取り組みが必要だった。それが、各地で展開された認知症カフェや居場所づくりだった。
そこでは、認知症の人や家族を一箇所に集めるようにして思いつく限りのサービスが提供された。今からすれば、認知症の人や家族ばかりを集めて対象化し画一の支援の提供に終始したことは批判されるだろう。そこにあったのは、認知症ではない側の良かれと思う恩恵の行使だったとして。
しかし、それは今だから言えることであって、俯瞰すれば、まちづくりはそのようにして進んでいったのである。ここからの学びがなければ今のまちづくりには到達していない。
まずは地域に認知症の人が出ていくことで、地域の人々は「認知症」と出会ったのである。
もちろん、認知症を自分に引き受けるようにして内実化することは簡単ではない。その簡単ではないことが、実は地域にイノベーションを積み重ねさせた。
今の認知症カフェや居場所の中には、そのようなプロセスを経て、かけがえのないまちづくりの拠点になっているところが多い。
認知症の当事者発信もこの下地がなければ、現在のような成熟を見せはしなかった。
もちろん、当事者との相互理解といった調和的な成果がすぐもたらされたわけではない。当事者の話は、どこか認知症ではない側からは、「認知症のつらさを克服した成功物語」として消費されたところもあった。しかし、そのようなことも含めて、当事者発信はジリジリと地域の中で成長していった。むしろそのような受け止めがあることで、地域の持つ課題や方向性を修正できたのである。
まちづくりの成功や成果の側面だけを見るのではなく、試行錯誤や誤謬の側面を見つめることが必要なのではないか。
そこでの、「認知症の人のため」に「良かれ」と思って濃厚な「支援をしてあげたい」とする善意をまずは認めることだ。それを間違いだとして、否定して葬り去ることがほんとうにいいのだろうか。そこからの気づきがなければ次には進めない。
私も、認知症の人々とは「支援するされる」といった非対称の支援ではなく、フラットな水平の関係性が大切だと思っている。
ただ、このことは、これが正解であるとして与えられるものではないだろう。そうではなく、懸命に善意の限りで支援してあげている人が、どこかで、それは自分が「健常」の側に立って、認知症の人を「弱者」に追いやっていることに気づかなければ本当の「認知症とともに生きるまち」に積み上がらない。
失敗のないまちづくりは脆弱だ。人もまた自身の錯誤や失敗を引き受けるところから、新たな責任を果たす役割を見出していく。
「認知症とともに生きるまち」に完成形はなく、あるのは絶えざる問い直しである。
例えば、全国的にも先駆的であるとして大きな評価を受けた福岡県大牟田市の、2004年に始まった「認知SOSネットワーク模擬訓練」は、20年近くの実績がありながら、そこに深く関わる人々からこれでいいのだろうかと問い直しが始まり、現在は本人の声を基点として「誰のためか、何のためか」と新たな視点での取り組みを継続している。
これまでの「まちづくり」として評価されてきたどの地域でも、実は常にその活動を見直しながらより広く深いまちづくりに成長している。そして特徴的なことは、そこからその地域のリーダーたちが数多く育っていることだ。まちづくりはひとづくりなのである。
まちづくりは、そこに住む人の主体性で動いていく。だとしたら、そこに暮らす人が自分を切り離すことはできない。「認知症とともに生きるまち」を自分を切り離すことなく考えるなら、それは「自分とともに生きるまち」としてもいいはずである。
今年の第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」のどの取り組みも、そこには必ずそこに至るまでのプロセスがありまたこれからの道筋がある。
今年の受賞団体の取り組みそれぞれを、対話するようにして読み取ってもらえればと思う。