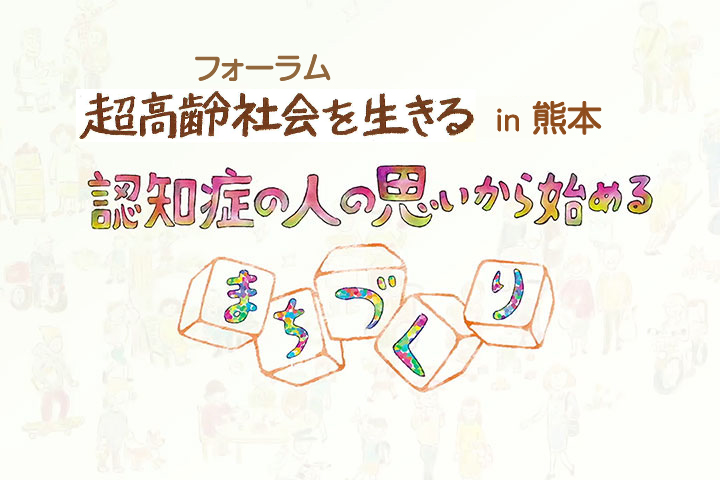▲NHKの子ども向け番組の「フクチッチ」で認知症を取り上げた。子ども向けだからこそ、私たちが観なければならない、そんな番組だ。この社会は認知症を「イチから」学び直す必要があるのかもしれない。
NHK Eテレのハートネットテレビに「フクチッチ」という番組がある。
そのコンセプトは、「福祉の知識をイチから楽しく学べます!」という教養バラエティなのだそうだ。ただし、ポップなスタジオのひな壇に出演者が居並ぶと言ったバラエティのしつらえにだまされてはいけない。これはなかなかどうして、手強さを秘めた新しい時代の福祉論の誕生なのかもしれない。
そのフクチッチで認知症を取り上げた。
そこでの認知症の語り口は、とても新鮮だった。
スタジオには、医師の數井裕光さん、認知症当事者の山中しのぶさん、そして出演者として進行役の風間俊介さんと天才テレビくんのテレビ戦士の小中学生たちである。
となると、そうか、これは子供たちが認知症について学ぶ番組なのだな、と思うだろう。確かに広義ではそう言ってもいいのだが、観ながら私は、ここにあるのはいまのこの社会が最も必要な「認知症」へのアプローチだと思いながら引き込まれていた。
番組ではまず、グループホームに暮らすあきこさんという婦人の一日が映像で紹介される。あきこさんは認知症のある人である。いつものグループホームの日常が映し出されるが、特徴的なのは映像とともに、常にそこにスタジオの子供達の声と表情がワイプ窓に映り込んでいることだ。
スタジオの子供達の反応がすごい。すごいというのも変なのだが、実に的確でシャープなのだ。
例えば、朝、スタッフが部屋にあきこさんを起こしに行くと、カメラに気づいたあきこさんは扉の隙間から外を伺い、「恥ずかしいから出られない」とはにかむ。すぐさま子供たちは「お茶目!「かわいい」と反応する。ハナから、「認知症」ではなく「人」を見ている。
あきこさんの日常が続く。台所で料理するあきこさんの姿。あれこれ迷いながらも施設スタッフのサポートを受けながらのかいがいしい朝食作りだ。
あきこさんの包丁さばきに子供たちの声。「さすがの手つき」「ドラマに描かれるつらさは感じないね」 ドラマの中のステレオタイプの認知症の描き方を、無意識ながら指摘したりするのだ。
さらに、食材として配達された魚のパックを受け取ったあきこさんが、その鮭のパックをしげしげと見つめてどうも名前がわからない。「なんでしょう、これ。わからない」とあきこさんがつぶやく。それに対する風間俊介さんの言葉に私はのけぞった。
「安心してるからわからないってちゃんと言えるのかな」
ここにあるのは、確かに子供たちの「学び」である。彼ら彼女たちは、認知症を学んでいる。誰から学んでいるのか。それはあきこさんから学んでいるのである。認知症の本人から学んでいる。
番組では、映像にそれぞれ補足としてのテロップ情報が画面下段に示される。
あきこさんがパックの魚の名前がわからなかったところには、「認知症の症状・モノの名前が出てこない」とテロップが出ていた。私たちは、「モノの名前が出てこない」という医学情報が示されれば、すぐさまそれを認知症の「問題」として捉える。
しかし、風間俊介さんは、あきこさんの映像と合わせ見ることで、「わからない」と言えるほどに本人が安心できる環境なら、それは「問題」とはならないと直感したのだ。
彼は認知症を、情報から学ぶのではなく、人間から学ぶ。付け加えれば、情報の本来性を生かしている。
さらに言えば、ここにあるのは「学び」というより「気づき」である。「学び」は外からやってくるが、「気づき」は自分の中のもうひとりの自分の発見である。
スタジオの彼女彼らのそれぞれの「気づき」は、言葉にすれば「認知症になってもできることがある」とか「安心の社会」というほぼ標語化した概念とも言えるのだが、そうした標語の上滑りはここにはない。なぜならそれらは、彼ら自身の「気づき」が生み出し、自分が獲得した「認知症」だからだ。
彼らは、ここで「認知症」と出会ったのだ。認知症のある人としっかりと出会って、気づき、自分の中の自己を押し上げるようにして、自分の認知症観を変えていったのである。これが本体の認知症へのアプローチであって、ここでは認知症の存在が彼らの若い力を育てている。
さらにフクチッチのすごいのは、あきこさんの一日と子供達の反応を、美しい物語として調和的に終わらせていないことである。
映像の終盤、夕暮れ時になるとあきこさんの心情は不穏と不安に包まれていく。
「わかんない。何しているかわかんない。わたし」
「おかしいよ。わたし、おかしい」
スタジオの空気も一変する。彼女の「わかんない」がわからない。「不安なのかなあ」、スタジオのつぶやく声。
映像の中のあきこさんが、施設のスタッフにしっかりと目を据えて放ったのが、「頭に来ている」の言葉だった。
「頭に来た。自分の生活ができない。それが頭に来てんの」
「自分の生きざまを決めて生きたいの、私は。ただ生きてりゃいいんじゃないの」
この言葉にスタジオは息を呑んだ。「すごい」をくりかえす。
すごい言葉だ。人間存在、実存の地平を開くようにして発している。認知症のつらさは、疾患ではなく、自己存在の不確かさに関わっている。
スタジオの若い世代は、あきこさんの言葉を受け止めた。
どう言えばいいのだろうといったつかの間があって、「本人が一番悔しいのね。あきこさん、悔しいんだ」「悲しいとか寂しいとかじゃないんだな」
キミたちは、とてつもなく深いところまでの「気づき」を得たのかもしれない。あとはその「気づき」を言葉と関わりにつなげればいい。
番組はこのあと医師の數井裕光さん、認知症当事者の山中しのぶさんたちとともに、専門的知見を挟んで、岡山県笠岡市のきのこエスポワール病院の取り組みの歴史へと続いていく。しかしここでも一方的な情報ではなく、様々な角度からの気づきをスリリングに積み重ね、最後には誰もの本質的な了解としてパーソンセンタードケア の地点にまで到達してしまうのだ。彼ら彼女たちの「イチからの学び」の確かさには圧倒される。
が、この稿の本意は、番組の紹介や解説ではないのでこれ以上の記述は抑制したい。あとは是非、諸氏はフクチッチで、認知症との出会いと「気づき」の体験をしていただきたい。(出稿時には後編は未見)
フクチッチのコンセプトは「福祉の知識をイチから楽しく学ぶ」である。番組から子供たちに向けての呼びかけである。
しかし、大人の世界であるこの世間は、そもそもイチから学んじゃいなかったのである。認知症にしろ福祉にしろ、いつも誰かの借り物の知識の受け売りで、「認知症になったら人生の終わり」のスティグマをそのままにして、「認知症とともに生きる社会」の看板を掲げているのが、この社会である。
「自分の生きざまを決めて自分の生活をしたい」とするイチから組み立てる生き方ができる社会となっているのか。それが安心の社会なのだ、と、認知症のある老婦人が放った言葉を、子供たちはしっかりと受け止めた。彼女の悔しさを読み取った。私たちはどうか。
これは子供たちが学ぶのではなく、大人が子供たちに学ぶ「認知症」の番組なのである。
いささかの余談ながら、このフクチッチを制作したのはNHKの川村雄次ディレクターである。
彼は認知症を20年以上ライフワークとし、クリスティーン・ブライデンを紹介する番組を何本も制作し、この国の認知症当事者の取り組みを丹野智文さんとともにメディア発信してきたディレクターだ。
いわばこの国の認知症状況の最先端の伝え手であった彼が、認知症を「イチから学びます!」とするこの番組に取り組んだのは、なぜだろう。
それは、このコロナの日々をかいくぐったこの社会と認知症の「イチから」のリ・スタートの思いがあったからではないか、私は勝手にそのように思っている。