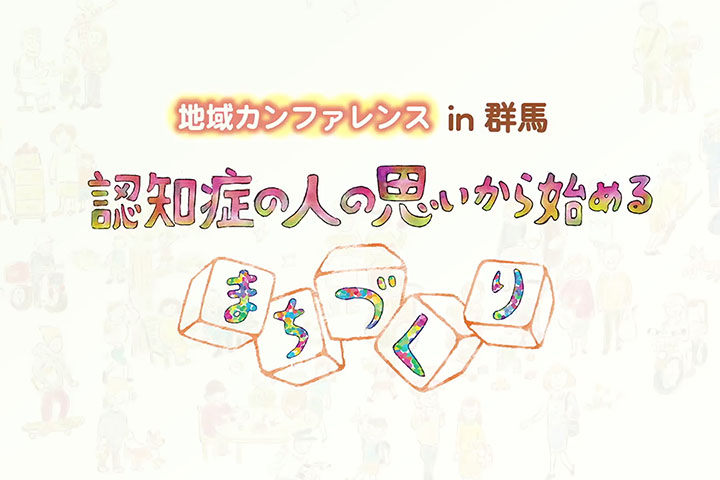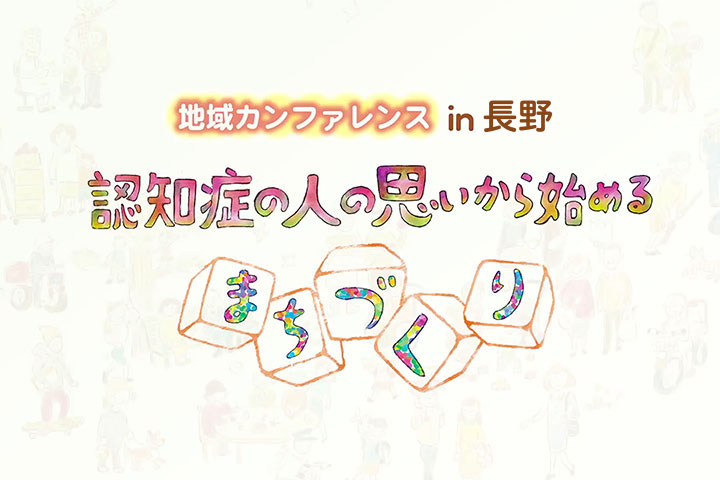▲最近のお気に入りのカップはフィンランドのブランドのカップ。こうしたカップ片手に何もしないひとときを持つというのが、実はどこかで豊かな時間を生み出すのかもしれない。何もしない怠惰への言い訳かもしれない。
朝のルーティンで、コーヒーを淹れる。
それだけのことなのだが、何か人生に流れる時間がくっきりとするひとときである。
これまでも朝のコーヒーは欠かせなかったのだが、このコロナの日々の3年間で私のこれまでずっと不安定に揺らいでいた人生の一角に、これだけが確かな時間として定着したような気がする。他にすることもなかったからかもしれない。
しがないフリーランスであるので、通勤はしなくてよろしい。たまさかの講演や会議もオンラインなので出かけなくてもよろしい。ということはもう生き急がなくてもいい人生だと考えてもよろしい。自分で自分にそう言い聞かせて、だから、朝のコーヒータイムがないと1日が起動しないようになったのだ。
豆をミルに淹れる。毎日やっている作業なのに、必ず何粒かの豆を足したり引いたりする。豆の量は果たしてこれでよかったか。私の奥さんはこれでよかったか。ふーむ、人生にはいつも不確定という不安がつきものだ。
稀代のコーヒー党の文豪バルザックは、毎日、豆粒を数えて淹れていたという。私はバルザックだ。
手動の旧式のコーヒーミルをゴリゴリまわす。
うーむ、香り立つコーヒー豆、至福のひととき、なんてことはなく、ただゴリゴリするだけだ。人生に過剰な意味づけはしない方がいい。
この時は何も考えないとかいう人も多いのだが、禅の修行ではあるまいし、あれこれ考える。多くは仕事の手順のあれこれがなのだが、ゴリゴリの単純作業とカフェインの予感で、ドーパミンドパドパとなって妄想に近いあれこれを考える。
その時は全世界の不条理を解明するものすごく鋭く天才的な考察が浮かんだりするのだが、飲み終わると消えている。すっきりとした後味のキリマンジャロのせいなのだろう。
淹れ立てのコーヒーを大きめのマグカップに入れてソファに座り、テレビをつけるとBSで「新日本風土記」をやっている。再放送らしい。私は決して熱心な視聴者ではなく、みたりみなかったり、途中から観たりと制作者には申し訳ないのだが、それでもこの「新日本風土記」には観る度に引き込まれる。
日本各地の「風土記」なのだが、描かれるのはただ美しい風景だけではなく、むしろそこに暮らす人々の姿と想いが前面に浮き上がる。
ひとかどの人物というより、無名の庶民といった人々が登場する。
風土の中の暮らしの過去と現在を重ね合わせ、これまでの尋常ではない苦労もそこの人々は土を耕しながら笑みを湛えて語るのだ。古老たちはあたりを眺めながら、失われた故郷と風景を語り、それでも今の幸せを確かめるようにしてつぶやく。必ずのようにして子供達の屈託のない姿が描かれ、その子らをかけがえのない希望のようにして大人たちが見つめている。そのような物語が展開する。なにげない風景のはずなのに、私はいつも観ていて胸迫り、込み上げてくるものがある。
声の旅人とされる語りは女優の松たか子さんなのだが、ナレーション担当は井上二郎アナと中條誠子アナで、この二人は私の見るところ、もっとも良質なナレーターで、この二人の声の人格で公共放送の基盤を支えているようなものだ。
井上二郎は落ち着いた声音で、情感を込めてはいてもあくまでも抑制し、語り始めにコンマ何秒かのタメを置くようにして、常に映像の細やかな粒子の中に物語を語り始める。映像の人々の想いが彼の語りかけるようなナレーションとともに立ち上がる。
中條誠子は言うまでもなく当代きってのナレーターである。透明な声の揺らぎが映像の人々にそっと、しっかりと寄り添う。
コーヒーの香りという日常性の中で、新日本風土記を観れば、そこにあるのは私たちの風土の豊かさであり力であり、同時に現代の私たちの暮らしというものの危うさと失いつつあるもののかけがえのなさである。
「新日本風土記」のコンセプトは「風の中に、土のにおいに、もういちど日本を見つける。私を見つける」というものだが、改めて思うのは、ついこの間までこうした風土に抱かれて人々の暮らしは育まれていたのだ。
今、この社会はこの国の風土を「地域」と捉え直し、地域包括ケアシステムと地域共生社会の概念を打ち出している。ここには風土の風のそよぎも土のにおいも希薄である。
しかし、この「地域」の中に私たちは「もういちど、私を見つける」しかない。
言い換えれば、私たちは地域に「風土」の豊かさと力を取り戻そうとしているのである。
「地域」とは、生活者のいる風景である。
生活者、あるいは住民と言ってもいいのだが、実はとらえどころがない。あいまいでしたたかで、そうした人々の集合体が地域だ。
とかく「地域」という行政的な括り方をするが、その正体は住民であり生活者で、その多様な個々と共生しつつ、どう新たな地域を創造するのか、そこに機能するのが地域福祉という言葉だ。
かつて、「地域福祉」という言葉のかけらもなかった時代から、私たちの先人たちは地域福祉の力で暮らしていた。それが「風土」というものだろう。
風土に暮らす人々は「つながろう」と言うまでもなく、そのはるか前から、ともに同じ「風の中」にいて、同じ「土のにおい」に生きてきた。誰もが懸命に暮らすことで風土が形作られ、その風土が暮らしを生み出していた。
自然との大きな循環の中に暮らしが組み込まれていたのが、私たちの風土という福祉の力なのだ。
「新日本風土記」は、別の見方をすれば、地域の持つ福祉力のありかを教えてくれる。
ここで描かれる風土の物語をノスタルジーに追いやるのではなく、今を生きる私たちの自然と人々との暮らしの力として拓きたい。私はそう思う。
「風の中、土のにおいに、もういちど私を見つける」
新日本風土記は、現在では貴重な程にテンポが緩やかで、息遣いのようにして起伏おだやかなシーンが続いていく。観る側をせかさない。この自然のリズムが風土を作るのだ。このテンポを暮らしに取り戻したい。
だから、いつも奄美の島唄の香りに満ちた「あはがり(島言葉ですべてがあかるい、という意味)」のどこまでも伸びやかな唄がたなびくようにして、番組を閉じていく。
この、風土色濃い唄声に、今日といういちにち、暮らしへの底深い勇気をもらうような気がするのも、毎回のことだ。
番組が終わるとカップ片手に、ヨシっと勢いよく立ち上がる。
明日はやっぱ、ブルマンだな。