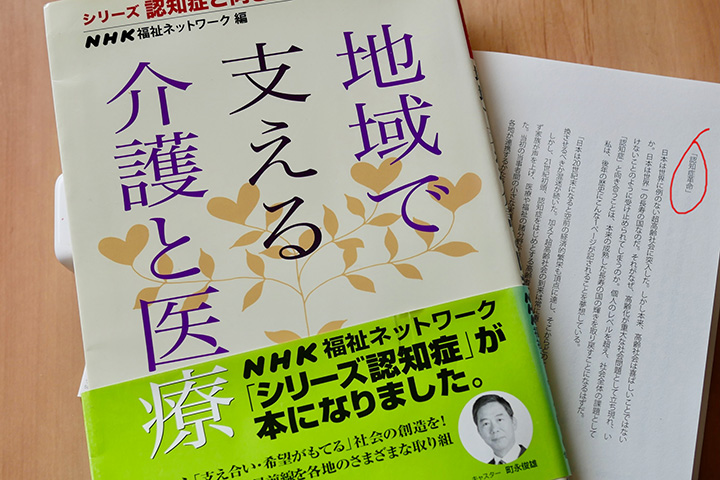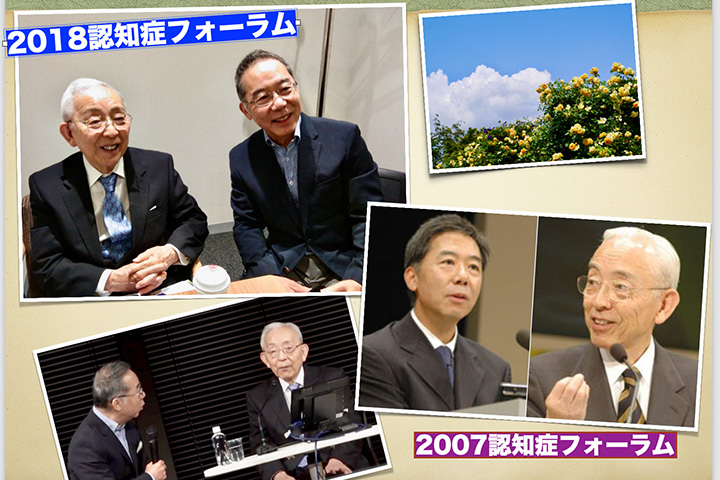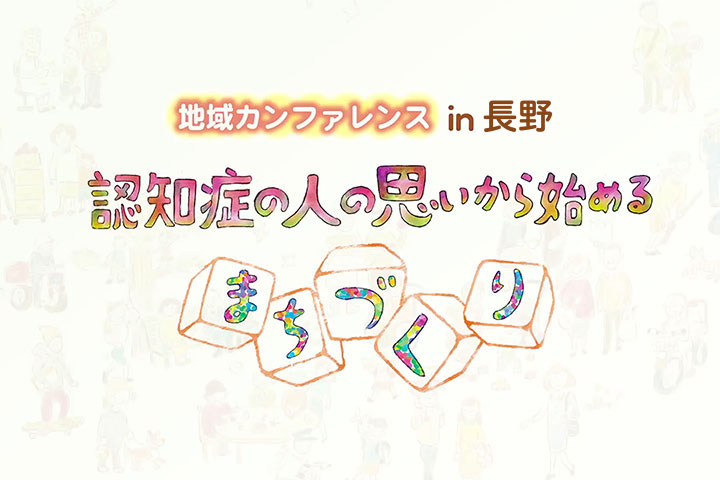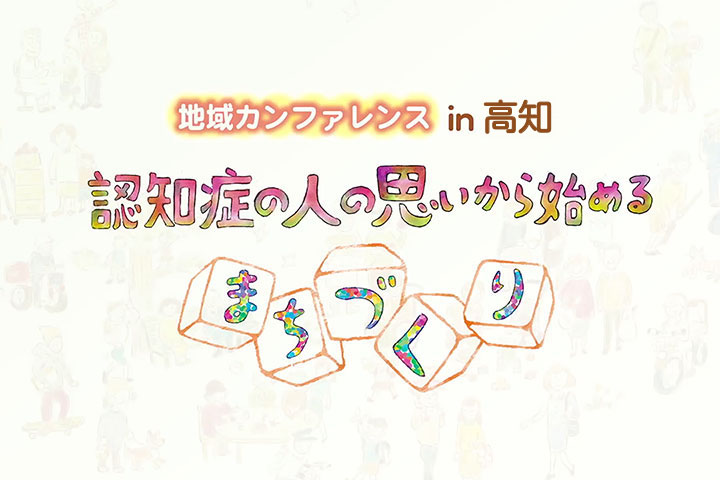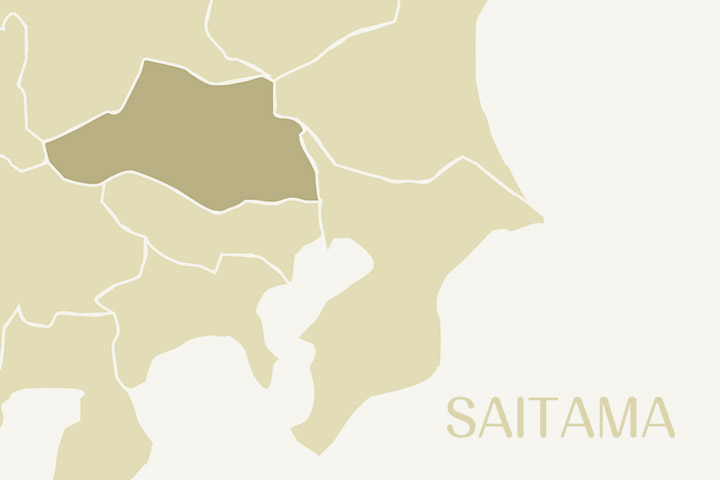▲NHKの厚生文化事業団の「認知症とともに生きるまち大賞」と並行して、各地で「地域ミーティング」を開いている。誰もが参加して誰もと語り合う。なんのためにやるのかではない。ただ、終わって誰もが晴れ晴れと家路につく。(写真・去年の秋田での開催風景)
「胎動」という言葉がある。
「あら、あなた今、動いたわ」
「えっ、どれどれ、ふーむ、あっ、動いた」
「ね、きっとあなたの声が聞こえたんだわ」
妊娠した妻と夫の会話。ドラマなどでおぼつかない夫婦の祝福される未来として必ず描かれるシーンである。胎動は、まだ見たことも抱いたこともない新しい命からのメッセージで、それを受け止める母親は、そこから抽象の命を、我が子というひとりの「人間」として関係性を育んでいくことになる。
「胎動」は時代性の中でも使われる。
いつもと変わらない日常の風景に、どこか予感のようにして時代の変化が押し寄せている。
ほんの小さな変化や気づきといったものがどこかで大きな変革へとつながっていく。
「時代の胎動」である。
しかし、認知症に限って言えば、かつて社会から、地域から、見えない存在とされた「呆け」の人々は、ただ凍りつく日々を強いられてきた。時代は無残な日々を強いていたのである。
1950年代の京都で、みずからを「わらじ医者」として地域医療に生涯取り組んだ医師、早川一光は、そのまだ見ぬ時代の到来をいち早く「風」と捉えた。「呆け」という「風」と。
京都西陣の路地を往診していて、ある日、三カ所も鍵のかかった家をそこのお嫁さんに開けてもらうと、そこに垂れ流しのおばあさんがひっそりと座っていた。「呆け」の人であった。
その時、早川医師は「風」を感じたと言う。それは大地震が起きて、そのあと大津波が襲ってくることに土地の古老が「津波が来るぞー」と叫ぶような「風」を感じたと早川一光は語っている。
住民の暮らしが主体であると西陣の路地から路地へと往診し、「わらじ医者」と呼ばれていた早川医師の直感が、津波のような認知症の到来を、いちはやく時代の「風圧」として捉えた。
認知症のおばあさんを隠して隠して、隠し通してきた家族と本人の苦しみに、早川さんは、なんとか隠さんでもいいようにしよう。そのためには、一緒に苦しみ一緒に悲しむ組織、家族の会が必要だと思ったとも語っている。以前私は、家族の会の初代代表の高見国生自身から、早川一光にこう言われたと聞いたことがある。
「医療ではもうどうにもならん。なんとか自分たちでやれ」
医療も福祉も力にはなれない。切ない思いと涙と不安の中から「認知症」は世に押し出された。
風向きが変わったのは、2012年に厚労省のプロジェクトチームがまとめたひとつの報告書からだった。そこには、こう記されている。
「かつて、私たちは認知症を何も分からなくなる病気と考え、徘徊や大声を出すなどの症状だけに目を向け、認知症の人の訴えを理解しようとするどころか、多くの場合、認知症の人を疎んじたり拘束するなど、不当な扱いをしてきた」(2012 厚労省・今後の認知症施策の方向性について)
そこから時代は加速する。
その後に続く10年有余を端折ってたどれば、2015年に認知症施策の大転換とされた認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)が出され、論議を呼んだ認知症施策推進大綱を経て、そして去年6月「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立。24年1月施行。成立から一年が経った。
大きな変化の時代の到来と見る向きも多い一方で、認知症基本法の成立をもって一区切りついた印象を持つ人々も多い。
「推進する」とする主体とされた生活者たちにとっては、認知症はあくまで政策課題にとどまり、冷めた目で見れば近年のこの変化の連続は、「認知症問題」に対応するため、施策政策、制度ばかりが積み上がってゆくようにも映る。
せっかくの時代の変化と制度の充実が、そのように他人事に映ってしまうのはなぜだろう。
最近報道されたNHKのニュースによれば、認知症の高齢者は、来年2025年には471万6000人となり、団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年には584万2000人にのぼると推計され、2040年には高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症と推計されるとしている。
報道ではその課題解決として、地域包括支援センターの相談事業や認知症サポーター養成などに触れている。
ニュースが伝える現実は全くその通りなのだろうが、ここにあるのはあいかわらずの伝え方だ。
認知症の人の増加が支援と制度の限界を招くだろうという恫喝としての認知症観なのである。
それを同じメディアが、「認知症とともに生きる」といい、あるいは認知症基本法を「共生社会の実現を推進する」と持ち上げる語り口と、どう折り合いをつけているのだろう。どこか分裂していないか。
私たちは、認知症の人が増えるという恫喝でしか、社会を変えられないのだろうか。そのことは、認知症にならないことをヨシとし、認知症になることを問題とするこれまでの認知症観を変更できないままにしている。その背景には、エイジズムがどっしりとうずくまっている。
「認知症とともに生きる」とは、認知症当事者の発信を受けてのこの社会の決意表明だったはずだ。「認知症」を排除するのではなく受け容れる。それが今、単なる修飾語、枕詞に押し込まれてしまっている。
認知症の当事者の視点から、この社会を、私たち自身を捉え直す。
1年前「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立した。そこには全ての認知症の人を「基本的人権を享有する個人」として記されている。
かつて、いくつもの鍵のかかる部屋に垂れ流しのままひっそりと過ごしていた老婆。ガランとした施設の部屋のベッドに縛られていた老人たち。老いの過程で地域と人間を奪われてしまった認知症の人たち。時空冥界を超えて、もしもその人々が認知症基本法成立に立ち会っていたなら、心中、ふるえるような思いであったろう。よくぞ、ここまできた。よくぞ、想いを受け継いでくれた。ようやく、「私」を取り戻せた。
認知症を考えるとき、認知症基本法を語り合うとき、そうした人々の無念を忘れるわけにはいかない。私たちはそうした人々を見なかったのである。そのような社会を私たちが形成していたのである。
時代の胎動とは、まだ見えてこない新しい社会が発するかすかなメッセージだ。
今、潮目が変わるようにして社会の側に、地域に、澎湃として湧き起きていることがある。全国の地域の一画のあちこちで小さな声を交わし、対話を重ねるようにして動き出している手づくりの実践の数々。
それらの実践には決まりきった規格も統一もなく、自然発生的でありながら自律的で、あえて言えば参画する人々の間に、ケアの互酬性といったものが行き来している。誰もが誰かのためであり、誰もが自分のためでもあって、そこに共通するのは、とりわけ「認知症」だけを切り出すのではなく、認知症との共生を、流れる空気のように陽射しのように暮らしの中に全体化している。
「認知症」を語ることなく、しかしそれが最も雄弁な認知症との共生の実践になっている。これが新たに生まれ出ずる時代の胎動なのかもしれない。
認知症の当事者の地域でのピアサポート、本人ミーティング、それに呼応するような地域の人々のまちづくり、カフェ、居場所、図書館、公民館、子ども食堂などなど、時代の胎動が聴こえる。
時代の胎動はそこかしこに感じ取れるはずだ。感じ取れないとしたら、それは私たちが聴こうとしていないからだ。誰かの言葉だけに右往左往し、自分の言葉で自分の思いを語り合うことを手放したからだ。
「あ、動いている」
「私たち、親になるのね」
祝福される未来としての共生社会は、胎動を感じ取る私たちの感性にかかっている。小さな声と動きに手を触れるように、社会に手を差し伸べて時代の胎動に触れてみる。
(文中敬称略)
|第283回 2024.6.11|