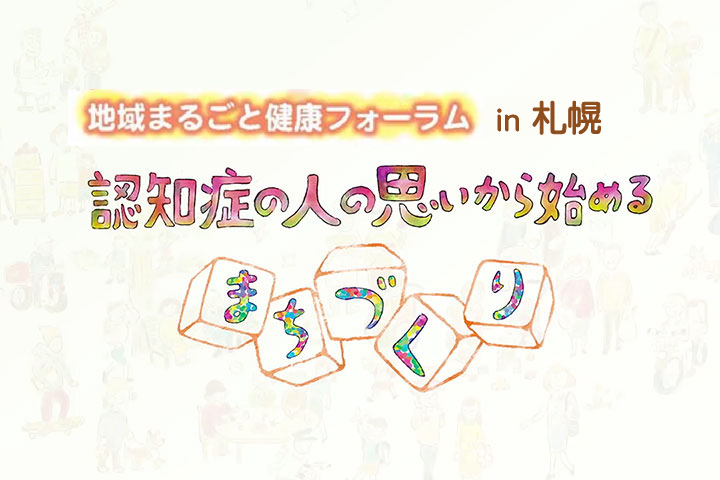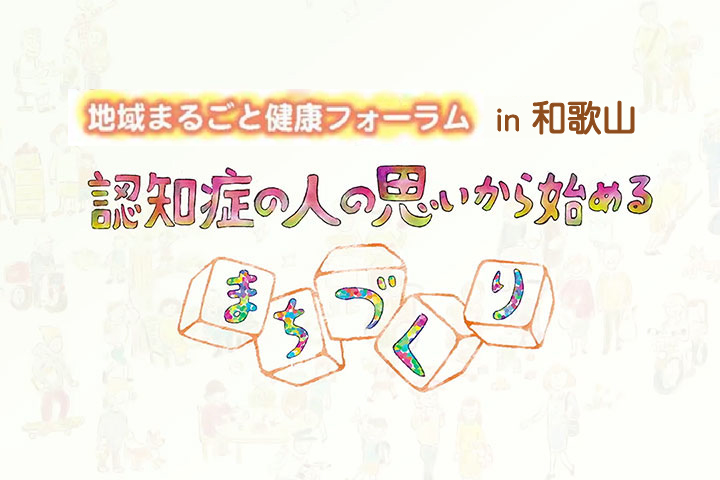▲ 名古屋でのフォーラム。ともすればお題目になりがちな「認知症にやさしい社会」も、地域では全く違った切実さを帯びる。名古屋では、認知症の人と地域の人があたりまえにつながっているように見えるが、そこには緻密な取り組みを創り上げた一群の人々がいる。それを誰もが「仲間です」と言い合っている。
「認知症にやさしい社会」とか「認知症になっても安心の地域」とか言われて久しい。超高齢社会に伴って認知症の人が飛躍的に増大する中で打ち出されたこうした言葉を、正直、多くの人はどう受け止めているのだろうか。
「公的責任の放棄に等しく、生活者への押し付け」という論から、「キレイゴト」「単なるキャッチフレーズ」という受け止めまで、様々だ。
その背後にあるのは認知症と地域の現実の重みである。
そうは言っても、介護家族の厳しさに変わりはないし、認知症にやさしい社会の実感も持てない。「認知症にやさしい社会」なぞ、そんな現実も知らないメディアの勝手な言い草、空論、油紙の上をつるつると滑り落ちる水滴のようなものだ。そんな声が根深く途切れることなくささやかれていないだろうか。
7月28日、名古屋で認知症のフォーラム「超高齢社会を生きる 〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」を開く。
認知症を語るときに、認知症をめぐる現実から目を離すことは出来ない。いや、むしろ、現実を見据えることで、より「認知症の力」を引き出すことができるはずだ。フォーラムでは、そうした現実そのものを語り、その現実に切り込むようにして語り合った。
| 認知症をとりまく現実
どんな現実か。
まずは登壇した二人の認知症当事者が語る「現実」がある。
認知症と診断され、様々なつながりが途切れる。病気のつらさもさることながら、自分らしい暮らしが失われ、孤立へと追いやられる。多くの場合、引きこもり、うつ状態に陥る。今なお、認知症となったほとんどの人が直面する「現実」だ。
「認知症にやさしい社会」はどこにあるのか。
名古屋のフォーラムでは、11年前の愛知県大府市での、認知症の人の鉄道事故裁判を取り上げた。フォーラムで、司法案件を取り上げることは異例だ。ことの性質上、慎重な扱いが必要だからである。
しかし、この裁判は司法判断を超えて、この社会が、果たして「認知症」に向き合っているのかが問われたところがある。一審では家族に監督責任があるとして、鉄道会社から720万円の賠償を求められた。
8年間にわたって闘った家族の高井隆一さんは、一貫して「閉じ込めなければ 罪ですか?」と問いかけ、高井さんの言葉によれば「認知症の『に』の字も理解していない法曹関係者」との裁判を続けた。
結局、最高裁では家族に責任はなし、と逆転勝訴になったが、この社会システム総体の「認知症」に対する不理解の現実の大きさを知らせることになった。
高井さんは、現在は地域で認知症啓発の活動を続けている。
| 介護家族の現実
そして、今なお大きな現実としてのしかかるのは、介護家族の課題だ。
フォーラムでは、介護家族の現実が映像で紹介された。さめた目で見れば、そこに映し出されたのは典型的な「家族で抱え込んでしまう介護」の現実である。認知症になった夫になんとかしてあげたい、なんとかなってほしいという思いばかりが先行する妻もまたひたすら消耗し体調を損ない、ついには救急車で搬送されることが度々だった。
認知症の本人発信が盛んになる中で、家族の丸抱えの支援、お世話は、本人から自立を奪い、「出来ない人にされてしまう」と言われた。確かにそれは「支援」のあり方を問い直し、本来の支援の模索へと、認知症ケアのあり方を変革した。その一方で、地域の片隅で懸命に365日24時間、身近な認知症の人の介護に当たる家族に、「なんとかしてあげたい」のどこがいけないのかと、自身の誠心をなじられたような鬱屈を植え込んでしまってはいなかったろうか。
実は家族の濃密な空間では、言えないことがある。
介護家族の思いの切なさやつらさは、本人には言うわけにはいかない。大切な本人を傷つけたくはない。私が守らなければならない、家族にはその思いだけが充満する。
一方で、その隣にたたずむ本人は、家族の世話なしには暮らしていけない、迷惑をかけている、申し訳ないという自分の気持ちに自身を幽閉させてしまう。一番身近なお互いが、切ない思いやりと気遣いの中で、寄り添う手立てなく交わす言葉も見つからず、遠くに隔たって暮らしているようだ。
ここに「認知症とともに生きる社会」は成立するのか。
| 現実と向き合う
フォーラムでは二人のケア関係者が登壇した。
一人は名古屋市認知症相談支援センターの鬼頭史樹さん。もう一人が認知症対応型通所介護(デイサービス)「とんとOHANA」の伊藤篤史さんだ。お二人とも若い世代に属するが、そんな気負いなく自然体の振る舞い、共通して醸し出しているのは、「別にそんなに大層なことをしているわけではない」ということだ。そうなのだ。「大層なことをしていない」という言明に、実は「大層なこと」がぎっしりと込められている。
介護に追い詰められ、共倒れ寸前だった認知症の本人と妻が、それぞれの自分を取り戻したのは、鬼頭さんが関わる名古屋市の認知症の本人と家族の交流会「あゆみの会」だった。ここでは、本人と家族それぞれが、当事者と交流する。普段の何気ないおしゃべりの力が本人と家族の互いをやさしく回復させる。
鬼頭さんは、「支えるのではない。つなげることをやっているだけ」という。その「大層な」役割は、本人や家族の見せる笑顔が物語る。
デイサービスを担う伊藤篤史さんは、「認知症の人から学ぶことは多い」という。
作業療法士の伊藤さんは若い頃、「認知症を治して見せる」と豪語していたという。今は、認知症の人と接することで、自分の専門のリハビリテーションにも新たな視点を学びとったと言う。
リハビリといえば、機能回復といった具合に機能を「治す」「回復する」ことが目的化しやすい。これを「登り坂」を歩むリハビリとするなら、認知症の人から学んだのは、いわば「下り坂」を歩むリハビリとでも言うものだ。
認知症の切ない現実には「進行」がある。その「進行」自体をネガティブなものではなく、その人らしい人生の「下り坂」に寄り添うリハビリがあると伊藤さんは言う。
「登る」より「くだる」ことにはつらさやリスクもある。と同時にくだる中で見える風景もまた美しいはずだ。認知症の人と共にその風景を共に楽しみたい、と。
考えるまでもなく、超高齢社会とは、誰もの人生も経済も国のかたちも、「下り坂」を歩むことになる。その時の普遍の力を、彼らケアにあたる二人は、認知症の人から学んでいるのだろう。
認知症をとりまく幾つもの現実にどう向き合うのか。もちろん、地域によって抱える現実は様々に姿を変える。
「現実」に対応するのに奇策はない。正答もない。時間がかかる。しかし、目の前の人々と向き合う「現在」はより良く改変可能な「現実」でもある。現実に押しつぶされるのは、今を見ないで、未来に怯えるからだ。
「社会」という仮想単位で捉えようとすれば、現実はただ重苦しくのしかかるが、暮らしの空間単位の「地域」で見つめれば、現実の輪郭はくっきりとなじみやすい自分ごとである。
認知症に学ぶ。そして地域に学ぶ。
名古屋でのフォーラム、あたりまえが特別だ。

▲ その「仲間」の皆さん。名古屋の取り組みを特別視するのではなく、あたりまえの認知症の人と地域の力が特別なのだ。左から、デイサービスとんとOHANAの伊藤篤史さん。認知症当事者の山田真由美さん。後方に、認知症介護研究・研修大府センターの小長谷陽子さん。当事者、稲垣豊さん、妻の一子さん。認知症の父の鉄道事故裁判を闘った高井隆一さん。名古屋市認知症相談支援センターの鬼頭史樹さん。
※このフォーラムの模様は、後日当サイト『認知症フォーラムドットコム』にてご紹介いたします。
|第76回 2018.8.3|