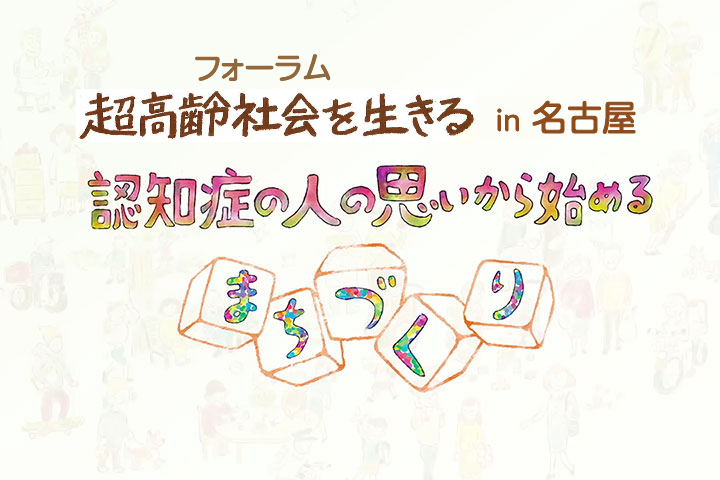▲ 参加者は、医師、介護福祉士、社会福祉士、薬剤師などなどとまさに多職種。地域の「くらし」を支えるのは「総論」と「各論」の全てのまなざしが繋がって見守ることだ。下段は、医療法人大井戸診療所院長の大澤誠氏と。地域医療、在宅医療の実践者であり、チームリーダーでもある。
認知症に対しては、「総論」と「各論」がある。
例えば総論としては「認知症にやさしい社会」であったり、施策的に言えば「地域包括ケア」や「地域共生社会」といったことだろう。一方で、認知症の「各論」というものがある。地域の認知症をめぐる「現実」と言ってもいい。
「認知症にやさしい社会」や「認知症になっても安心の地域」が言われる、その一画で年老いた認知症の夫と暮らす妻は、自身も抱える慢性疾患をなだめながら、すっかり言葉も表情も乏しい夫に語りかけ、食事の世話をしながら深くため息をつく。
認知症の「総論」と「各論」の間の懸隔は大きい。
総論としての「地域包括」は、各論の視点からすれば、公の責任の放棄であり、地域の生活者の側への押し付けとなり、「認知症にやさしい社会」は、進行した認知症の人と暮らす介護家族にとっては、どこのお花畑のお話かということにもなる。
「認知症にやさしい社会なんて・・・」と天を仰ぎ、今ここにいる認知症の人との向き合いに希望のひとかけらでもあるものだろうかというつぶやきと、「認知症にやさしい社会総論」とが、遠く隔たって別個に語られていないだろうか。
現場という「各論」に向き合い、そこでの生身の認知症の人々とそのつらさや困難を分かち合い、額の汗をぬぐい、涙を振り払い、崖っぷちギリギリの地点で踏みとどまるようにして支え寄り添っている家族や専門職に、「総論」は届いているか。
しかし、認知症の「各論」は、「総論」を無効化するものではない。
むしろ、「各論」という現場性を取り込みながら「総論」が積み上がり、そしてまた「各論」に流し込むという連動性がなければならないだろう。
「総論」が「各論」からの問い返しや検証を受け止め、「各論」が、「総論」によって現場の取組みの座標軸を確認していくという双方向の交流なくしては、「認知症」の社会は前に進まない。
では、この認知症の「総論」と「各論」をつなぎ、噛み合わせていく機能とはなんだろう。
最近、認知症に対する地域医療の取り組みが活発だ。
先日、群馬県高崎市で医療、介護専門職の研修会に参加してきた。「高齢者支援・多職種協働地域研修会」とされた取り組みだ。今、全国各地で同様の取り組みが展開されている。
主宰者の一人の大澤誠医師は、地域医師会会長であり、医療法人の診療所の院長である。大澤医師は、認知症は現時点では治癒が望めない以上、医療モデル的アプローチには限界があり、認知症の人とその家族のQOLを高める生活モデル的アプローチが重要になるとして長年、認知症の人の在宅医療に取り組んできた。
高崎での「多職種協働地域研修会」では、だから、この「総論」と「各論」とが並列して行われた。「総論」としては、大澤医師が教育講演として高齢者の「尊厳ある生を支えるために」、私が「認知症が拓く新時代」と題して講演した。
私の講演は、「認知症」を社会問題化するのではなく所与の前提としてみるなら、その課題こそが社会活力となり、「認知症」の発信と取り組みが地域へと進化拡大する中で社会システムを共生社会へと拓いていくという内容だ。
続くプログラムが専門職の人々との「事例検討 認知症の人とともに作る地域社会をみんなで考えよう」というまさに「各論」なのである。
ワークショップである。まず事例として、地域の認知症の人の基本情報が細かく具体的に提示される。
「自転車で出かけては帰れなくなる。転倒してけがをすることが多い。家の中はゴミ屋敷状態。排泄に失敗し、尿臭がひどい。カビの生えた食品を食べている。薬もちゃんと飲んではない。市職員が介入しようとしても、呆けてなんかいないと追い返す」などなど、とてもここでは紹介しきれない項目が並ぶ。
これをもとにグループ分けしたメンバーがそれぞれ課題や手立てを書き出し、それを模造紙に貼り出してグループワーク、話し合うのである。
オブザーバーとして参加した私は、正直、ほんのちょっと心配した。この事例検討会が、地域の認知症の人の事例をいわゆる「問題行動」視し、地域のトラブルメーカーにどう対処するかの検討会だったらどうしたものか。「ボーッと生きてんじゃねえよ」と叫べば、あの番組みたいに調和的な合意点が見えるわけでもなさそうだし・・・
ということは全て杞憂だった。当たり前だ。
それぞれのグループの報告に移った。あるグループは「本人の視点で見る」と前置きしてそれぞれの事例の背後にある環境因子を検討したというのである。なぜそうした行動をしてしまうのか、そうせざるを得ない本人の孤立や不安を探る語り合いをしたと報告する。
またあるグループには、私はたまたま巡回するようにしてその場にいたのだが、事例の中に巧妙にひっそりと別々のところに記されている本人の「一代で事業を起こし、かつては地域の名士と目されていた。社交的で、外出好き」といった項目に、一人のメンバーが、「どこかに仲間が大勢いるはずだよなあ」と指摘し、もう一人が「ここにもともとオシャレと書いていある」と指差し、あちこちの事例の陰の記載から、「地域で活発な活動をし、多彩な人脈を持つおしゃれで社交的な実業家」という人物像を立ち上げた。
ここに「総論」と「各論」の豊かで実質の交流がある。
「各論」の現場を担う専門職は「総論」の方向を取り込み、「総論」は認知症の人の生き生きとした息遣いを「各論」の現場である地域に見出していく。
「各論」が見出した認知症の人は、他者から見る「困った人」ではなく、本人の視点からは「困っている人」である。
そのとき、困らせているのは誰か。「困った人」とみれば、本人が周りを困らせているが、本人を「困っている人」とすれば、手を差し伸べる責務は医療を含めた地域の側に移る。
ここに「認知症になっても安心して暮らすことができる地域」が、総論としても各論としても、新たな現実の姿として響き合う。
事例研究を振り返り、大澤誠医師は、「着実に進化している」という。それはこうした多職種連携の成果だろう。医師、看護師、歯科医師、薬剤師、社会福祉士や介護福祉士、作業療法士などなど、広範な職種の複眼が、語り合い、取り組みを重ね、そして地域に張り巡らされていく。
研修を終えてホールを出れば、春まだ浅いこの土地に、名物赤城おろしが吹きつける。
同じ風土に暮らすこの土地では、医師であろうが専門職であろうが、誰もが共に同じ地域の生活者である。顔なじみの風景と人間関係は、「総論」も「各論」もわけ隔てなく、自分たちのやるべきことでしかない。
夕映えに染まる赤城山から、上州空っ風は、この時、時代の新風のように吹き渡った。

▲ 群馬県高崎市で行われた「高齢者支援・多職種協働地域研修会」での事例検討会での様子。誰もの言葉に現実の裏書きがあり上滑りしない。下は、グループごとの報告の様子。報告での言葉もしっかりしていることは、取り組みの成果を示している。
|第98回 2019.3.27|