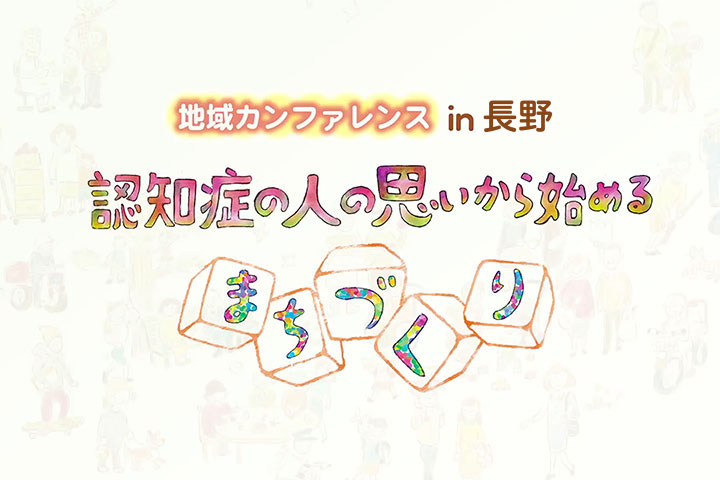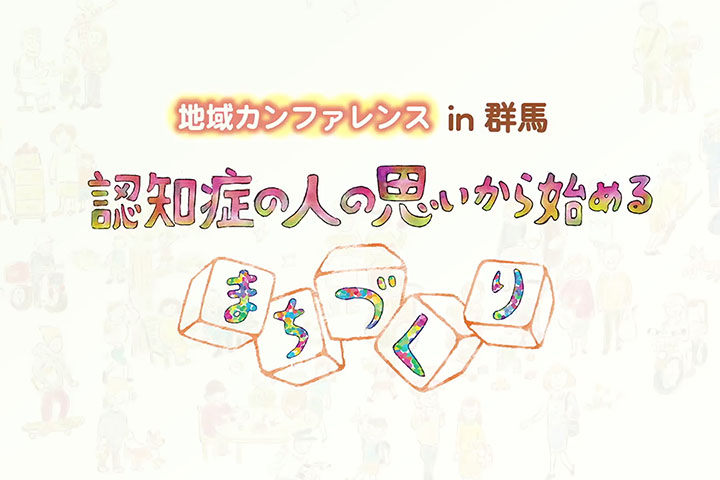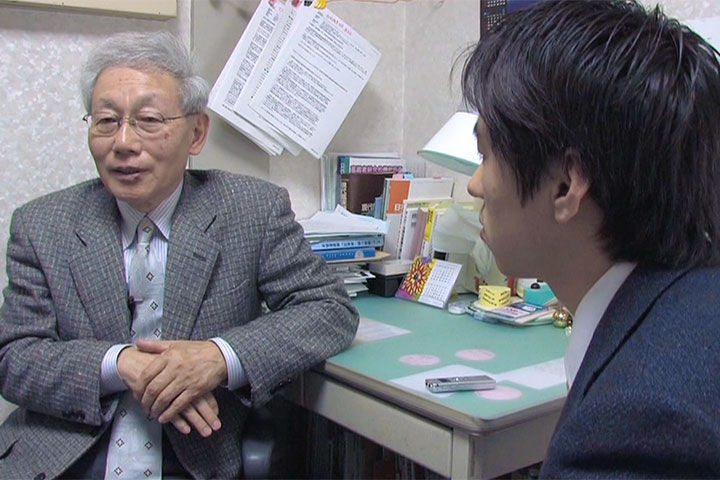▲ 佐久病院といえば、誰もが独特の想いを寄せる「聖地」である。先端医療と地域医療の双方を担い、それは、理念は現実を改善できるという戦後一貫した信念の成果である。恒例の農村医学夏季大学は全国からの人々で熱気に包まれる。そこでの講演は、時代を撃ち「人間」を語るとされているからだ。
7月19日に、長野県の佐久総合病院での農村医学夏季大学講座で講演をしてきた。
講演全体の最終部、「共生社会と対話」を語った部分を補筆修正した上で、コラムとして記したものである。
さて、「認知症とともに生きる」とは、端的には共生社会の一類型でしょう。
既存のパラダイムで未来は拓けないと打ち出されたのが「共生社会」です。
しかし、すでにこの言葉に新鮮味はありません。「地域包括ケアシステム」「地域共生社会」といった施策が打ち出された時、こうした受け止めがありました。
「これは公的責任の放棄であり、生活者への押し付けである」という声です。
実は、ここには根深い福祉観が投影されているのだと思います。それは、福祉は誰かのやってくれることで自分は関係ない、という捉え方で、これがあまりに根深いので、慌てて「自分ごと」として考えましょうと呼びかけることになるのですが、その呼びかける人自身が、「他人事」として呼びかけていますから定着するはずはありません。
今や、やってくれる「誰か」はいないことに気づくべきなのです。少子超高齢社会というのはそういう社会です。
そもそも、地域社会というのは原初、共生の社会として誕生したはずです。
互いの「命」を寄り添わせるようにして、厳しい寒さと飢えのおびえに耐えるためには、互いのぬくもりを確認するしかなく、そこから私たちの社会は形づくられてきたのです。
それを経済成長の再配分の恩恵さえあれば、地域などいらないと打ち捨てたのは、実は歴史のごく短期間の成長幻想の中でしかありません。
だから、この成長幻想の本当の負の側面は、私たち自身が私たちの地域社会の主体であるという市民意識を限りなく希薄にしたことにあるのかもしれません。
では、この共生社会を少し丁寧に検討してみましょう。
認知症に関していえば、それは「認知症とともによく生きる」ということになります。
言葉としては美しい理念が先行するような気がします。そのイメージはどこからきているのでしょうか。
厚労省などの地域包括ケアの概念イラストを見れば、認知症の人を中心に置いて、その周りを医療や福祉、地域の人々、施設、行政の人々誰もが笑顔で繋がり囲んでいるのを見ることができます。タイトルをつけるとすれば、「みんな仲良し、共生社会」ということでしょうか。どうもこの無邪気さが誤解の元かもしれません。
だいたい、「ともに生きる」ということであれば、認知症の人だけがイラストの真ん中で対象化されるのではなく、地域の他の人々との繋がりの輪の中に、「ともに」描かれるのが筋合いではありませんか。
「認知症とともによく生きる」と簡単に言いますが、それは例えば「障がい者とともによく生きる」とか「移住外国人とともによく生きる」という共生概念とは、別個の枠組みなのでしょうか。
もちろんそれぞれ、個別の課題性はあるにしろ、「認知症の人だけとよく生きる」ということには、無理があります。共生社会は、この社会の成員誰もの合意と包摂で成り立つからです。
近代人が自我に目覚めたということは、この社会は「分かり得ない他者と共存する」ことが宿命になったといえます。
そうした社会では、実は、共生は厳しい試練でもあったはずです。
「わかりえない他者と共存すること」とは、それは、訳の分からないおっさんが隣人であったり、地域に一切の無関心を決め込む若者がいたり、認知症になりたくない人がいて、もちろん認知症の人もいるというのが当たり前のことなのですが、「共生」と言うときに、なぜかこういう、共生にとって「都合の悪いこと」は視野から外してしまいます。
マンモスを追って、氷雪の原野をさまよう太古の人類にとって「共生」は生き抜く武器でした。しかし、近代の人々にとっては、「共生」は厳しい試練でもあったに違いありません。それは常に個人の孤独であるとか、社会に満ちている苦痛や憎しみ、怒りとも向き合い、つきあわざるを得なかったからです。そこから立ち上げる「共生」でなければ、未来は拓けるはずはない、私はそう思っています。
さて、それでは「共生社会」をどう創ればいいのでしょうか。
最近私は、「対話」と言うことをよく考えます。
対話のルーツは文明と同じくらいに古くからあり、例えば、ネイティブ・アメリカンの人々が焚き火を囲んで、部族の物語を語り、狩の体験を分かち合い、自分たちで自分たちの文化や社会を構成し継承していったと言われますし、それはまた、この国での、囲炉裏を囲んで老人の民話が語られ、男親がその年の作柄を語り、母親が子供たちに笑みとともに味噌をつけた餅を焼くといった具合にそれぞれの繋がりが、なんの目的化されることなく、雪が降り積もるように、それぞれの心に沁みていく。そんな「対話」が、地域を作り、文化に繋がっていったのだと、私は思います。
思い浮かべるたびに、私たちが、経済に置き換えるようにして打ち捨ててきた豊かさと、その力を思います。
物理学者にして思想家、デヴィッド・ボームの提唱した「ボームのダイアログ」といわれる古典的対話論があります。
ボーム自身が、すぐれた物理学者としてマンハッタン計画にも関わったことで、その後、この人類世界に深い懸念を抱くに至ったことから「ダイアログ」を構築していったことを考え合わせると、彼の「対話」に寄せる重い質量を思うしかありません。
ダイアログ、対話とは、議論でもディベートでもなく、ここでのダイアログは、人々の間の「意味の流れ」であり、議論に勝つことでも自己主張の場でもないとされます。
ボームのダイアログの概念自体は、難解なところが多いのですが、私たちの通常の議論というのは、議論の「内容」を目的化して、自己主張の正当性を巡ってその是と非、勝ち負けを判断します。が、対話とは、そうでなくあくまでも、議論の「過程」という流れによって互いに共通する新しい視点、「新たな場所」をともに探すこととしています。
対話によって、お互いが一緒に「新たな場所」を生み出す、というのが、ボームの「対話」の核心といっていいでしょう。
ではそのようにして生み出された「新たな場所」とはなにか。私は、それが「共生社会」ということに繋がると思っています。
ところで、私が、なぜ「対話」に関心を持つに至ったのかは、実は仙台の「宮城の認知症をともに考える会」に参加して、認知症当事者たちのピアサポートに接したとき、これこそが「対話」の力なのだと直感したところがあるからです。
認知症の人たちのピアサポートについては、これは実際にあの場に立ち会った人なら、誰もがわかるとおもいますが、そこにあったのは、相互承認と「新たな場所」への発見に満ちた「対話」でした。互いの話は何も否定されることなく受け入れられ、その安心感の中で、当事者同士がそのレジリエンス(回復する自分)を感じ取るのです。
自由に流れるようにそれぞれの体験を語り合う、そのことが当事者発信の力となっているのだ、とあの場でそう確信しました。
今、「認知症とともによく生きる」ということを語るとき、この「対話」が必要でしょう。そして、当事者同士だけでなく、当事者と、まだ認知症ではない人たちとの対話もまた展開されなくてはなりません。
認知症の人の疾病的側面の負荷も考えれば、現実的には、認知症の人とそうでない人との、面と向かっての対話には難しい場合もあるでしょう。もちろん本人との対話もあっていいのですが、より深い意味を共有するためには、まずは聴く側が自身の内面で、自分自身と「対話」するということができないでしょうか。
当事者発信が盛んになるにつれ、そこにいつの間にか、壇上で「語る人」と、会場で「聴く人」の分化が起き、認知症の人の話を「いい話」「感動の話」として、ただ消費するということが起きてはいないとは言えません。
だからこそ、「対話」なのです。あなたがあなた自身と「対話」して、「新たな場所」のあなたを見つけるのが「対話」です。
最後に、谷川俊太郎さんの詩を一つ、ご紹介しましょう。
「ここ」 谷川俊太郎
どっかに行こうと私が言う
どこ行こうかとあなたが言う
ここもいいなと私が言う
ここでもいいねとあなたが言う
言ってるうちに日が暮れて
ここがどこかになっていく
一行ずつ、やわらかに対話がくり返されています。
それぞれが互いに違うことを言いながら、その違いを受け入れながら語り合いが重なって、「どこか」という「新たな場所」を二人で生み出していくのです。
ここにあるのは、「対話」の本質である以上に、「ここがどこかになっていく」という共生社会の創り方のようにも読み取れます。
最初から、あるべき共生社会が用意されているわけではありません。
それぞれが、互いの思いを聴き取り、自分の枠組みを解きほぐし、互いの違いに共通するこの社会の「新たな場所」を一緒に求め生み出していく。そんな対話の力がこの詩には潜んでいるように、私には思えます。
そして同時に、これは、ここ佐久総合病院が戦後70年、一貫して「農民とともに」と、農村の暮らしの中に飛び込むようにして模索と実践を重ねてきた、世界に冠たる農村医療、農村医学の歩みに、そのまま重なります。
どこに向かうか、その方向性を絶えず農民との「対話」を積み重ねて、そして、「ここ」佐久平の地を日本の、世界の、農村医学という「どこか」にしてきました。それは、完成されることなく絶えず「どっかに行こう」と問い続けることで未来を拓こうとしています。私はそのように思うのです。
この社会という「ここ」を、「認知症とともに生きる」という確かな「どこかに」変革していく「対話」をどうかさねるか、そんなことを考えつつ、私の話を終わりたいと思います。
ご静聴、ありがとうございました。