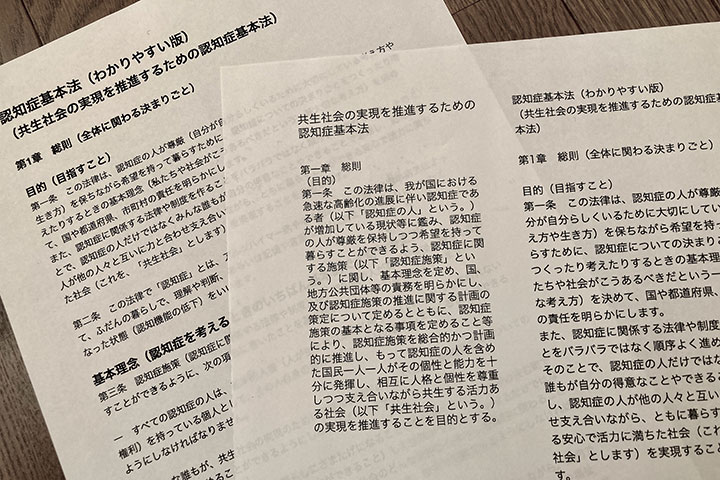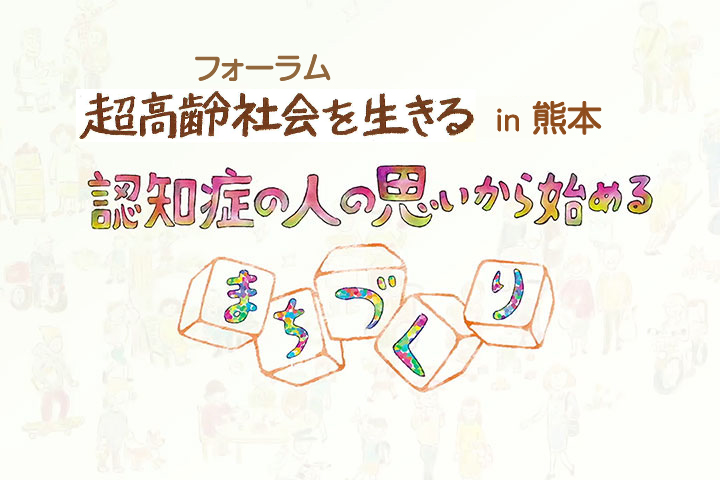▲ 「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され,かつ健全で安らかな生活を保障される 」とは老人福祉法(1963)の基本理念である。その一方で、世界の三大差別はレイシズム(人種差別)、セクシズム(性差別)、そしてエイジズム(老人差別)だとされる。差別の中から認知症は何を問いかけるのか。
「老人」という言葉も悪くない。
そんなふうに思った。普段、福祉的テーマでは「高齢者」という用語を使い、口語的な語りでは「お年寄り」と言うことが多い気がする。
なんとなく放送の現場などでは、「老人」は差別的で、「高齢者」なら問題ないとしてきたところがある。そうだろうか。
それより気になるのはやたら敬語的修辞さえ重ねれば、自分の立ち位置を曖昧にして言いがかりを回避できるとする安直さである。
「ご高齢の方」とかね。もちろん、その物言いに人柄が滲む場合もあって、あくまでもコンテクストにもよるのだが、これを連発する場合は大抵、他者性の鎧をまとっている。敬語ではあっても、そこで語られる「ご高齢の方」とは、突き放して他者に追いやるような表現で、敬ってはいない。
「老人」は違う。すっきりとして余計な装飾がない。老いた人、なのである。「人」なのである。若人、大人、老人、かつて私たちの共同体ではあたりまえに「人」が生まれ、育ち、死んでいく、その「人」の連続を見つめてきたのではないか。いつから、この社会から「人」が欠落してしまったのか。
そう思っていたら、老人という言葉が好きになった。
言葉を好きになるというのは、そこにある「老人」という存在を好きになることだ。
「高齢者」は匿名で顔もその人生も見えてこない。ヘミングウエイの「老人と海」は、「高齢者と海」では成り立たない。
時代劇で、「そこな、ご老人」と呼びかける時、そこには身分を超えた年長への畏敬がにじむようである。カッコいい。
ところが今、コンビニでレジの若者が「そこの老人」と呼びかけたら、多分、相手はムッとする。それはなぜか。
それはそこに「老い」の抜きがたいスティグマがまとわりつくからだ。だから、コンビニで「老人」と呼ばれれば、「オレは老人ではない」とムッとする。
近代は「老人」という人格に、生産性と効率の衰えた人という価値観を貼り付けた。そのレッテルはついでにその老いた「人」の方までおとしめてしまったのである。そのことに気づかなかった。「老人」の言葉の忌避は、実は根深く周到に私たちの「老い」のスティグマを世間から隠蔽することになったのだ。
この国の「看護」「介護」概念を確立し創り上げた中島紀恵子さんと、認知症ケアの勉強会を開いた時、中島さんは二枚のスライドを提示した。
私たちは、老後の生活が極端に過酷な社会をつくってしまった。
老後の悲劇とは、我々の誰もが老いそして死ぬという事実ではなく、老いへの道のりが、無自覚、無知、貧困のために、不必要なまでの堪えがたい苦痛、侮辱、無気力、孤独なものになってしまったという事実である」(ロバート・バトラー:老人差別)
ボーヴォワールは人間存在探求の哲学者であり、バトラーは老年学の父とされ、生涯を通じてエイジズムという言葉で老いへの偏見を告発した精神科医である。
やっかいなのは、この「老い」のスティグマはいつの間にか私たちに刷り込まれてしまったことだ。丸の内を肩で風きって行き交うサラリーマンに、渋谷のスクランブルを賑やかに渡る若者に、公園で子供達を遊ばせながら語り合うママ友にも、「老い」への差別と偏見は根付いている。
バトラーは、老後の悲劇は、誰もが老いそして死ぬという事実ではなく、老いへの道のりが無自覚、無知なのだとし、ボーヴォワールは、それを文明の挫折としている。
この社会の最大の差別と偏見は、だれもの「老い」に潜む。
「老人」の復権はどうすればいいのか。
今年の成人式の時、こんな一文をものにした。
「新成人の皆さんおめでとう。ただし、皆さんの未来は実はそれほど祝福に満ちているわけではない。そもそも若い時というのはつらいことがかなり多い。恋に破れ、仕事に行き詰まり、人間関係に悩み、家族をうとみ、自分に自信が持てなくなることの連続だ。
でも、若さはいつもそこから立ち上がる。悩みや失敗は、いつか人生の糧になる。失敗してもやり直せるのが若さの特権だ。
それは、この人生の終盤にさしかかる老人には眩しいほどに羨ましい。キミたちには失敗できる時間があるのだ。
対して、老人には、もはや、失敗したり悩んだり、やり直しする未来という時間はない。その代わり、老人には、たっぷりとした過去がある。それは、それまでの人生での幾度もの挫折と涙の収蔵庫だ。膝を屈してもそこから何とか立ち上がり、試行錯誤し、学び直しの経験を重ねた過去という時間の圧縮だ。
失敗と悩みの先達、知恵者、それがキミの周りの「老人」という存在だ。
皆さんの未来がどのようなものか、私にはわからない。ただ一つ言えるのは、皆さんは確実に老いていく。老いていく人生、おそらく誰もそんなことは視野にはないに違いない。
しかし、一日一日、あなたは未来という時間を、あなたの過去の時間に繰り込んでいく。
人生とは、未来という毎日をあなたの過去に送り込んでいくことだ。若さと老いは別物ではなく、あなたの未来と過去は連続するスペクトラムなのだ。
あなたの未来と老人の過去の連続が社会をつなぐ。この社会は地域の横のつながりだけではなく、人生という時間軸を縦につないでいる。
あなたが深い挫折にうずくまった時、その時、その横にたたずむ人がきっといる。その気配を感じ取ることができるはずだ。いつの世も老人はそんな存在だった。
繰り返すが、あなたは確実に老いていく。それを衰退の人生とするか、それとも豊かな人生への歩みとするのか。
あなたの未来とは、あなたというひとりの老人を創り上げていく過程でもある。それが成人式を迎えた皆さんの人生の始まりだ」
認知症の人とは、この社会のスティグマを切り分けのりこえ歩む人でもある。
「患者」から「認知症の人」としたのは、単に医学モデルの幽閉からの脱却にとどまらず、むしろ欠落していた「人」としての存在をこの社会に埋め込む先達者として現れたのである。
認知症が、老いのリスクであるとするなら、認知症の人は老いと認知症の二つの偏見を引き受けざるを得ない。認知症の人は、認知症の進行や喪失を見据え、自身に内面化することで、衰退ではなく豊かな人生にする決意を社会に発信してきた。
それは「認知症」を語るだけではなく、この社会の根深い「老い」のスティグマを解き放す力を語ることになった。
一月の認知症の希望大使任命式で、オーストラリアのクリスティーン・ブライデンがビデオメッセージを寄せた。
スクリーンに映し出されたクリスティーンの70年の人生を刻む相貌は、確かに「老い」の刻印ではあっても、それは衰退ではなく豊かさと力強さの何よりの証明だった。
彼女は、そのスピーチの冒頭、こう切り出した。
「希望大使のみなさま、おめでとうございます。
認知症と共に生きる私たちだけでなく、社会全体にとって意義ある大切な任務です。
私たち一人ひとりが家族や地域コミュニティ、そして社会を思いやる気持ちを持ち、日々の選択をすることがより良い社会を作っていくはずです」
クリスティーンは、平易な言葉にまず社会全体を規定し、そこに「日々の選択をせよ」と能動を呼びかけ、より良い社会をつくる覚悟を問いかけた。それは、認知症だけでなくその背後に張り付く「老い」のスティグマを解き放す力と希望を響かせた。私はそう思う。
|第129回 2020.2.6|