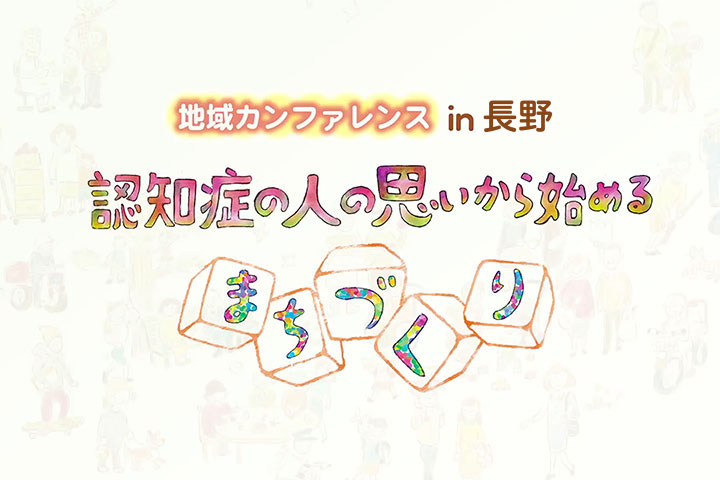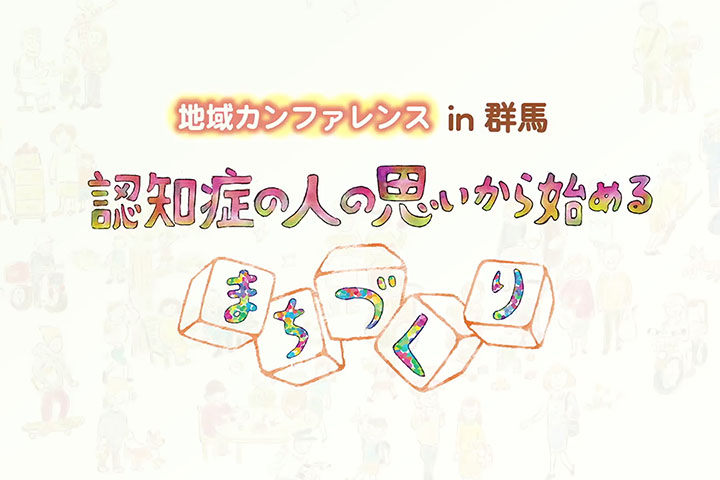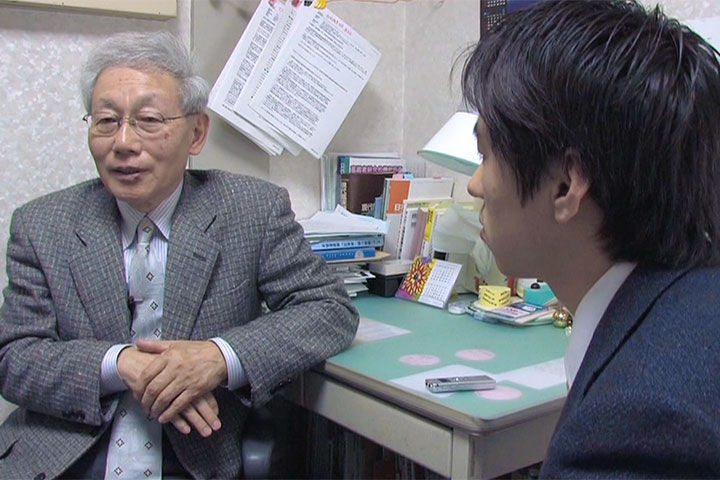▲広場の孤独(堀田善衛にこのタイトルの小説があった)。週末は大道芸が披露され大勢で賑わう広場に、人はいない。これは、新型ウィルスによるこの状況をのりこえた時にこの社会はどうあったらいいのかを考えるために、心に刻み込んでおくべき光景のように思える。
この事態だからしょうがない、引きこもって読書三昧と思ってもどうも身が入らない。というか心が入らない。晴耕雨読というのが最高の充実の時間とされてきたのは、社会と個人の一定の安定が前提だったのだ。
で、気晴らしに散歩に出る。街に人がいない。週末の賑わいがかき消されている。これまで、ごった返す混雑に舌打ちしていた自分は身勝手なまでに宗旨替えして、普段の日常が消えてしまっている不安に佇む。ここにあるのは周囲が切り立つ壁のような孤絶感である。
青春の一時期に求める孤独は自己形成の通過儀礼であっても、いまここに押し寄せる孤立、孤絶は人をさいなむ。
思えば、今日が昨日と変わらず、明日もまた同じような朝がやってくることを前提として私たちは日々を営んできた。
この新型ウィルスの事態がもたらした不安は、感染リスクはもちろんだが圧倒する不安は、私たちの日常が一変させられたことだ。
明日が今日と同じように明けるであろうというこの確信が、実は福祉の基盤である。変わらない日常の暮らしを維持し、保証するのが福祉の命題である。しかし、そのためには福祉が変わらなければならない。変わらないことのために変わる。現代の福祉はその難しさを抱え込んでいる。
LIFE LINEという言葉がある。電気、ガス、水道といった緊急時の社会インフラである。社会の生命維持装置だ。
このLIFEをもう一度見つめ直してみよう。LIFEとはまずもって命である。生命の尊重は揺るがない。しかし、LIFEはそれだけではない。暮らしがある。命は暮らしであり、暮らしは命の維持である。LIFEにはまだある。人生だ。生命を連続させる暮らしがあり、その蓄積が一人ひとりの人生を創っていく。
生命と暮らしと人生。
変えてはならない福祉の命題はここにある。この維持、尊重のためには、福祉は時代の中で柔軟に変わらなければならない。
この超高齢社会を運営していくためには、これまでのような福祉予算を再配分するシステムで需要と供給が均衡するはずがない。
生命と暮らしと人生の変わりない連続と維持のためには、その基盤の社会システムを変えなければならない。それが変わらない日々の暮らしを連続させるために変わらなければならない福祉の宿命である。
そのために打ち出したのが、地域包括ケアであり、共生社会だ。
共生社会は、お題目ではない。この国の新たなLIFE LINEである。
独立の父、インドのマハトマ・ガンジーの「平和への道はない。平和こそが道なのだ」の言葉を借りれば、「共生への道はない。共生こそが道なのだ」ということだろう。この道しかない。
その「共生」という道は、このウィルスによって、ズタズタに途切れてしまったのだろうか。
私はそうは思わない。このところ連続して、各地の地域での活動を担っている団体や、参加している人々に接してきた。確かにこの事態で交流や取り組みは棚上げされている。しかし、そこで人々が改めて感じ取るのは、むしろ「つながり」の役割と意味だ。
おそらく、この雌伏する機会に自分たちの活動の脆弱なところを今一度、洗いなおすようにして点検しているはずだ。
もしも私が感染者となったら何が起こるのか。多分、防護服に身を固めた担当者がドヤドヤとやってきて、どこに行き、誰に会ったのか、交通手段は何か、どのくらいの時間で、どのくらいの距離であったか、そうしたことが徹底的に調べられるのだろう。
そうなったとしたら、私自身は、自分の感染の不安に加えて、友人知人、地域の人に大変な迷惑をかけたこと、不安をもたらしたことを耐え難い苦痛に思うに違いない。
今そうしたことを多くの人が考えているはずだ。感染対策は何より重要であるが、それは感染をあってはならないことにするのではなく、感染した時の私たちの心の備えもまた求められている。
それが「自分ごと」ということだ。共生社会の必須アイテムである「自分ごと」を、今回のウィルスはこの上なくリアルに切実に私たちに問いかけている。「自分ごと」は、他者のつらさを涙とともに、自分の不幸に置き換える心清い人のたしなみなどではない。
「当事者」になるということはどういうことか、このウィルスは、ありありと浮き上がらせている。
「共生」するということは、葛藤を生む。同じ思いの人だけの共生などはあり得ない。それはもたれ合いというものだ。共生するということは、葛藤や対立も生むプロセスだ。
私たちはこの状況で「問い」を立てる。事態に呑み込まれず、事態を受け入れる形に変えていく。それもまた「自分ごと」である。
そのプロセスを経て、私たちは市民的成熟に進むことができる。
このウィルスの試練をのりこえることができた時、この社会は何かしらの変化を見せることができるだろうか。せめて、この事態を奇貨として、私たちは地域共同体を今一度前に進ませることができるだろうか。
もちろん、気がかりなこともある。
報道によれば、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正して緊急事態宣言を出せるようにしたいとのこと。それは人権や私権の制限につながる。しかし、そこに「そんなことを言っている場合ではない。この事態なのだから」という声がかぶさって、まっとうな批判も封じ込めている。
「この事態なのだから」という強権的な発動は、法的根拠のないままの一斉休校にもなった。確かに、この事態に対処するにはスピード感が何よりであろう。しかし、スピード感と頭ごなしのずさんは違う。
この事態がもたらすのは、強権の横行する荒涼とした社会なのか、それとも試練をかいくぐったつながり合う成熟社会なのか、その分岐点での私たちの選択なのだ。
今この事態に、市井の名もない人々は、精一杯、両の手を広げ、その指先にかすかにつながりあっている人々の感触を感じ取るようにしながら、自分たちの暮らしをじっとスタンバイさせている。
その指先にふるえるように確かめ合う子供の息遣い、高齢者の思い、私たちの切ない悔しさを、「この事態なのだから」と言いつのる施政者は感じ取ることができない。
そんな人が「この事態なのだから」という上からの大きな声でねじ伏せようとしているのは、今、やわらかに生まれ始めた、私たちの共同体の誕生の芽だ。
私は、ウィルスの脅威より、「この事態なのだから」として、私たちの小さくかけがえない暮らしの力をなぎ倒す声の方が、よほど怖い。
|第133回 2020.3.11|