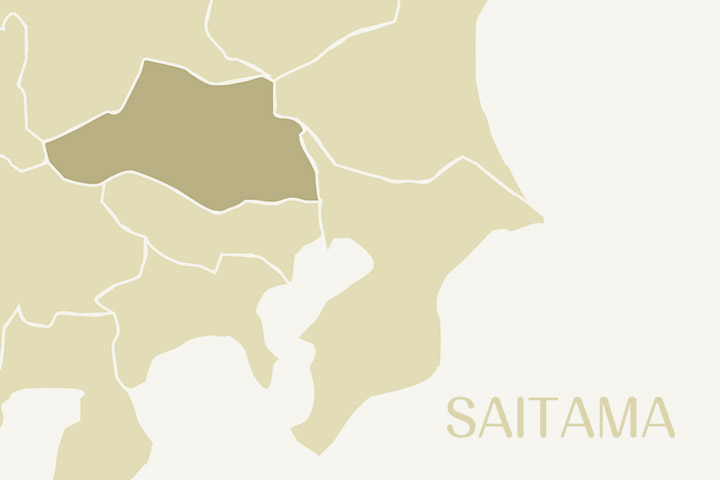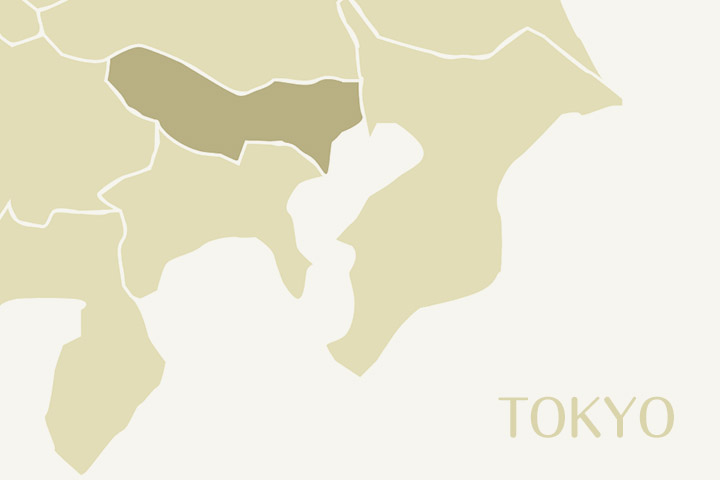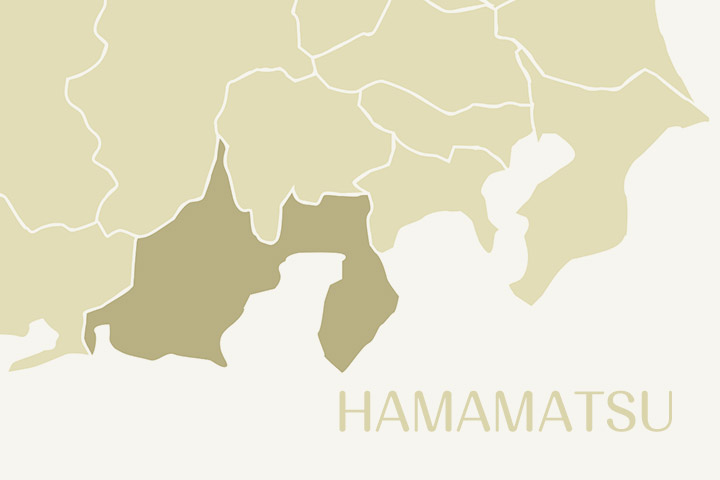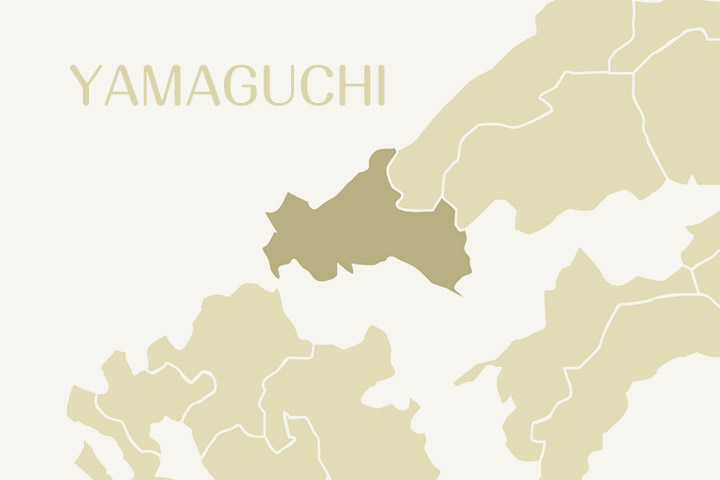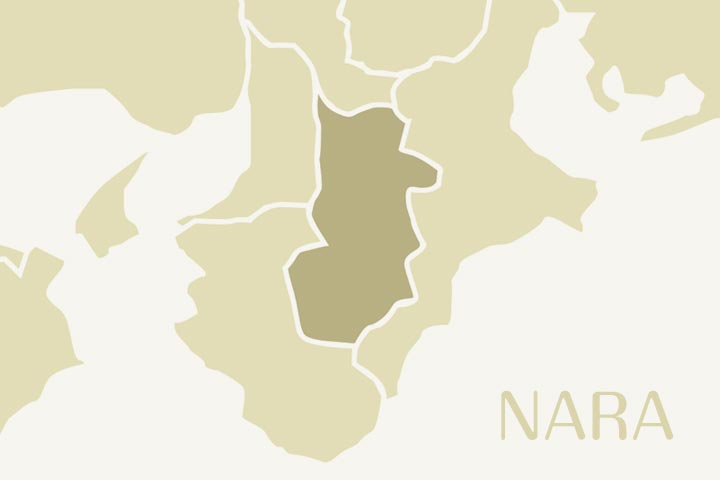▲上段、金沢でのオンラインフォーラムのパネリストの皆さん。答えを語るのではなく問いかけるような対話のフォーラムだった。下段右、金沢の冬の風物詩、兼六園の雪吊り。見事な枝ぶりの松を吊る縄が大きく広がって、中心で一点にまとまっていく。「ともに生きる」の象形だ。
金沢で「認知症とともに生きるまち」と題してオンラインフォーラムを開く。
このフォーラムの特色のひとつは、パネリストの誰もが、地域での「現場」を持っているということだろう。
現場を持つということはどういうことか。それは現実を引き受けるということだ。
この新型コロナの日々の中で、だれもが現実を引き受けざるを得ない。なんとかしてくれ、と誰かに押し付けるわけにはいかない。
その中で何ができないのか、何ができるのか、目の前の逃げられない人々に逃げることなく「現場」を引き受け、向き合うことである。
そのような人々とのフォーラムだった。
新型コロナウィルスは世界に侵攻した。ウィルスは誰もに、ある意味平等にリスク配分をした。しかし、このウィルスの本当の怖さというのは、そのリスクはこの社会の一番弱い人々にシワ寄せされてしまうことだ。高齢者、病の人々へと狙いすましたようにクラスターとしてウィルスは侵攻する。
金沢市にあるデイサービス「ゆいまーる戸水」を運営する加納央氏のジレンマは深い。
「ゆいまーる」のサービスにはメニューはない。利用者が思い思いにやりたいことができる。映像では認知症の婦人がキッチンに立ち、料理をする。そのためにはケアの人たちとスーパーに買い出しに行き、その食材から献立を相談する。その一つひとつが地域でともに生きる実践だ。
しかし、いつもやっていることができない。外出も制限され、食事も互いに離れて会話をしないように黙々と食べるしかない。いつもの賑やかな食卓風景が消えた。
「こんなの、ちっともここらしくない」、ケアの女性は本当に悔しそうだ。
管理者の加納氏は、「そうは言ってもこの場をなくすわけにはいかない。しかし、もし感染者を出したらどうなるのか、やはり自己責任ということになるのでしょうね」と割り切れなさを抑えて語る。
「自己責任」となるのだろうか。近年の自己責任という言葉の使われ方には、この社会の悪意が潜む。この社会の一番脆弱な部分に「自己責任」を押し付け見捨てて、どうこの超高齢社会を運営できるというのか。
新型コロナウィルスは、誰もが感染しうる。同じように認知症は誰もがなりうる。老いることは誰もが辿る道だ。誰もの未来を誰かの責任で論じることができるのだろうか。誰かの、ではなく、誰もが分かち合う自己責任ではないのか。
なぜ「自己責任」と言う言葉が、醜悪な響きを持ってしまうのか。
それはこの事態での、「感染したもの」と「感染していないもの」との分断から生まれる。感染することを否定の文脈でしか捉えていないから、自己責任に差別と中傷を押し付け合う。それまで心地よく語り合っていた私たちの共生社会は脆くも崩れた。
誰もがなりうるという当事者性から見れば、誰もが感染しうることを前提としてこの社会を再構成するしかない。それが「安心して感染できる社会」ということだ。
あえて言うまでもないのだが、感染対策をなおざりにしてもいいということでは全くない。ただ、濃厚な感染対策が、この事態だからしょうがないとして振り落としていることはないのか、あるいは見えなくしていることがないのか、そのことをも話し合った。
端久美氏は、石川県白山市の特養の老人ホーム福寿園の施設長である。彼女の語ることの重さに壇上は言葉を失った。
新型コロナウィルスの事態で、施設でもこれまでの活動の制限を重ねざるを得ない。一般の人々にとっては自粛であっても、認知症の人にとっては自由の剥奪であり、それは本人への拘束や虐待となっていく危険を孕む。正直、ではどうすればいいのかはわからない。だが、せめてせめての思いとして、このことを仕方ないとせず、これは拘束なのだと自分に言い聞かせるしかないと、そのギリギリの想いを押し出すようにして語った。
ここでの拘束は、あからさまな縛りつけるような拘束ではないだろう。それだけにケアする側が陥りやすい錯誤となって容認してしまいがちである。認知症の人を自室から出さないようにする。それは感染対策なのだから仕方ないとするのではなく、自分は、今、その人の思いを封殺し拘束していると厳しく自己検証を課していくことをせめての責務とする。
新型コロナウィルスがもたらしたものは決して一過性の災厄であるはずがない。それはこの社会の歪みを暴き、脆弱を洗い出した。が、同時に、現場を引き受けたケアの人々の中に、この事態に改めて本人の思いを取り戻すような気づきが生まれている。
コロナの日々は、現場の人々に本当に必要なことは何か、何をしなければならないかをも示したとも言える。
こうしたオンラインのフォーラムは全国各地で開かれている。当初の、つながりが途切れた時のせめてもの代替機能としてのオンラインは、しだいにそこに多くの人が関わり参加し、それまでの福祉的な関心度の高い集団の枠組みを超えた広がりを見せてきた。
金沢のオンラインフォーラムでもそんな変化が語られた。
オンラインでの語り合いは、ディスプレイの中での語り合いだ。
リアルに対面できないそのもどかしさは、かえって事態の切実さを際立たせ、聴衆を前にした場合よりどこか内省的な密度ある語りに傾く。
今回のフォーラムでも、ケアの現場の人から「拘束」や「虐待」が語られたことは、その課題性ももちろんだが、そのようなことを語り合える成熟を、私たちはオンラインに付与できたのかもしれない。
今や、ウイズコロナの時代とも言われるフェイズに入り、私たちの意識の深層にも変化が起きている。「どうすればいいのか」と言ったやみくもの対策対応を抜け出て、「どうあったらいいのか」とする静かに深い自分自身の存在への問いかけといったことが起きている。
今再び、急速な感染拡大への可能性が言われている。
だからこそ、どうすればいいのだと狂乱するのではなく、どうあったらいいのか、誰もが当事者であるふるまいが問われるはずだ。
試練の日々が続くことは間違いない。しかしそれはウィルスがもたらしたものと言うより、私たちの側の、「ともに生きること」の試練と言ったほうがいいのかもしれない。
「つながり続けることです」
金沢の「若年性認知症の人と家族と寄り添いつむぐ会」の副代表の道岸奈緒美さんは、どんな時でもいつもそう言う。
自分たちが認知症の人々と積み重ねてきた「認知症カフェ」の対面しての取り組みは3ヶ月の中断を余儀なくされた。今はリアルなカフェと、オンラインを併用しながらの取り組みだ。
「つながり続けること」、その困難や難しさも承知しながら、道岸さんは、道岸さんの「現場」を引き受ける。