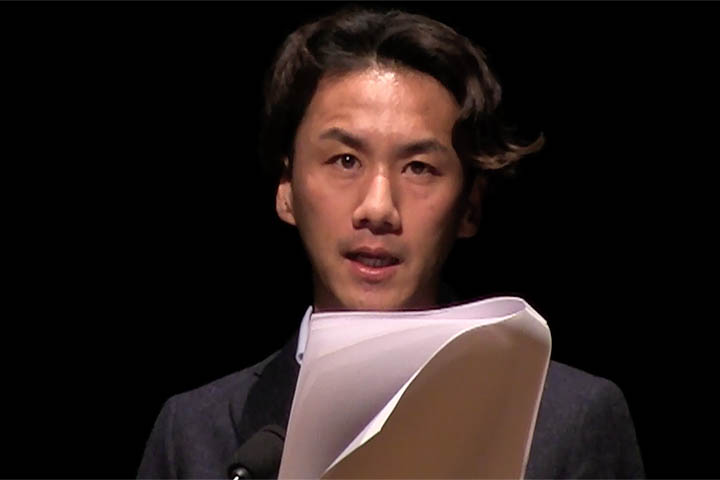▲パンデミックとは地球規模の大流行。私たちの社会のつながりは途切れても、この惑星のウイルスのつながりは緊密につながりこの惑星を覆い広がっていく。地域社会の暮らしのリスクと地球のリスクは別物ではない。そのことに関心を持ち続けることも大切な暮らしの感染対策のはずだ。(写真・NASA)
この頃ことあるごとに耳にする「コロナ禍」という言葉に、私はどうも馴染めない。
あれは、「新型コロナウイルスが・・」と、いちいち書き出す手間を省いたとか、新聞の見出しの字数スペースの倹約になるとかの説もあるらしいのだが、それ以上にあの「ころ・なか」というころころとした音韻の軽さと、そう言い切ってしまう言葉とその運用に杜撰と怠慢を感じてしまう。
「コロナ禍でわたしたちの暮らしはどうなるのでしょう」と眉をひそめながらキャスターが言う場合、主文を規定するのが「コロナ禍」である以上、全ての責任はコロナにあり、私たちは一律に被害者という匿名集団になる。コロナ禍と投げかければ、自分の問題意識とは無関係に、いくらでも眉をひそめられる。とにかく災いは、あっちからやってきたコロナなんだからね、こっち側としては肩をすくめるか、眉をひそめるかするしかなく、そうすれば何を言っても大衆はうなずいてくれるであろう、というその言説があやうい。
私がどうも気になるのは、「コロナ禍」とすることで、私たち全員が「この禍いに巻き込まれてしまった被害者」という位置付けになってしまうことだ。
確かにこの新型コロナウイルスのもたらした事態は、禍(災い)であろう。
辞書によれば、禍いとは天変地異、病い、災難など人を不幸にする出来事、とある。だから語彙の定義からしてもコロナ禍でよろしかろうとなる。
しかしこの事態の私たちはなべて、禍いとその被害者なのだろうか。私たちはただただ不幸な被害者であって、それは禍いによってもたらされた人智の及ばぬ事態とくくってしまっていいのだろうか。コロナ禍の連発は、責任は全てコロナにあるとする思考停止を招く。
この事態を、コロナ禍とその被害者と単純化してしまえば、見るべきものも見えなくなる。
施策の無策ぶりは災いである以上に、その失政は暮らしへの加害ではないのか。孤立の中で、被害者とされる人が誹謗と中傷、差別に走ったのは、被害者なのか加害者なのか。
誰もが公平にこうむったはずの被害に、リスクの不公平が生まれ、不幸の格差に分断し、互いに監視し合い、被害者集団の中から加害者を生み出してしまったのは何故だろうか。
今再びの緊急事態宣言が、世間の感覚ではほとんど新たな災いとして捉えられている。災いは見えないコロナがもたらしたのではなく、この緊急事態宣言が作り出しているのではないかという閉塞の感覚。それは誰もが疲弊し萎縮する中の幻想と片付けるわけにはいかない。
感覚的にも、最初の緊急事態宣言の時の気分と現在とはかなり密度が違う。最初の宣言の春には、桜の花の下で多くの人々が「今、自分にできること」を引き寄せながら、離れていても結集する感覚を頼みにして乗り切ろうとした。今、「自分にできること」の声は、とてもか細い。徒労感だけが漂う。メディアがキャンペーンとして呼びかける「今、自分のできること」が空疎に響く。
このことは案外に深刻なのではないか。「コロナ禍」で覆い隠されて、せっかくの「ウイズコロナ」の新たなパラダイムも、今の社会の人心や状況も見えてこない。
だからこそ、ここは一旦深呼吸して、私たちの言説を立ち上げよう。
禍、わざわいを作り出したのは、実は私たちの側でもあるのではないか、と。
新型コロナウイルスがもたらした事態はパンデミック、地球規模の大流行である。
パンは全て、デミアは人々を意味するギリシャ語を語源とする。島国で身を寄せ合う私たちはこうした全体を包摂する広々とした概念の言葉、パン(pan)を持っていなかった。そこでpanに「汎」という漢字を当てたとされ、そこから汎太平洋とか汎アジア主義といった言葉が生まれている。
UNDP(国連開発計画)では、パンデミックには国境は関係なく、最も弱い立場にある人々が最も大きな打撃を受け続ける、と警告している。
先進国と貧困国との医療と感染対策の格差、富裕国のワクチンの占有や接種体制の格差はそのまま途上国の未来を破壊する。感染対策は一国で完結するものでなく、世界での感染が収束しなければ、私たちのこの国だけが感染から逃れることはできるはずがない。
私たちは、国境を越えた「汎」の発想が求められている。それは、世界の苦難にも目を向けることで、自身の当事者性の汎用を確かめることだろう。このウイルスを、世界の中の私たちの試練とすることで、世界市民としてのしなやかな思いも立ち上がってくる。
私たちの今抱えているコロナ禍での怯えや不安は、こうした「汎」という世界観の中でしか解消はできないだろう。そしてそのことが、今回の緊急事態宣言の閉塞に、風通しのいい新たな発想を生むかもしれない。
世界を見つめることが、自分の足元を見つめ、そして目の前の人の困難や自分の行き詰まりと世界のパンデミックとがつながる時、自分のことだけの不安から離れて、世界の人々との連帯が見えてくる。
世界に踏み出し、世界の不幸をどこまでも引き受け、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師は、今から30年ほども前の著の後書きで、まるでこの世界的破局の事態を予見したかのように、私たちの今に向けてメッセージを伝えようとしている。
「今、内外を見渡すと、信ずべき既成の「正義」や「進歩」に対する信頼が失われ、出口のない閉塞感や絶望に覆われているように思える。十年前、漠然と予感していた「世界的破局の始まり」が現実のものとして感ぜられ、一つの時代の終焉の時を、私たちは生きているように思えてならない。
強調したかったのは、人が人である限り、失ってはならぬものを守る限り、破局を恐れて「不安の運動」に惑わされる必要はないということである。人が守らねばならぬものは、そう多くはない。そして、人間の希望は観念の中で捏造できるものではない」
────「アフガニスタンの診療所から(文庫版後書き)」中村哲