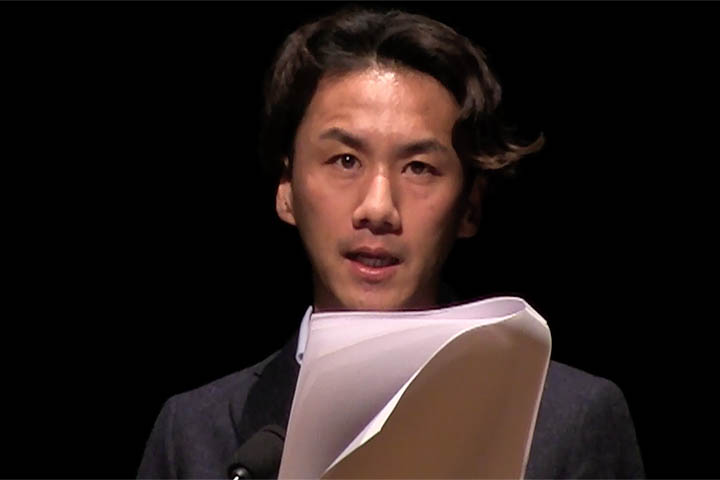▲不発弾で両目と両手を失った元教師の藤野高明さん(82)は、今も教職を目指す学生たちに語りかける。藤野さんの日常と言葉を伝える映像は、今を生きる若者たちの心をわしづかみにした。それはなぜなのだろう。(写真:NHKハートネットTV・HPより)
福岡の小さな町のある朝、小学2年の子供が弟と、近所の小川に無造作に捨ててあった鉄パイプで遊んでいた。それは銀色に光り、少年と弟にとってはなんとも魅惑的な外観をしていたのだ。戦争が終わった翌年1946年の夏のことだった。
すさまじい爆発が7月の夏雲を切り裂いた。旧日本軍の不発弾だった。
少年の弟は即死。少年は、両眼の視力と両手を一瞬にして失った。
少年は、その後教師になる。
その藤野高明さん(82)の手記「人と時代に恵まれて」が、2002年の「NHK障害福祉賞」の最優秀賞になった。そしてその手記をもとに藤野さんのそれまでの人生が今年の5月にNHKハートネットTV「文字の獲得は光の獲得でした 〜両眼と両手を失って教師になる」という番組となった。
この藤野さんの映像が、番組に先だってネット上のYouTubeで公開されると、10代20代に大反響を呼び起こした。「この人すごい」「勇気をもらった」「人間の可能性を信じたくなる」、そうした若者の声が次々と寄せられ、その再生回数は430万回を超え、なお増え続けている。おそらくその反響に番組関係者は慄然とした思いを抱いたであろう。
番組は再構成され、この8月には総合テレビでも放送された。最初の番組からは異例ともいえる三度にわたってひとりの二重障害の元教師の姿を伝えたことになる。
何がそんなに若者の心をとらえたのだろう。
この稿の冒頭部分で私は「少年は、両眼の視力と両手を一瞬にして失った」と書き出し、次いで一挙に時間を飛び越え、「少年は、その後教師になる」と直結させている。その間に、一行分のスペースを置いた。
一行の空白に何があったのか。それはとてもここで記し切れるものではない。すさまじい差別と排除、壮絶な差別との闘い、と記すこともできるかもしれない。当時の現実はそのようなものであった。しかしそうした紋切りの言葉で記してしまっては、大切な何かがすり抜けてしまう。
この番組には声高なところも、尖ったメッセージも盛り込まれていない。ただ淡々とした藤野さんの日常と語り口が、そのまま伝えられている。そのことがかえって視る側を大きく揺さぶる。一行の空白にながれた歳月と、取り戻してきた人生のとてつもない重量を実感する。
「文字の獲得は光の獲得でした」という番組タイトルは、藤野さんの手記の中の言葉だ。
両手のない藤野さんは点字を唇で読む。最初はザラザラとツルツルしかわからなかった点字を、唇の上の何ミリかという感覚部分で際限なくなぞっていくうち、やがて、いくつかの文字が浮かぶようにわかってくる。そしてそれは文字の塊となり、言葉になり、そしてついには文章となって理解できるようになる。
「光を失った自らの世界に、一筋の光が射しこんでくるのを感じました」と、藤野さんは記し、映像では「たとえようのない嬉しさでした」と語っている。
藤野さんの人生に一筋の光をもたらしたものはもうひとつある。
北条民雄の「いのちの初夜」である。ハンセン病を発病した主人公の極限的な生と死を見つめた小説だ。
藤野さんは目の手術のために入院していた時、3歳年上の看護学生と出会う。
視力の回復は無理と言われて自暴自棄になっていたころだった。「何かできることはないか」という看護学生に、「何か本を読んでほしい」と求めた藤野さんに読んだのが「いのちの初夜」だった。
看護学生の女性は「面白くないと思うけど」と言いながら彼の傍で本を読んだ。
その本について、藤野さんはインタビューでこう語っている。
「面白くないと思うけどと、彼女が言うから、それなりに覚悟して読んでもらってたんですが、なんかすごく引き付けられて一気に読んでもらった」
北条民雄の「いのちの初夜」には、ハンセン病療養施設での一夜の体験が記されている。そこでは、顔全体が病に侵された付添人との深夜の病室での対話が続く。その付添人は、重症となった患者たちについて、「静かに重大なものを含めた声で」こう尋ねる。
「あの人たちを、人間だと思いますか」
こたえられない主人公に彼はこう続ける。
「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです」
深夜の生と死をめぐる問答、苦悩と葛藤は圧倒的だ。
その後、散歩しましょうと二人は外に出て、そこで主人公は「やはり生きてみることだ」と強く思いながら夜明けの曙光を見つめて小説は終わる。
当時、人生にすさんでいたという藤野さんは「いのちの初夜」のどこにそれほどひきつけられたのだろう。
藤野さんの人生の軌跡と「いのちの初夜」の苦悩と葛藤はどこか深いところで通底している。それは「いのち」であり「生きる」ことへの存在の獲得と言っていい。
幾多の困難や差別の中をかいくぐってきたであろう藤野さんの手記のタイトルが、むしろ向日の響きに満ちた「人と時代に恵まれて」であることは、そのことを物語っている。
そこにあるのは、「光の獲得」としての根源的な「人間肯定」なのだ。それは「いのちの初夜」の主人公が夜明けの光の中で、「生きてみることだ」と、強く自分に言い聞かすラストシーンと不思議に符合する。
藤野さんの映像が、あれほど多くの若者の心をとらえ続けているのはなぜなのだろう。
それはおそらく、真っ直ぐにこの「人間の存在」が届いたからなのではないか。
ある女性は、その感想をSNSでこう寄せている。
「不屈の精神、切実な学び、柔らかな物腰、優しいお声、人間としての在り方、原点を私も教えられた気がします。ありがとうございます」
自分の中の言葉を探り当て、藤野さんの映像を的確に見て取り、言葉を重ねて自分の感性に響かせながら自己存在の原点につなげている。この番組を見たある精神科医は、「沁みるような番組だった」と語ったが、まさに若者たちに理屈ではなく、渇いた心に沁みるように届いたのだ。藤野さんの映像は、今のパンデミックの日々に閉塞する自分たちの日常と地続きなのだ。
パンデミックの日々は今なお先行きが見えない。むしろ一歩あゆむごとに沈み込んでいく。そこでは、誰もが「感染者」「重症者」であり、「高齢者」「若者」と感染リスクで区分けされた顔の見えない匿名で語られる社会である。
この映像は、両眼と両手を失った元教師が、失明したまなこで時代を見据え、失ったかいなで確かな自分を獲得した記録である。
この事態のノイズの中に彷徨う若者たちの存在不安に、命や生きるということの確かな「人間」の存在を、あの映像は直感させたのかもしれない。
私は、そうした若者たちの反応に、時代に射しこむ一筋の光を見る思いがする。