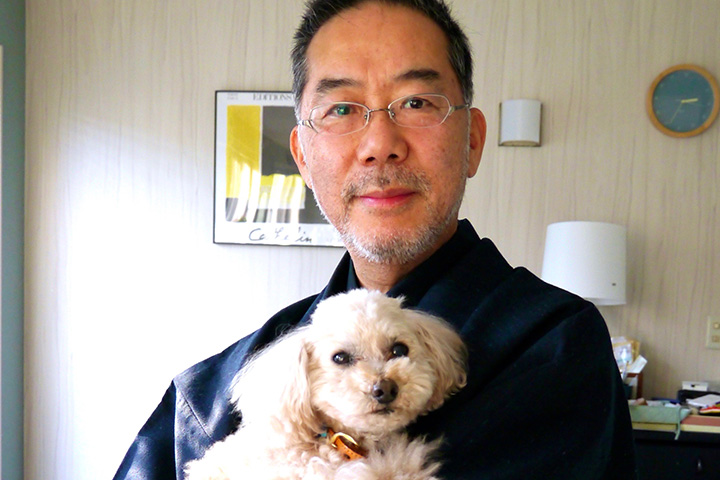▲人前で語るとき、語りながら新しい考えにきづくことがある。聴衆との交感がそれをうながす。こればかりはオンラインにはない力だ。誰もが自分の語りを持つとき、新しいあなたが生まれる。
みなさんこんにちは、今ご紹介いただいたマチナガです。
えーと、私はおわかりのように医者ではないし、介護職でもありません。たまたまメディアの世界で認知症というテーマに向き合ってきた立場です。ですので、別段、認知症の専門家ではないのです。じゃ、聴いてもしょうがないとここからゾロゾロ帰る人が出ても当然ですが、実は、とここで力を込めて言いますが、専門家ではないからこそ、見えるものがあるし、語れることがあるのです。(エヘン)
それは何か。それは一つは社会総体の中に「認知症」を置いて考えるということ。もう一つは、私も認知症になりうる地域の生活者の立場で、そうした人々の息吹を感じ取りながら語ることが出来るということなのです。
私の講演の聴衆の多くは、別に認知症に関わる活動をしているわけでもないし、地域包括と言っても、は? という反応です。ただ、認知症については関心が高い。それは、なったら大変なんだという固い信念を持っている人が、ま、かなりというか、半数くらいはそうです。心身ともにスティグマにどっぷり浸かっている人々です。
でも実はそうした人々がこの社会を形作っています。「認知症と共に生きる社会」とは天から舞い降りてくるものではなく、私たちそれぞれが、自分たちの思いをより合わせるようにして組み上げていく、私たちの社会です。
それには、認知症に対して素朴なスティグマを抱いている、というより抱かされてしまっている人々の力が必要なのです。そうした人々を埒外において「認知症と共に生きる社会」ができるはずがありません。そのような人々に語りかけることが、これまで意外と手薄だったのかもしれません。
ですので、ここからは現実と擦り合わせながらお話しできたらと思います。
まずは四つの設問を提示します。世間ではよく言われていることです。でもあまり大っぴらには言われません。それは最近の「認知症と共に生きる社会」の理念の中では、どうもマズイと思われているからかもしれません。でもこのことにしっかりと向き合わなければ、認知症と共に生きる社会なんてお風呂屋の富士山です(若干意味不明)。
では、最初の問題です。
近所のおっさん、おばさんがこう言うのを聞いたとき、あなたはどう答えるでしょうか。
「認知症でも大丈夫ってよく言うけれど、そんなわけないでしょ」
どう答えますか。それぞれの答えが大切です。
でもまあ、私見を述べておきますね。これは世間には「認知症になると大丈夫ではない」という情報が圧倒的で、しかも説得力があるのです。それは現実のスティグマの側に身を置いているからです。これを突き崩すために、ちゃんと考えた方がいいと思います。
一番いけないのは、おまえなあ、問題意識低いなあ、とうそぶいて背を向け立ち去るあなたです。その人を批判するのではなく、社会のスティグマの側を変えなければいけないのです。
次、「認知症でない人が認知症の人を本当に理解できるんですか」
つぶらな瞳を輝かせた女子高生(である必要はないのですが)からこう聞かれたらどうしますか。風邪を引いた人には、私たちはごく自然に、そして親身に「大丈夫ですか? つらいでしょうね」と心底言えます。それは誰もが、風邪を引いたことがあるからです。
しかし、まだ認知症になっていない人にとっては、認知症を理解すること自体がとても難題に映ります。しかしこれは今に始まった事ではない。女性の社会参加の過程で、かつてこんな声も出ました。「お腹を痛めたこともない人に、分かるはずがない」「おしめを変えたこともない人に、子育てのつらさなんて語ってほしくない」
ここにある壁は、両者の交換不能の立場性です。一方が他者との立場の交換を不可とする時点で、理解の扉は開かない。あの状況での女性がいかに周囲の無理解と偏見の中に孤立していたかを示しています。
認知症の人と対する場合の壁は、「認知症」と「自分」との立場交換を不能と思い込んでしまうこちらの側にあります。そうではなく、認知症の「人」と「自分」の立場交換なら、どこか可能なはずではありませんか。
だって風邪を引いた人への共感は、「風邪」と「自分」との立場交換ではなく、風邪を引いて鼻水を垂らしているその「人」と「自分」との関係性で共感を寄せるのです。
認知症当事者の先駆者でいち早く認知症の人の権利を主張したケイト・スワファーは「認知症を見るのではなく、人を見よ(SEE THE PERSON NOT THE DEMENTIA)」と力強く語りました。
次、三つ目の問題です。「認知症にはなりたくない」にどうこたえるか。
本音で言えば、こう思っている人は多い。というかマジョリティでしょう。これを言論統制しても逆効果です。そうでしょうね、と一拍置いてそこからどう言うか。
「なりたくない」というのは本音でしょうが、この場合の課題はそう言った途端に、認知症に対する想像力の一切を遮断してしまうことです。「なりたくない」と「考えたくない」をごちゃ混ぜにしています。こうした言説に対する対応がいつも「偏見」「無理解」というだけで放置されるから、生活者の本音の奥深くに、「ま、表立っては言わないけどな、そりゃ、認知症になったらもうおしまいだわな。そうだろ」と居酒屋に偏見を跋扈させるのです。
ゴギブリは堂々とリビングの真ん中を歩いていくわけではないのです。部屋の隅の家具の裏でしっかり繁殖しています(ナンノコッチャ。偏見のことです)。
「なりたくない」と言う人にこそ、「ではなぜなりたくないのか、一緒に考えてみましょう」とリビングの真ん中で誠実に問い返せるでしょうか。
次、第四問。「うちのおじいちゃんは、もう何もわからないからどうしようもない」、さてどう答えますか。
この声は意外と多い。当事者発信が盛んになるにつれ、切実な自分の抱える現実が取り残されてしまうような気がしているのでしょう。講演の後の質疑によく出る声です。その現実からしてムゲにはできません。私はこんなふうに答えたことがあります。
「それは大変ですね、私は医療者や専門職ではないので確かなことを述べることはできません。ただ、当事者やその家族の声を聴いているとどんなに進行してもどこか感情は息づいているといいます。言葉や表情は消え去ったようでも、どこかわかっている、と。
「何もわからなくなった」ではなく、「どこかわかっているはず」というふうには考えられないでしょうか。目の前のおじいちゃんと接しているあなたにはとても無理なのかもしれません。
でも、それは願いでもいい。祈りと言ってもいい。そう念じ続けるようにしてどうにかなるのか。どうにもならないかもしれません。おじいちゃんが元気に立ち上がって笑顔で語りかけることはないでしょう。
でもね、変わるとしたら、あなたが変わるのです。あなたの中のどこか心の片隅がコトリと変わる。おじいちゃんを見るまなざしにかつてのおじいちゃんの姿が投影するかもしれない。あなたの日常に何か目に見えない変化が起こるかもしれません。
「あなたが変わる」と私は申し上げた。しかしそれは、おじいちゃんの存在自体があなたを変えたのです。おじいちゃんがあなたを変える。それが本当の認知症理解です。
どんな状態でも、その人の感情は息づき、それをあなたはわかることができる。そう祈るようにして思うことであなたが変わり、そのあなたが接するおじいちゃんはきっとどこか深いところであなたのおじいちゃんに立ち返ります」
私は心を込めて、そうしゃべる。多くは納得しない表情で席に座る。でも今後も私はこう語りかけつづけるだろうと思います。
ここまで、暮らしの中の根深い認知症観にどう語りかけるか、そのことを私なりにお話ししたつもりです。認知症を語るとき、多くはここをジャンプして語られます。こうした声はないものとして、歓迎すべきポジティブな認知症観ありきのその前提で語られがちです。
これまでの生活者のネガティブな思いはすべて、「認知症」を対象化した上に築かれていました。「なりたくない」にしろ、「理解できない」にしろ「もう何もわからない」にしろ、すべて「認知症」を他者性の視線で睨みつけ、しっしっと追い払うように自分の暮らしから遠ざけてきたのです。それは本音である以上、ここが変わらなければ本当の共生の認知症社会に到達できないと思います。
認知症を「自分ごと」として考える、これは想像以上に難しいことです。自分ごとである以上、それぞれ自分の語り口を持つべきです。私はこんなふうに語りかける、あなたならどのように語るのでしょうか。
「認知症と共に生きる社会」とは、とりもなおさず「自分と共に生きる社会」、私はそう思います。(まばらな拍手・・)
ありがとうございました。礼