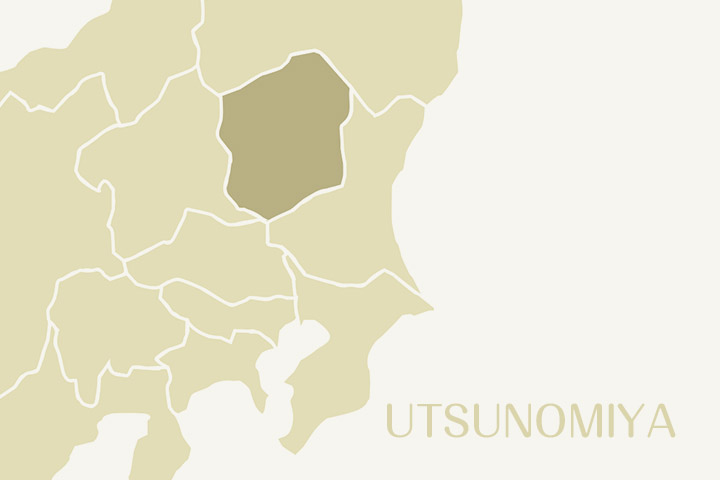▲ VRによる認知症の体験会の様子。会議室の中が認知症の世界にワープする。それぞれが認知症を「体験」し、その後にその意味合いの読み解きが続く。
先日、都内で開かれた認知症VR体験会に参加した。VR、バーチャル・リアリティとは仮想現実。360度の映像を映し出すHMD(ヘッドマウントディスプレイ)のゴーグルをつけることで、あたかもその映像世界を体験できるというものだ。認知症の人の世界を体験できるとは一体どんなことで、どんな意味合いがあるのか。
正直、好奇心と懐疑心とがないまぜで参加した。今回の参加者は認知症研究者、薬剤師、ソーシャルワーカー、そしてメディア関係者とどちらかといえば、認知症への関心度の高い人達がメインだった。早速ゴーグルとヘッドフォフォンをつけてみる。おお、眼前に宮殿のような空間が広がり、ぐるりと首を回すと背後にも庭園にベンチが並んでいる。ここはユニバーサルスタジオ・ジャパンなのか。
これはデモ映像なのだが、殺風景な会議室で、いい大人たちが集団でゴーグルをつけてグリグリ頭を動かして天井を見上げたり後ろを見たりという、傍から見れば異様な光景だったに違いない。さて、本編である。「ここはどこですか」というタイトルから映像での認知症体験が始まる。場面は高いビルの屋上だ。そこから覗き込むとはるか下に車がゆきかう大通りがある。ゴーグルをつけている自分が覗き込むとビルの屋上のヘリに立ち、踏み出すと墜落するかという感覚だ。誰かがキャア、と声を上げる。怖いよね。「大丈夫ですよ」と声をかけられ、左を向くと間近に人がいる。
この設定はデイケアに通う認知症の人が送迎バスから降りるときの状況である。認知症の人はバスのステップから降りようとするが、視空間失念のため高いビルの屋上から飛び降りるような感覚に襲われている。しかし、介護スタッフはすぐ隣で優しく降りるように促す。いくら大丈夫ですよとやさしく言われても、高いビルの屋上から下へ降りろと言われている本人の恐怖は解消しない。スタッフの側にどんなに専門の知識や経験があっても、認知症の人の感覚との距離には大きな隔たりがある。それは単に笑顔や優しい声かけでは埋めきれない。
VRで認知症を「体験」するというはどういうことか。
風邪をひいた人に対しては誰もが、「それは大変ですね、つらいでしょう」と何気なく言う。それは誰もが風邪をひいた体験があるからだ。だから風邪の人への共感は誰もが持てる。しかし、世の多くの人は(まだ)認知症を自分で体験していない。そうした人々はなんとか「理解」まではできる。しかし、体験していない以上、「理解」からそれから先の、本当に「共感」するには限りなく難度が高い。
そこに自身の「認知症体験」があればまったくちがう、と言うのはこのシステムを開発したシルバーウッド社長の下河原忠道氏だ。認知症を「一人称」として、つまり「自分のこと」として体験するインパクトは大きい。どうしても抽象的な呼びかけに終止しがちな「認知症にやさしいまちづくり」も、このVRでの「体験」は一気にその垣根を乗り越える可能性があるだろう。と同時にVRという「疑似」体験では限界もまたあると思う。単にVR体験だけだとやはり「異常体験」「ホラー体験」的な関心に引っ張られがちだ。この「体験」を共有し、語り合い、確認するワークショップや、あるいは今回は開発者の下河原氏が担ったような、ファシリテーターの養成といった一体化したシステムとして成熟させる必要がある。
VR体験をするということは、疑似体験を突き抜けて、つまりは自分自身の中に「認知症の人」という「当事者性」のリアルを根付かせることだ。「体験」が自分の認知症観の変化を呼び、それを地域と社会の転換までつなげていく、それは畢竟、「体験」した一人ひとりの「認知症の人」としての当事者の役割なのである。

▲ 当日の認知症VR体験会参加者。前列右から4人目、白のワイシャツ姿が開発した下河原忠道氏。ファシリテーターの役割も果たしていただいた。
|