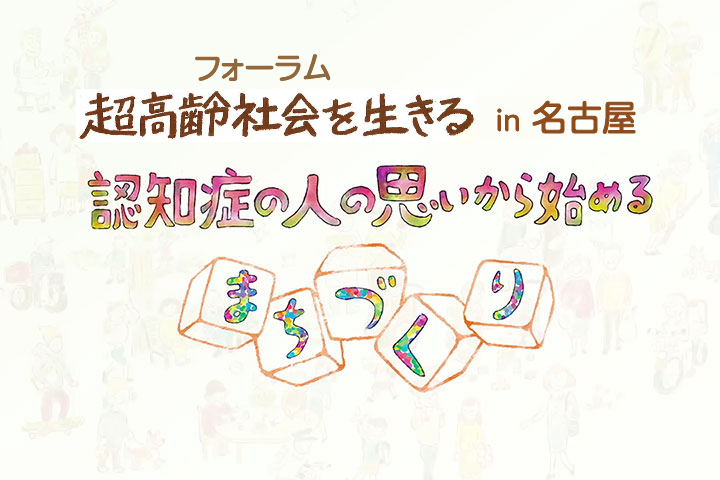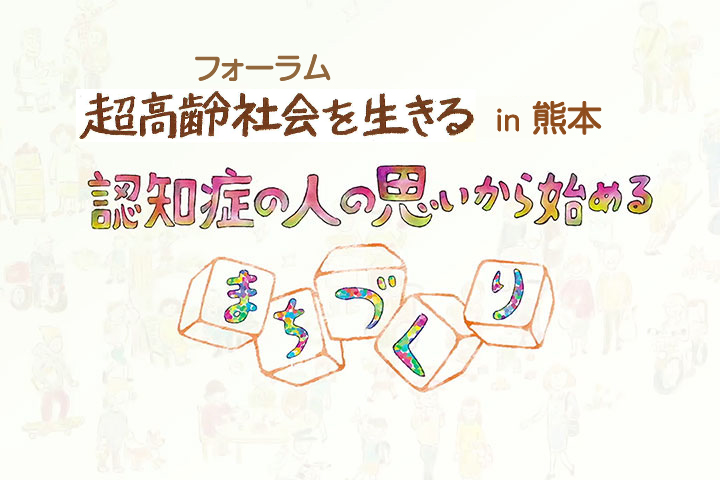▲ 先日の当事者勉強会の世話人会の様子。報告はのぞみメモリークリニックの木之下徹医師。認知症に関してはこのところ音立てるようにして施策が動いている。認知症官民協議会、大綱案、そして基本法の骨子案など。その中で私たち当事者は待っているのではなく、動きにどう発信できるのか。正念場かもしれない。
6月15日に都内で開かれる認知症当事者勉強会の案内が届いた。
今回の報告者は、認知症医療の木之下徹医師である。
案内文にはこうある。
木之下さんは、「認知症医学は予防、回復、維持、いずれについても多くの人が期待するほどの成果を上げられていない」、と言います。だが同時に、「医学は敗北していない」とも。
木之下徹という人は認知症医療についてはラジカルであると同時に、中高生の青春の頃には、スコアを読みながらブルックナーを聴き、あるいは風呂の入口に置いたラジカセでマーラーを流しながら入浴し読書に耽っていたという多感な人である。
そんな人柄を知った上で案内文を読んで浮き上がるのは、木之下徹氏は実は、自身の打ち出す理念のテーゼと実践とで、引き裂かれるようなアンビバレンスを抱いてしまっているのではないだろうか、という思いである。
それはまるで右手に理念を握り、左手に現実を捕まえて、その自分自身の左右の手を、どうしても合わせることができないで苦悩しているようだ。
「認知症の人とともにある認知症医療」とはどんなものなのか。
「認知症とともに生きる旅の最初の第一歩」とはどういうことか。
あるいは、「認知症医学は期待する成果を上げられていない」としながら「医学は敗北していない」とどうして言えるのか。
というのも、この勉強会の世話人会を開いた時、ちょうど政府が認知症の大綱案を示した。それは予防対策を強化することが柱で、70代の認知症の人の割合を、10年で約1割減らすことを目標とする数値目標を初めて打ち出したのだ。
ここでの「予防」や「数値目標」ついては報道した各紙のほとんどが違和感や疑義を記した。
それは、現時点で認知症を予防する科学的なエビデンスを持つ方策はない中で、なぜ「認知症予防」であり、「数値目標」なのかということだった。数値目標ありきの危険性を論じたメディアもあった。
心ある認知症医療者は誰もが「認知症予防に科学的なエビデンスある確定的な方法はない」と言い切る。認知症医療の英知の結集とされる日本精神神経学会監修の「認知症疾患診療ガイド」にもそのことは明記されており、それは現時点の認知症医療の常識であろう。
しかし、その中でどうして施策や世間に「認知症予防」があふれるのだろう。
ここに認知症医療の苦悩が滲む。
「科学的エビデンス」を根拠にして、認知症予防に実効性はないとしながら、実は認知症医療そのものは、この「科学的エビデンス」の縛りから脱出した地点を新たな目指す医療の姿としてきた。
それが、「認知症の人とともにある医療」であり、「認知症とともに生きる旅の第一歩」という理念的テーゼである。ここには、科学的エビデンスの裏書は必要とされない。
「科学的エビデンス」が説得力を発揮するのは、診断と治療が堅固に結びついたサイエンスとしての医療である。ところが、認知症医療は、治すことのできない「敗北の医療」とされた地点から歩み出し、そして「治す医療」から「支える医療」への転換を自らに課した。
そこに依拠するのは、科学的エビデンスではなく、むしろエビデンスの名の下に声を封じられてきた「認知症の人」だった。「患者」ではなく「人間」だった。当事者であった。
それは物語の風景で語れば、エビデンスに満ちたサイエンスである認知症医療が、大きく息を吸い込むようにして、「人間」の思想や哲学を取り込んで歩み出した姿ではないか。「いのち」の祭主が、「くらし」の伴走者として立ち現れた。
だから、エビデンスがないことを持って認知症予防を切り捨てるとするなら、それは、「なりたくない」と認知症を否認する人間の感情に医療は寄り添えないとすることであり、その人の希望を選別し簒奪することにもつながりかねない。
エビデンスがないからといって「予防」は否定されるものではないだろう。
本人が望み、良かれと思って取り組む暮らしの中の認知症予防を、科学的エビデンスがないからといって取り上げることはできない。
では否定されるべきは、なにか。
それは、「認知症予防」につきまとう根深い偏見である。認知症を「なってはならない病」とし、「なったらおしまい」という世間の素朴な思いが、実は認知症とよく生きる共生の社会の実現を阻み、その実現をひたすら先延ばしにしてしまう。
しかし、「認知症予防」から偏見を引きはがすのは、現実的にはなかなか難しい。
それは、「なりたくない」という気持ちには偏見が潜むことがあるので、そう思わずに「予防」しましょうと言うに等しい。
どうしたら、予防にまとわりつく「なりたくない病」のネガティブなイメージを振り落とすことができるのだろう。
ここは大切なところだ。ひとりひとりが今一度原点に立ち戻り、「自分」を見つめることが必要だ。
なぜ、認知症になりたくないのか。「なりたくない」という入り口で脊髄反射のように拒否するのではなく、そもそも認知症になりたくないと思う自分の胸の底を覗き込んで、なぜそう思うのかを探り切ることだろう。
どんな不安があり、どこが胸のつかえになっていて、思い浮かぶ人の顔や、自分の暮らしを点検するように考えてみる。
そして改めて「予防」を考えてみる。予防はその不安を解消するだろうか。解消してほしいと思う。が、懸命に予防すればするほど、なりたくないという不安はかえって濃くなるかもしれない。それを「こんなに予防しているんだもの」で、紛らわすことが、本当にできるのだろうか。
「認知症予防」の怖さは、あなたの認知症への想像力を、その時点で遮断してしまうことだ。しかし大丈夫。振り返れば、そこに「認知症医療」がある。あるはずだ、そう思いたい。
「認知症とともに生きる社会」、その共生社会は、同じ理念にうなずきあうような同志的な結びつきであってはならない。認知症になりたくないと思う人々をも内包する広々と、そして多様で深い社会であるはずだ。
さて、その時、認知症医療はどこにいるのだろうか。
木之下徹医師によれば、認知症医療は、かつては「認知症をなんとかしよう」から始まり、次いで「認知症のある人をなんとかしよう」となり、今は「認知症の人と、何かをしよう」となってきたと言う。
6月15日に認知症医療をテーマに当事者勉強会が開かれる。
それは「認知症医療は何ができるのか」ではなく、「認知症医療と、私たちは何ができるのか」、そんな話し合いになりそうな気がする。