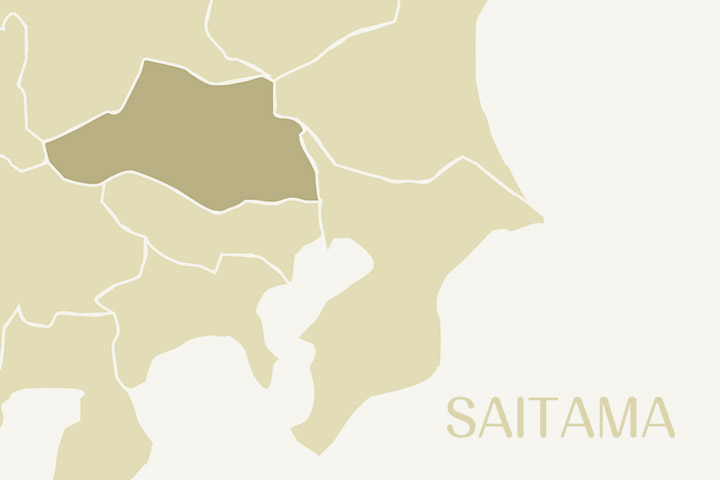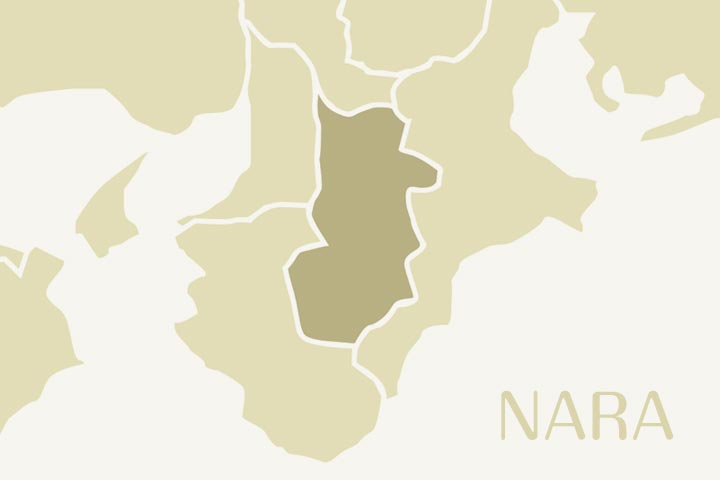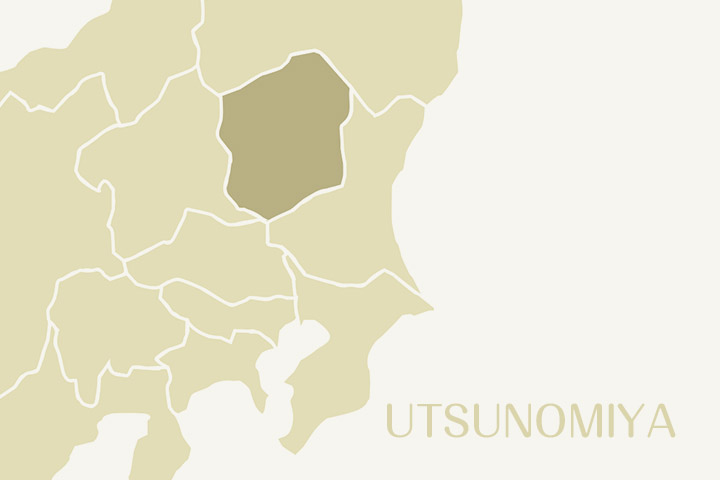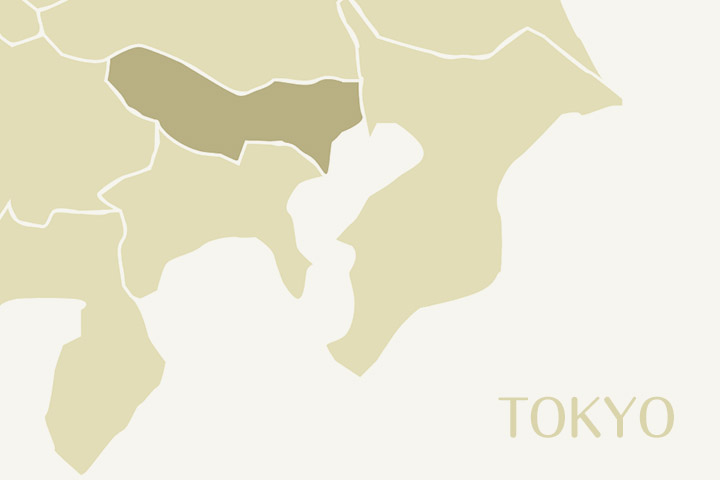▲上段、左が八森淳「つながるクリニック」院長。右が町永氏。下段、対談では、訪問診療での事例がいくつも紹介された。それは事例であると同時に誰もの人生の物語にも重なり、聴衆の共感を呼んだ。
先日、横浜で地域医療をテーマに対談をした。
対談相手は、横浜港南区で「つながるクリニック」というなんともぬくもりのある名称の医療法人院長の八森淳さんだ。
実は八森さんとはずいぶん以前から私の関わっていた認知症フォーラムでご一緒してきた。
八森さんは、多職種の人々や地域の住民も参加してのユニークな地域医療の実践で、関係者の間ではよく知られている。
その八森さんの「つながるクリニック」とは、文字通り「つながる医療」の実践なのである。つながる医療と一口で言うが、その「つながる」と言ったやさしげな言葉の背後には地域の厳しい現実が横たわる。だからそこでの実践には、医療の専門性を超えた暮らしへの深い見識と対応が求められている。そこでの「つながる医療」とは、どんなものなのだろう。
八森さんのクリニックは、団地の一画にある。
元パン屋さんの店舗の佇まいをそのままに残していて、大きなガラス戸の入り口である。
つい「こんにちわー」と入っていきそうである。「いらっしゃい」「毎度!」と言う声が返ってきても不思議ではない。でもそこはクリニックなのである。
そのクリニックは、横浜の巨大団地の中にある。
横浜港南区の野庭団地は、市営住宅と分譲団地合わせて、分譲戸数6000戸と全国2位の大規模団地とされる。
団地には緑豊かな遊歩道が整備され、週末とあって多くの人出で賑わっていたが、やはり高齢の住民が多い。
今、全国各地、とりわけ都市部ではこうした団地の高齢化が地域社会に重くのしかかっている。高齢化に加えて建物やそこの施設などの老朽化、そして現役世代の人口減少が、その先に立ち塞がる。
八森さんのクリニックは、この巨大団地の一画に開業して、今年で7年になる。
その7周年を記念しての講演会なのである。
八森淳さんと訪問診療や生活支援の実践を語り合いながら、私はここにあるのは、今この社会が必要としている「先進の医療」なのではないか、そんな思いに駆られた。
通常「先進医療」と言うのは最新の医療技術や知見をもって、それまで治療困難とされてきた疾病に対しても治療可能とする輝かしい成果として語られることが多い。
しかし一方ではこの国は、超高齢化の中で、ひとつの慢性の病を持つことで自分らしい暮らしが困難になる人々で溢れている。病は治すだけで済むわけではない。その人の暮らしを取り戻す道筋までを支える医療の不在は、人々を病院通いと入院生活の人生に追いやり、医療資源を圧迫し、少子超高齢社会を不安と怯えの中にしか描けない。
八森さんは、この団地の人々の中に分け入るようにして感じ取ったことがあった。
「確かにこの団地の高齢化は進んでいる。でも、その暮らしぶりを見ていくと、みんなどこかで支え合っている。それは実に自然で、誰かが誰かを、と言うことではなく分かち合うような支え合いで、そのことがそれぞれの暮らしを成り立たせているのです。
実際、具合が悪くなった高齢者を同じ棟の高齢者の友達がこのクリニックに連れてくることもよくあります。」
私たちはいつも、高齢化率の高さにおののく。
野庭団地は出来てから50年が経ち、その高齢化率は、2015年の国勢調査ですでに43.5%だから、現在はさらに進んでいるに違いない。
しかし八森さんは、その高齢化率の高さを直ちに問題視しない。地域を見つめて、ここには互いに支え合う「地域の力」が根付いていると見出し、そこから自身の在宅診療の実践を組み立てている。
それは八森さんのこれまでのへき地医療の経験からきている。へき地とは確かに過疎高齢の地ではあるが、しかし、そこに暮らす人々はつながることを地域の力としていたのである。
その意味では、高齢化率40%を超える野庭団地は過疎地と同じ高齢社会ではあるが、しかし、団地の人口密度は極めて高い。それはそのまま地域力の基盤である。
訪問診療を通して人々の暮らしと医療とがつながることで、地域の力は生まれていく。医療はその核として、相互に誰もをつなげる力を備えている。
「つながる医療」は病を治し、地域を起こす。そのように八森淳さんは考えたのである。
それはこれまでの医療の組み替えである。医療と患者の関係を従来のパターナリズムからフラットに組み直し、そこに、同じ地域の住民であることから立ち上げる訪問診療を中心としたクリニックを開業した。
地域医療とは、あるいはプライマリーケアとしての総合診療とは、そこで暮らす人々と共に家族や暮らしの背景、さらには地域全体を診ることであるとしたら、ひとつのクリニックの存在が、その地域力を育て、同時にそのクリニックもまた、地域の人々から育ててもらうという協働の関係性を持つ。とりわけ、都市部での医療の新しい社会システムであろう。
講演会は団地の集会所で昼過ぎから始まった。
受付のクリニックのスタッフによれば、当日は申し込み人数よりだいぶ多くの人がやってきたのだと言う。それはどうやら、互いに誘い合ったり、来る途中で会った人に声かけて一緒にきた人々でどんどん増えていったらしい。
いいなあ。仲間なのである。仲間の講演会なのである。このことだけで、このクリニックがこの団地という地域でどのように位置づけされているのかは明確である。
講演会場は小ぶりということもあり満員だった。誰もが団地の住民で、このクリニックの利用者や地域のNPOなどで関わる人々である。なにか賑やかなごやかで、普通、医療講演会というとどこかいかめしく、壇上のセンセの講話にかしこまっている聴衆の風景が多いのだが、ここは全く違う。これで聴衆がお弁当でも広げれば、ほとんどどこかのヘルスセンターの催しである。
この親和性に満ちた関係性は作ろうとしてできるものではない。相互の関係性に生まれたのである。
講演が始まると、わたしはさらに新鮮なおどろきを感じることになる。
八森さんは自身の在宅診療を、実際のケースを挙げながら語る。それは医療の取り組みとしてではなく、それぞれの病に向き合った本人や家族の「物語」を語るのである。
すると、会場のあちこちから、「えー」「なんで」とか、「うわー」「まあ」といったまことに素直な反応が声となってあがり、その度にしんみりとなったり喜びの笑顔になったりする。
医療は、本来こうして語られるものかもしれない。物語の共有はそのまま「自分ごと」のそれぞれの意思表明の声となったのだ。
俯瞰すれば、この横浜でのクリニックの実践は、本来の地域包括ケアの中の医療の姿である。
しかし、厚労省が示す地域包括ケアの、あの図柄から解き起こした地域医療ではない。住民と共に協働して地べたから創り上げた独自の医療システムである。
実は私は先日の小松市での講演会で、厚労省の医務技官で元医政局長の迫井正深さんの「2040年を見据えた地域医療構想ー社会システムとしての医療・福祉」の講演に接した。
この講演は興味深い。それによると、これまではよく2025年問題と言われてきたが、これからは2040年が焦点化する。
2040年とは、人口構造の急速な変化で、この国は超高齢化と共に人口の急激な減少が起こるフェイズに突入する。その時どうなるか。
報告によれば、それは医療需要の変化を引き起こし、外来患者は2025年にピークを迎えるのに対し、代わって、今度は在宅患者が2040年以降にピークを迎え、65歳以上の訪問診療の利用者は患者の90%以上となると推計されている。(2023/4 日本医学会総会:2040年を見据えた地域医療構想)
つまりは、この横浜の団地の一画での八森さんの「つながる医療」の実践は、この国の近未来を先取りしているのだ。超高齢化だけでなく、少子化による目もくらむような人口減少の時代は、すでに2040年という目前に迫っている。
おそらく、この横浜での地域医療の実践と同じような取り組みは全国各地にあるのに違いない。それぞれの地域特性にあった形の地域医療は、しかしともすれば、メディアにも「素晴らしい取り組み」のトピックとして消費されがちだ。
そうではなく、こうした取り組みがもつ意味を構造化し、どうこれからの地域包括ケアを支える医療構想につなげて行くのかが喫緊の課題だろう。
あえて繰り返すなら、横浜の八森さんの「つながる医療」は、団地に暮らす人々の声に耳傾け、そこから立ち上げた医療の形である。
それは、先般成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」での、当事者の声の反映させることという条項とも響き合い、新たな時代精神とも呼応している。
地域住民は、地域医療の当事者なのである。
私たちの未来を拓く私たちの「先進の医療」は、私たちが創り上げて行く。
|第261回 2023.10.25|