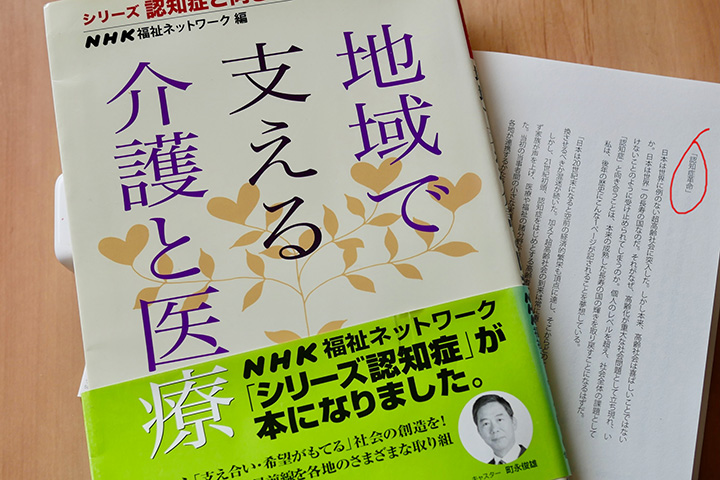▲これは4月12日の横浜の桜。桜もまた咲く場所で表情を変えるようだ。ひっそりと咲いたり、物語るように咲いたりする。ミナトの桜はいつもほがらかだ。
春も桜の季節が過ぎると、何やら春も終わったような気分になる。そうは言っても夏に入れ替わるには、このモンスーンの風土ではこのあとに田畑の実りのためにも雨季を迎えるしかない。はるかな農耕民としての遺伝子の記憶(?)が四季のめぐりを教えてくれる。
今は夕刻過ぎてだいぶ経ち、陽も長くなって書斎から見える児童公園の桜散った木々は名残の夕陽に赤く染まっている。陽射しが後ずさりしつつ、ゆらりと夜が混ざり込む逢魔が刻だ。
あいまいな季節のあいまいな時刻には思考もあいまいに溶け出して、さて、私が「認知症」というテーマに取り組み始めたのはいつ頃だったろうか、とチクチクと考えたりしている。
メディアの世界にいた私が認知症と本格的に出会ったのは、2005年の4月からだった。
その前年の2004年は、痴呆が認知症と呼称変更された年で、その年、京都では国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI)が開かれた。その京都の会場でクリスティーン・ブライデンに会い、そのADIでは認知症当事者の越智俊二さんが、日本で始めて二千人の聴衆を前に講演をした。
そうした機運を受けてNHKでも認知症の大々的なキャンペーンを展開し、私の担当番組でもシリーズで認知症を伝えたのが2005年だった。
それから20年である。年も取るはずだ。だが、改めてこの国の認知症の社会史といったものをたどり直せば、起点をどこに据えるかで違ってくるにしても、2000年以降のうねるような認知症と社会の変化というのは、これまでにない性格のものなのではないか、そんな気がする。どういうことか。
とかく、この国の福祉分野で認知症の変遷を語るときには、例えば2000年の介護保険から始まって、ゴールドプラン、認知症新オレンジプラン、認知症大綱、そして今回の認知症基本法といったふうに制度政策を連ねることで論じられている。たしかに制度的な観点は社会変換の論証としては欠かすことが出来ないだろう。
しかし実は、この社会を突き動かして来たのは、そこに暮らす人々なのである。その人々の心情であり、そこから生まれたささやかな行動の集積なのである。
そうした人々はときに庶民といわれたり生活者とされたりして、いつも政策や福祉の受益者と位置づけられている。そうだろうか。私はここに至る認知症を巡る動向を決定づけたのは、ごく普通の、一般の、わたしたちの隣人といった人々の存在だったのだと思っている。
世上ではよく「失われた30年」と言われてきた。1990年代初頭のバブル崩壊から2020年代にかけての株価や不動産の大暴落の30年の長きに渡る経済停滞期を、そう呼ぶ。
最近この「失われた30年」と言った自己憐憫のような空語がくりかえされたのは、ついこの間、株価がバブル以降の最高値を更新したからである。株価更新で、失われた30年がたちまち取り戻せたかのようなはしゃぎようである。バカいってるんじゃないよ。
誰が30年を失わせたのか。
「失われた30年」と嘆くのは勝手だが、この国の津々浦々で日々のいとなみとなりわいを懸命に生きている人々に、自分たちの暮らしを失っている余裕などないのである。
満員電車に揉まれ、吐き出され、我が子の寝顔だけに会うしかなく、日々の雲の流れと空の輝きの観天望気の漁模様に一喜一憂し、夕方のスーパーの値引きを家計の足しにし、子供をわけなく抱きしめたくなる想いを明日への希望とする。そんな人々の暮らしと想いは、失うわけにはいかないのである。誰に向かって失われた30年とか言っているのか。わかっているのか。名もなく地位なく、しかし命と暮らしに誠実であろうとした人々が、あんた方が勝手に「失われた」としている30年を支えてきたのである。
私には、たえずあたまにおいている漠然とした主題があって、あえていえばそれは、この社会はどうあったらいいのか、といったことである。
それは学生時代に私がわずかに接した社会科学から引き出した形而上のあいまいな物思いといったところだったのが、この「認知症」というテーマに出会って以来、そのことの輪郭が妙にくっきりとしてきている。
メディアにいた頃、「伝える」ということはどうしても世に顕在化した大きくはっきりした声に基づかざるを得ない。ゲストとして迎え入れ「お話を伺う」とするメディア作法ではそうなる。
しかし、10年ほど前にフリーランスになってからは、認知症に関わる医療者や介護専門職、そして認知症の当事者たちと会うようになった。伝える側から聴く立場になったのである。
つまりは聴いてなかったのである。聴くこととは、小さな声や見えない存在を聴くことなのだった。さらには自分の内側の声を聴くことなのである。
この社会は「聴く社会」になっていない。SNSでは異論に耳貸さず自論の正当の鋭さを競っている。その思いで見渡せば、あの認知症基本法は「聴く社会」への門戸を大きく押し広げたのである。どの条文にも背後に「聴くこと」の権利が息づいているようである。
今、各地に認知症と共に生きるまちづくりや認知症カフェ、居場所、本人ミーティングといった取り組みが展開されている。そうした人々に接していると、誰もが生き生きとしている。どの活動も大変なことや負担もあるはずなのだが、健康な楽天性を伴ってそのことが自分を生かしているという直感があるらしい。
この辺りは解説が難しい。それぞれの意味合いの定型や法則ができないことがそのまま強みになっている。人々の取り組みは際限ないほどに多様な思いと実践で成り立っている。
もちろん、こうした地域が完璧で、差別や偏見もないお花畑というつもりはない。むしろ、そうした偏見といったことを互いのつらさや困難に還元し、ちがいを駆動力として地域のリカバリー、回復力につなげていく。
地域の人々は、例えば「共生社会とは」という高みから語ることはない。互いの暮らしの感覚から創り上げる。
それは「こうあったほうがいいよね」「こうしたらどうだろう」という自分たちの互酬の確認であり、それが自分たちのくらしの共生の風景となる。
社会変化の歴史は、常に言論権力の側で描かれる。
しかし、社会の確かな変化は生活者の暮らしの日々から生み出した発信力がもたらす。これまでそれは、例えば「庶民列伝」といった郷土史の中の口伝のようにして限定的に伝えられてきた。
歴史家であり思想家の色川大吉氏は、草莽の民こそが歴史の主体者であるとして「民衆史」を提唱、あの明治期の民による「五日市憲法草案」の発見につなげた。
その著「民衆史 その100年」には、「歴史に埋もれた人間たちを掘り起こし、すぐれた民衆群像の資質と高い倫理性への誇りをとり戻す」と宣言している。
間違いなく、「失われた30年」と入れ替わるようにしてこの20年、認知症当事者とともに歩み出したのは民衆である。市井のいわゆる「普通」の人々だった。
「経済」から「人間」へ。それは政治次元では成し得なかった、民衆という新たな市民性が大変革のうねりを湧き起こしたといっていい。
後世の歴史の1ページには、2000年初頭からの生活者が呼び起こしたこの一連の社会変革を、「認知症革命」と記されるかもしれない。
|第277回 2024.4.19|