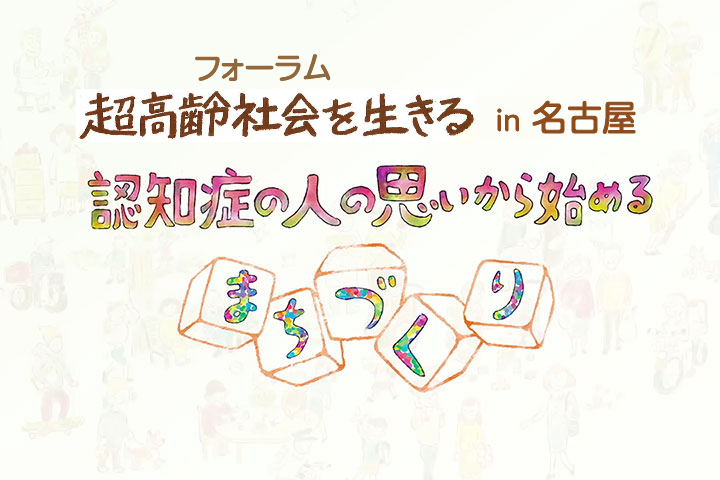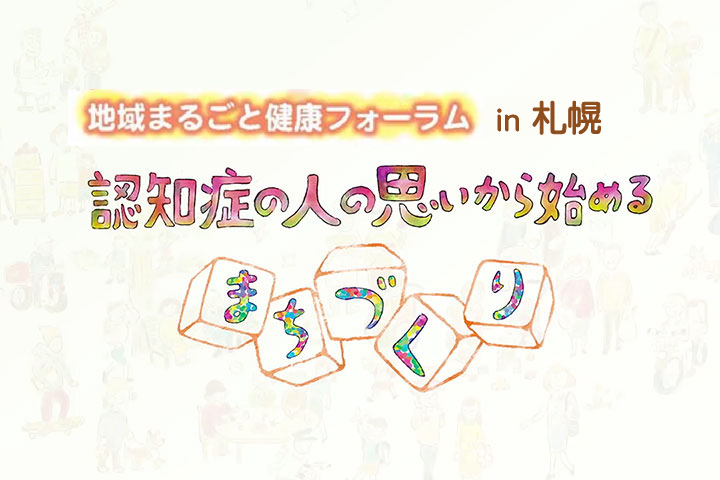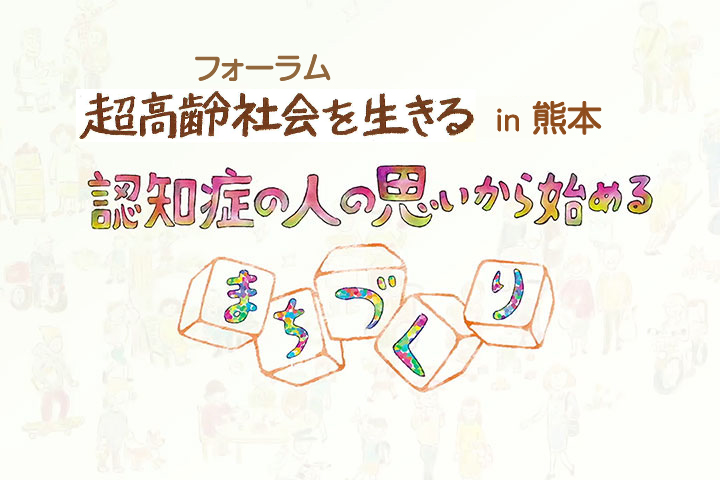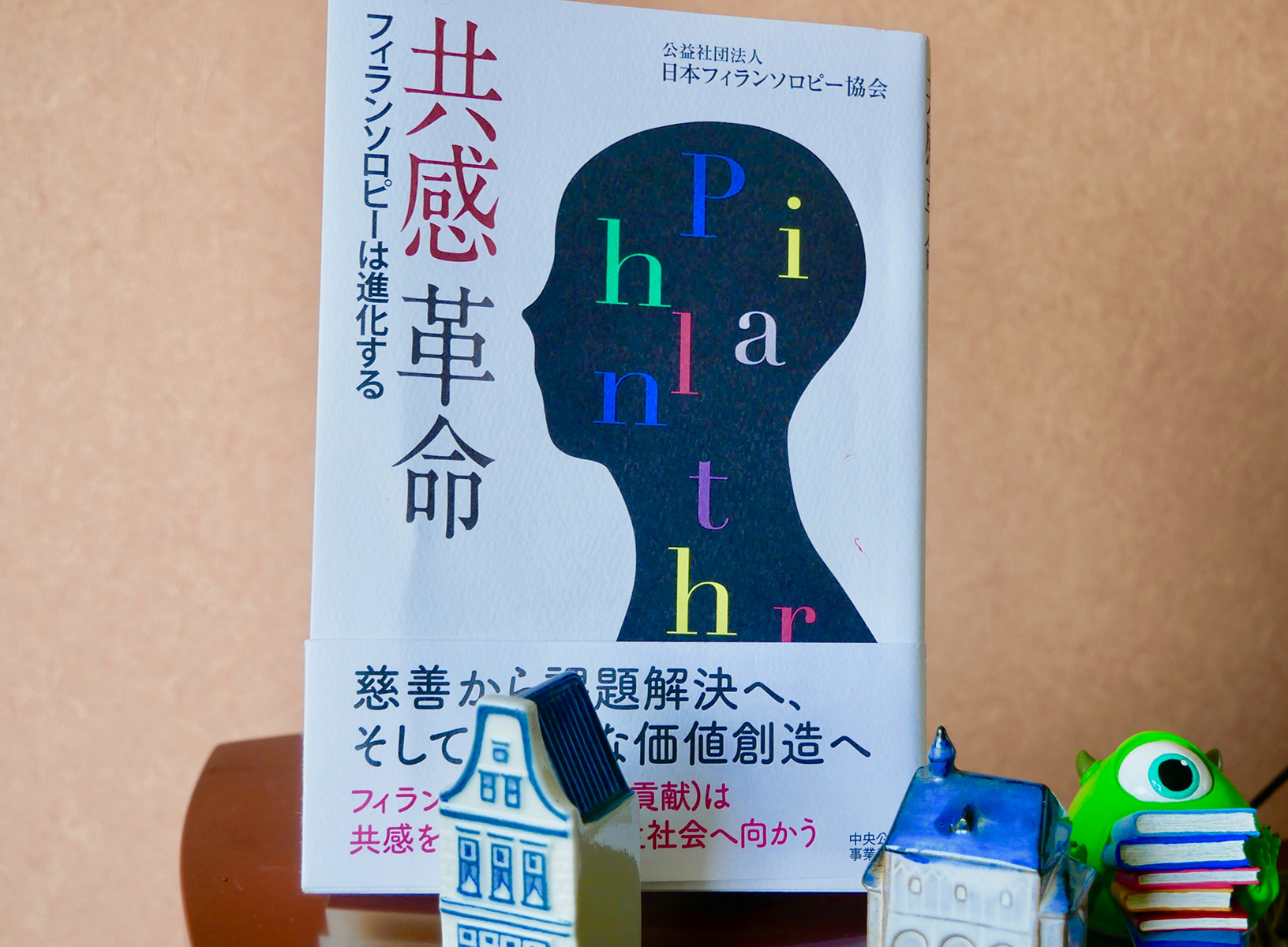
▲コロナの時代は情報の混迷がもたらしたという側面もある。だとしたら、この惑星で、現生人類はいかにしてこの社会の原型を造ったのか。そこには「共感する力」があったという。刺激的で示唆に富む論考である。暑気払いにどうぞ。
二回のワクチン接種が終わって二週間も過ぎた頃、すっかり足の遠のいていた行きつけの街のレストランに夫婦で行ってみた。普段は予約を入れないと席が取れない場合が多いのに、ランチタイムということもあったのか、すんなり席につく。
馴染みのウエイターがオーダーを取りに来て、「大変だね」「なんとかやってます」とか、言葉を交わす。そのうち入れ替わり立ち替わりウエイターや厨房からシェフも顔を見せ、あれこれと世間話。
シェフのおすすめランチに、その頃は午後7時までのアルコール提供もあったから、せっかくなので夫婦でワインも楽しんで、以前通りのどうということもないひととき。
「またどうぞ」、そんな声に見送られて店を出ると、何か元気になった。お腹が満たされた以上に、何かが満たされた。
ささやかな日常が戻ることが、この社会の回復につながるのかもしれない。
店の隅からこちらに気づき、そこから笑顔いっぱいになってそそくさとテーブルまでやってくる年若いウエイターの真情に、夫婦ともども何かとてつもなく嬉しくなる。こちらはそんなに喜ばれるほどの上客ではないのに。
日本フィランソロピー協会がこの3月に出版した「共感革命」によると、この社会を形づくるのは「共感する力」なのだという。共感は信頼を育み、それが共同体をつなぎ、この社会の基盤となっているという。
「共感革命」と銘打つこの書のユニークなところは、「共感」を現時点の社会課題のソリューションへの「お役立ち機能」とはとらえていないことだ。そうではなく、この書では、生命論や生物進化、経済、建築、ロボット分野などのフロントランナーが、この社会の広々とした歴史の時間軸を行き来させながら、社会創造としての「共感」を論じている。
だから、この本の多彩な論者たちのアンソロジーは、これまでとは全く異なった視点から共感を語る。それは人間の、ほとんど生命力と同義のようにして共感力を再定義しているのである。それは私たちが忘れてしまったこの惑星の生命の一員としての感覚といってもいい。
例えば、40年にわたってアフリカでのゴリラ学の第一人者であり、霊長類学者、人類学者、京都大学総長だった山極寿一氏は、現生人類の成り立ちといった地点から、共感への考察を立ち上げている。
ついでに言えば、以前読んだ別の山極氏の論によれば、人間とオランウータン、チンパンジー、ゴリラはヒト科の仲間なのだが、サルとゴリラの違いの方が、ゴリラと人間の違いより大きい。つまり、ゴリラはヒトの仲間(ヒト科)であってサルの仲間ではないのだという。ゴリラは、我らが仲間なのである。
山極氏の考察は、人間から今の社会環境と現実をいったんすべて振り落とし、ゴリラなどと共に生物としてのヒト科としての人間からたどり直すようで、スカッと視界が開ける新鮮な説得力を持つ。
山極氏によれば、チンパンジーもゴリラも集団を維持するにはまず身体的つながりを不可欠とする。つねに仲間の姿や気配がわかる距離にいて繋がりが確認できることが必要で、そこから離れてしまうと、関係が途切れてしまう。群れからはぐれることは、命の危機に直結する。
ところが、人間は数日からときには数カ月集団を離れても、また元の集団に戻れる。それはその人の話をしたり、その人を示す茶碗が、家族といった集団的空間にあったりすることで、その人とのつながりは途切れることなく維持できるのだという。
なぜ、人間は身体的つながりが途切れても、集団を維持できたのか。そこに共感力がある。
生物の進化の過程で現生人類は、やがて熱帯雨林を出て、サバンナで二足歩行で暮らすようになった。そのことは食べ物を運ぶことと仲間と共有することを可能にし、それは互いの共感力を育むことになり、そこに家族とそれを包み込む共同体が生まれたのである。
そのことを山極氏は、「人間は、身体のつながりを超える「共感力」というコミュニケーション能力を育て、他人とのつながりを拡張し、仲間の事情や気持ちを理解して問題を解決することができるようになったからです。そこが人間と他の霊長類との大きな違いです」と述べている。
共感とは、私たちの進化の過程で獲得され、そして現在の私たちの社会を成り立たせたのだ。
しかし一方で、現在私たちの想起する「共感」は随分と狭義でやせほそっている。
ネットの世界での共感は、仲間内だけに行き交い、「いいね」ボタンだけで交わされる記号でしかなく、自身の価値観による共感から外れた人は排除されていく。共感のただ賑やかなだけの交換は、どこか、自分の不安をかき消そうとする共感の擬態でしかない。
さらにこのコロナの時代で、人々のくらしは三密の回避に分断され、身体的なつながりもなく、それぞれ互いを感染リスクと見る中で、共感する力がかき消えた。
この本に収められた各界の論者の中でもユニークな研究者である中村桂子氏は、ゲノム研究を通し38億年の生命の歴史をたどり、ヒトを自然の一部と見る生命論的世界観を提唱している。
中村桂子氏の生命論的世界観とは、例えば、この地球上には38億年前に共通の祖先細胞が生まれていて、そこから派生したあらゆる生命がこの惑星に暮らしている。では、この地球の生命の歴史の中で人間はどこにいるのか。
私たちは生きものたちの上に人間がいると思ってはいないだろうか、それは人間のおごりではないかと、そのように語り始める人である。
近年の生物学では、「高等生物」とか「下等生物」といった言い方はしない。生きものも人間も同じ歴史を生き続ける生命体として見れば、コロナの時代の人間の課題も力も鮮やかに見出すことができるのである。
中村桂子氏は、コロナの日々にとても懸念することがあるという。
そのことを、本書ではこう語っている。
「生き物の世界には ”違い”がありますが、”格差”はあり得ないのです。ところが人間の世界を見ると、ひどい格差社会になってしまった。今回のように、何か大きな危機が起こると、弱い人たちのところにしわ寄せが行きやすい。それを見ると、人間は本当に生き物らしさを失っていると思います」
私たちは「生き物らしさ」を失っている。
中村氏のこの指摘は、「人間らしさ」を失っているというよりはるかに根源的な懐疑である。私たちは、「人間らしさ」というときさまざまな自己装飾を施し、持論の正当化に使いがちである。
この本の論者の一人である経済学者で大阪大学教授の堂目卓生氏は、共感を成り立たせるためには「あなたも私も人間だというところから始めるのがいい」と語っている。
これを原点とするなら、あるいは「あなたも私も生き物だ」と言い換えてもいいのかもしれない。生き物には違いはあっても、格差はないとする原点。
この書は日本フィランソロピー協会が30周年を記念して出版したものだ。
フィランソロピーとは、企業の社会貢献とされているが、前書きを記した高橋陽子フィランソロピー協会理事長によれば、そのもともとはギリシャ語のフィリア(愛)とアンソロパス(人類)の合成語で、博愛、人類愛を語源とするという。
往々にして、私たちは「共感」を思いやりや心配りといった言葉の類義語のように解釈してしまいがちだ。
しかし、この本の中に描かれる共感する力は、生命の進化の中で生まれ、そして今日の博愛や人類愛といった普遍の価値にまでたどり着く、そうした壮大な論考の中に展開している。
ここでの「共感力」は、この新型コロナウイルスの事態で縮こまった私たちの暮らしや考えを、はるばるとその誕生地点にまで立ち戻って、今一度取り戻す力となるだろう。
地域活動に関わるひとりの生活者が、この事態の中、「あの人はどうしているだろう」と夕空を眺めながら、はるかに離れたある人を想うとき、そこには生命あるものとしての、かけがえのない共感する力が満ちているはずである。
|第183回 2021.7.27|