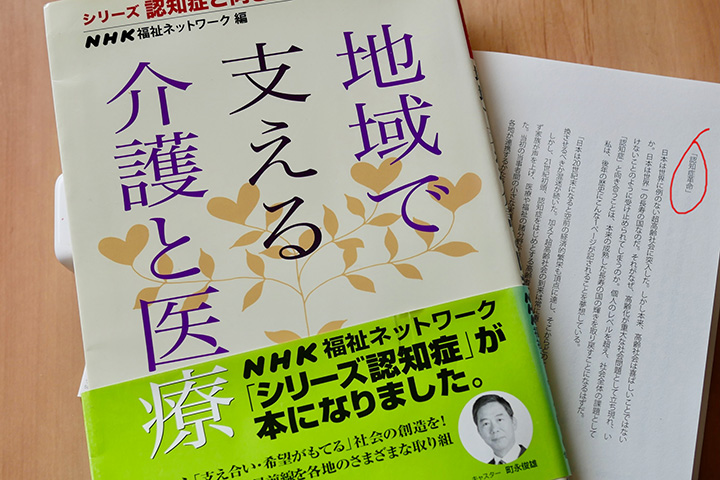▲NHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」の収録スタジオにて。これは3年ほど前、丹野智文さんとの放送。中央にディレクターであり、聴き手の佐治真規子さん。カフェのオーナーである。
深夜、日付が変わる頃に開店する小さな認知症カフェがある。
夜も更けた頃、女性オーナーがひとりで切り盛りするそのカフェに、ゲストがふらりとやってくる。認知症カフェである以上、認知症に関わる多彩な人が訪れる。認知症の当事者も来れば、医療や地域福祉に関わる人もいて、なぜか私も迷い込んで、あれこれを語ったことがある。
その認知症カフェが開店するのは、実はNHKのラジオ深夜便である。
ラジオ深夜便の放送に、認知症カフェと名付けられたコーナーがあるのをごぞんじだろうか。(ついでに言っておくが、深夜に開店すると言ってもそれは放送時間のことで、基本、事前のスタジオ収録だからね、出演者が深夜に渋谷の放送センターをウロウロするわけではない)
さて、その認知症カフェのコーナーがあるNHKのラジオ深夜便は、もう30年以上も続く長寿番組である。まずは、そのラジオ深夜便の成り立ちから語り始めるとしよう。
それ以前のNHKの深夜は、放送休止時間帯だった。しかし、これだと深夜に地震など自然災害が突発した時に、全国ネットワークの膨大な放送設備のいわゆる「火起こし」と言われる電源投入や宿直のアナウンサーがスタジオに飛び込むまでにどうしても時間がかかる。一刻を争う地震災害などの初期対応に遅れが出れば、これは公共放送としては責務と使命が問われるところだろう。
となれば、いっそ深夜帯にも放送を続けていれば即時対応が可能になる、とまあ、そんな思惑もあって始まったのが「ラジオ深夜便」だった。
だから最初は主に深夜にふさわしい静かな曲や懐かしい歌などを中心に放送していた。
ま、ここだけの話だが、即時対応のためという意味合いもあったので、最初はとにかく音楽を流しておこうというところだったのだろう。たぶん。
ところがこれが好評を呼んだ。
この国の超高齢社会の夜は、寂しさの中に更けてゆく。昼には何くれとなく過ごしていた人々も、夜の底に沈むような深夜、眠れないままに天井を見上げているお年寄りがそっと耳を傾けていたのである。
お年寄りは眠りが浅い。ふと、無音の闇に目覚めた時の胸締め付ける寂寥の想いが、枕元のラジオから流れる音楽と、それを紹介するアナウンサーの声があることで、どれだけ癒されたか。
思わぬことに、やがて「ラジオ深夜便」に宛てて、お年寄りからのお便りが届くようになった。
そこに届いたのは、音楽もさることながら「人の声」が届くことの安心であった。
「深夜便」を聴くお年寄りの多くは、枕元にラジオをほとんどつけっぱなしにして眠りにつく。実際、のちには、ラジオ深夜便を聴く高齢者のために、見やすい目盛りと大きなダイヤルのラジオが各メーカーから出されたほどで、実は私も実家のオフクロに買ってあげたことがある。
ああ、声が聞こえる。降り積もる雪のように深まる夜のどこかに人がいて、私に語りかけている。とりわけ、一人暮らしのお年寄りは、目覚めたきれぎれにラジオから人の声が聞こえるだけでもう夜は怖くなくなり、再びまどろみの中に戻ることができると感謝を綴ってきた。
そのような声が次々に届き、やがて「ラジオ深夜便」は、寄せられたお便りを紹介しながら、人生や心を語る豊かな物語に満ちた深夜の解放区となったのである。
「ラジオ深夜便」が定着するにつれ、実は聴いている人はお年寄りだけではなかったことも見えてきた。
深夜に働いている人々、そして、病室でひっそりとイヤホンで聴いている患者。入院治療が長引く中、深夜の静まり返った病室では、昼に芽生えた希望を押し退けて不安が次々と頭をもたげる。そんな時、イヤホンからの「こころの時代」のコーナーに、自分のこころを見つめ直す。
それだけではない。ひきこもりの若者が聴いていた。本人がお便りを寄せることは少なく、家族がそのことを知らせてくれたりした。
長距離トラックの運転手から聴いているとの手紙もあった。寄せられたお年寄りのお便りに、離れて暮らしている老いた母を思い出して、必死に涙こらえてはるかな深夜の高速道路を走り続けた、と。
私たちのこの少子超高齢社会を考えるとき、いつも課題として捉える。確かに避けることができない宿命的な課題である。
しかし、このラジオ深夜便が浮き上がらせたのは、課題としての超高齢社会ではない。地域の隅々の小さな声や想い、発せられなかった暮らしの喜びや楽しさを掬い上げたのである。
生産と効率で轟音上げて突き進んだ昼の世界が終わって、静かな夜の帷が降りて誰もが眠りにつく頃になって初めて、小さきものの小さな声が、夜に輝く星々の光のようにして、津々浦々に撒かれていった。
昼日中、行き交う雑踏の中にあっても見上げれば、そこに星はあるはずだ。昼の空には見えないだけでそこに存在していた星々が、夜のしじまにその輝きを取り戻す。深夜便は、それまで誰も気づかなかった星々を照らし出す、もう一つのささやかな月となったのである。
マスメディアがこれまで大きな声の中に取りこぼしてきた小さな声、深い声が、ここでは時につぶやかれ、時に生き生きと、時にためらいがちに語られ、おだやかに行き交っていく。
誰もがひとりではなく、誰もが小さな声を持ち寄り、深夜にそうした声々がつながっていく。ラジオ深夜便は、「暮らしの当事者発信」を生み出していったのである。
そしていまや、毎晩数十万人が聴いているという「ラジオ深夜便」の一角に「認知症カフェ」が開店している。私はそれを限りなく嬉しく思う。
夜の街角に小さな「認知症カフェ」があって、そこからオレンジ色の室内の灯りが漏れている。あるいは、眠りについた海辺の街の小さな岬の灯台の明かり。私にはそんなイメージが思い浮かぶ。
深夜便のコーナーとしての「認知症カフェ」は2017年に始まっている。このカフェのオーナー、つまり番組の担当者は、NHKラジオセンターの佐治真規子ディレクターだ。
私も何回かカフェの客というか、つまり、出演したことがあるが、いつも、「じゃ、始めましょうか」と、自然にいつの間にか語り合っているという空気感がとてもいい。
それは佐治ディレクターの基本的なスタンスにある。自身は、これまでもさまざまな放送の仕事をしている中で、「認知症」の言葉に出会ったと言う。当時の自分を探ればやはり「認知症は怖い病気」ととらえていたところもあることにも気づき、そこから当事者をはじめとしてさまざまな人々に話を聞いていく。目線低くく、この社会総体の認知症観を自分に引き受けながら、さまざまな人々の話を聴き続けてきたのである。
言い換えれば、彼女と「認知症」との出会いが起点なのだ。そこから、認知症と共に、自分がどこまで変われるのか、変わらなければならない自分と社会を向こうに目指しながら、認知症カフェは日付が変わる前のひと時を、和やかに、しかし、何か大切なものを探り当てるようにして全国の暮らしの当事者と時間を共有していく。
巨大メディアの中のまことに小さな認知症カフェが、広々とこの社会に拓かれている。
私は、佐治ディレクターに提案したことがある。
いつか、「今宵はとことん認知症」というタイトルで、一晩そっくり認知症をテーマに語り合う深夜便を作って欲しい、と。
そうすると、きっと認知症を語ることは、認知症だけを語ることではなくて、それぞれの人生やふるさと、家族、この社会、自分の想いを語ることになる。つらく厳しい話と楽しい話が混ざり合って、それは私たちの共に生きる社会だと、そんなことは一言も言わなくても、聴く人の心に染み込むような時間になるに違いない。
あ、それから、アンカーは丹野智文さんに頼むといいよ。
(ラジオ深夜便・認知症カフェ:放送予定は原則、毎月第2・第3火曜23時台)
|第222回 2022.9.15|