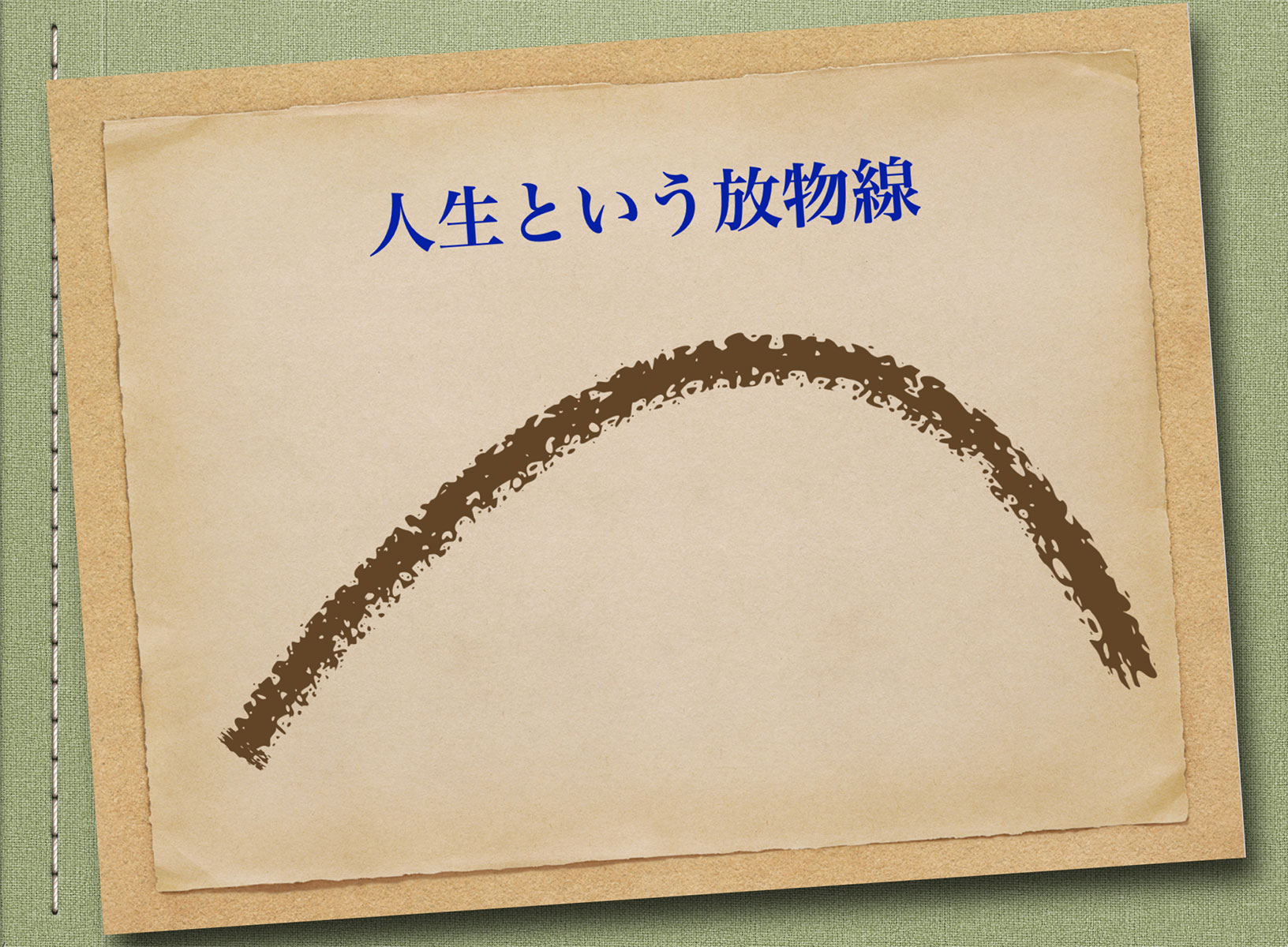
▲多くの人は人生曲線のピークを働き盛りの時期に描くが、あるいはそのピークを高齢期と呼ばれる時期に描ける社会がいいのかもしれない。我が春はこれからやってくる。
コロナの日々もどうやらひと区切りの気分だ。こんな時こそ自分自身を振り返りたい。しかも俯瞰的に。いや、そんなに難しいことではない。画用紙に一気にぐいっと我が人生の曲線を描いてみる。
改めて眺めれば、自分のいのちの連続に様々な思いが浮かび上がる。春の盛りを前に、こんなひと時を持つのもいいのかもしれない。
さて、人生は放物線だ。
放物線とは、空高くボールを放り投げた時の軌跡だ。ボールは美しい曲線を描いて飛んでいき、そして地上に落ちる。この放物の曲線が人生である。
この世に生まれいずる誰もが、それぞれがひとつのボールを高々とこの世界に投げ上げる。それが誕生である。
おさなごよ。はいはいから伝え歩き。やがて歩き始めると少年少女から若者へとまっすぐに空を駆け上がる。チチハハは額に手をかざして我が子の飛翔をまぶしげに見あげ、やがてその子は配偶者と出会い家族を造る人もいて、家族や仲間に囲まれるようにして蒼穹を突き進む。
幾たびかの暗雲、嵐にも、投げ上げられた推力は保たれて、彼らの放物線は巡航高度を進んでいく。
が、しかし。
その放物線も、やがては緩やかに落下に転じる。老いが確かに、そして静かに空気抵抗を与え、なだらかに曲線は下降線となっていく。そして、夕闇に尾を引く彗星の光芒のようにして、やがて、終着の地に落ちる。友よ、これが人生だ。
この放物線が試練を受けるときがある。
下降局面のどこかで、すとんと突然落下させるものがある。 スピードメーターの針が一挙にゼロにぶれるようにして推力は失われ、その曲線は鋭角に落ち込む。それは何か。
そのひとつに「認知症」がある。
認知症の環境はこの10年余りで大きく変わった。かつてはなってしまったら「もう治らない」「何もわからなくなる、できなくなる」と言われて来た。それが新たな抗認知症薬の登場などで医療の手だても確立している。介護の側でも「心は生きている」と新たなケアの潮流が定着した。
そして今、「認知症とともに生きる社会」は、この少子超高齢社会の具体的な未来図として、全国各地の共生のまちづくりに注ぎ込まれている。そうしたことのすべて、その根本にあるのは、このいわば「人生は放物線」といった人間存在を俯瞰するようにして、誰もが確認することにある。
かつて医療はその曲線の突然の落ち込みをなんとか復元することに躍起になった。別の言い方をすれば、疾患・疾病を「治療」することに躍起になったということである。
「ベストを尽くす」医療とは、その落ち込んでしまった曲線を当然、元に戻そうとする。が、先端医療のある側面は、病理をたたくことを優先するあまり、人生曲線をきわめて不自然なかたちにはね上げたり、折り曲げたりするのだ。なだらかな下降は、人為的に押し上げられ、本来の曲線は集中治療室の心電図波形の中に押し込められてしまう。
かつて言われたいわゆる「スパゲティ症候群」という過剰な延命医療とは、この美しい人生の曲線の尊厳を「ベストを尽くす」という正義のもとに収奪しているのだ。
医療の側の「ベストを尽くす」ということと、私たち生活者(患者家族)の側の「ベストを尽くす」医療にはどこかで決定的な食い違いがないだろうか。
認知症の医療やケアは、この人生の放物線の曲線に寄り添う。無理にねじ曲げない。
なだらかに下降していく人生の曲線は、喪失の過程である。私たちはどのようにがんばろうと力もうと、生きていく中で否応なく何かを失っていく。かけがえのないものを失うことを受け入れていくしかない。
幼子を胸にかき抱く親は、普遍のありようとして、我が子より先にこの世界を退場する。子は人生のどこかで親の喪失に出会う。その際限ない繰り返しが私たちの世界の秩序なのだ。
私たちはそうした自身の「喪失」を受け入れられるだろうか。
これまでの私たちはどこまでも驀進する人生を善としてきたところがある。生産性を評価基準とする経済原理がそれを後押しして、私たちはイカロスとなって、ひたすら上昇を目指し、その果てに、太陽神の灼熱に身を焦がし墜落してしまうという神話的寓意をなぞってきたのではないか。それはどう考えても不自然なことだと、私は思う。
人生はどこからか、下降する。終着の地に向かって。
認知症の医療やケアは、その「喪失」を受け入れるところから始まった。喪失を受け入れた上で、そこを埋め合わせる道筋を探るようにして、鋭角に落ち込んだその人の放物線を本来の曲線にそっと押しあげ戻していく。これが認知症ケアであり「自分らしくを支える医療」といわれる当事者に依拠する統合された「福祉の力」であり、「ともに生きる力」なのである。
これは今までにない形の労働形態だ。サービス提供の見返りとしては報酬が設定されてはいるが、ここには対価としての改善、生産、成果というものが設定されているわけではない。医療の目的が治療、つまり「治す」ことであるなら、そこから逸脱した行為とも言える。ケアの立場からすれば「老い」とは今日の状態が一番良くて、徐々に放物線は下降していくわけだから、そこに向き合うということは、生産的な成果は期待できない。認知症ケアとは、ある種、形而上学的な実践である。「人間」に向き合う労働なのである。
そもそも、認知症の医療は「治すことができない」という「医療の敗北」から頭もたげた。
「治せない」スティグマは、当初から厳しい自己検証の道のりを歩むしかなく、医療の存在地点をいわば、臓器、疾患から人と心と暮らしに視点転換していく。
そうした認知症医療やケアが大きく転換したのは、当事者の声に耳傾けたことがある。治す医療から診断後支援や社会的処方といった支える医療を提示し、そこに地域ケアが結びつき、それはそのまま「認知症とともに生きる誰もの人生」を描いていく。
私は、最近とみに実感するのだが、認知症を突き詰めるように考えると、この社会のありようといったものがくっきりと見えてくるようである。
だから「喪失」を、世に出回る人生エッセイの中の「老いの覚悟」といった老年期特有のものとして相対的に縮小させることには反対である。
人生という放物線には、認知症を超えて、人生の途上でのつらさや困難に接する基本動作のすべてが込められているように思う。今高揚期にある人、放物線のピークに達している人に水をかけるような思いはさらさらない。どうぞ、自身の人生を謳歌していただきたい。ただ、そうした人にこそ、「喪失」に対する想像力を持ってほしい。
大きさ、強さ、早さを求めて突き進む人にこそ、小さきもの、弱きもの、ゆっくりとした歩みを受け入れる「力」を持ってほしい。
やがて失うものがある。かけがえのないものを振り落とすように生きていかなければならないことは、やはり哀しく、切ない。
だからこそ、悲哀をかいくぐった「靭さ(つよさ)」が生まれる。
認知症の当事者の、喪失を受け入れていく中で切り出される「残されたもの」、それを「靭さ」と言っていいのだと、私は思う。
口当たりの良い表面的な支え合い、助け合い、共生の心地よさに留まっているわけにはいかない。
人生は放物線である。
私たちは、誕生から、終着の地までを一本の放物線としてくっきりと描けるか。それがあなた自身の人生という放物線である。





























