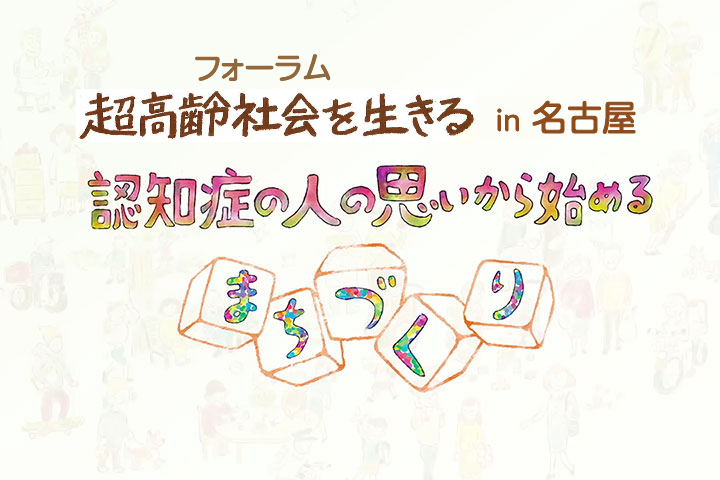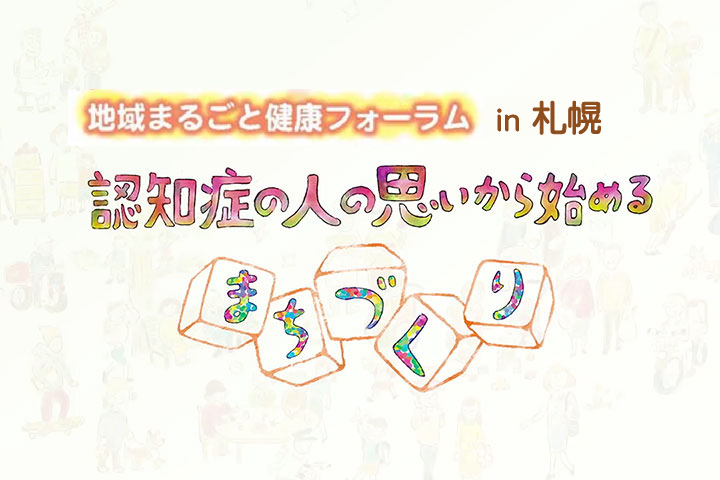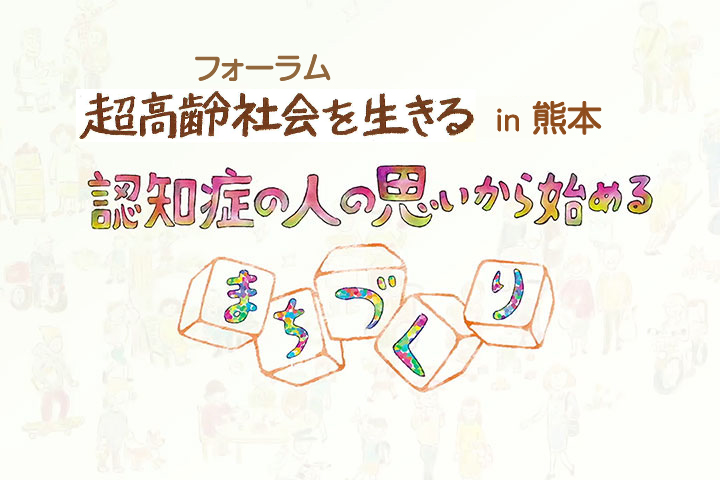▲大阪がんフォーラムの登壇の皆さん。上段左から、福祉ジャーナリスト町永俊雄さん。俳優の秋野暢子さん。大阪国際がんセンター病院長、大植雅之さん。大阪大学医学部、高橋剛さん。NPO「がんノート」代表、岸田徹さん。
がんフォーラムを開くために大阪に行った。
週末の大阪はインバウンドの客もあって大混雑。ホテルのチェックインに長蛇の列で30分ほどかかった。
前日の会場準備を終えたスタッフと夕食を兼ねた打ち合わせ会場に出かけるが、どうも大阪の土地勘が全くない二人だったので、たちまち迷い、交差点のたびにあっちに行ったりこっちに行ったりで、肝心のスマホのルートアプリは電波の状況なのか、矢印がぐるぐると変わる。
とそこに一人の女性が、「お困りのようで」と声をかけてくれた。
どうもウロウロと行ったり来たりしている私たちを見かけて声をかけてくれたようだ。
「大変ね。子供をあっちに待たせといたから、なんでも聞いてや」
まあ、親切な方だった。私たちがあーでもないこーでもないと指差していた道路脇の地図表示を一緒になぞりながら、「こー行ってここ曲がって、ここわかりにくいねん、このコンビニが見えたらその向かいね。あと5分くらい。頑張って」と何度も道筋を確かめるように教えてくれて、それから、子供を待たせてあると言うデパートの方にそそくさと小走りに去っていった。
いやあ、なんとまあ、と二人で感心した。東京モンは、子供を待たせてまでして、これほど親切には教えてくれへんで、と東京モンのふたりは大阪言葉になって感激した。
この感激には続きがあった。
翌朝、ホテルからフォーラム会場に向かう途中で、今度は私一人だったのだがまた迷ったのである。ホテルからもらった地図を片手に建物を見上げたり、振り向いたりしていてよほど途方に暮れた様子だったのだろう。
「どちらに行きますの」
振り向くと、品のよい和装のご年配の女性である。にこやかに声をかけてくれたのだ。
フォーラム会場のホールを告げると、ああ、それはあそこね、と指差した向こうのビルのてっぺんに会場の名前がついていた。どうも道を一筋間違えて行き過ぎていたのだった。
ありがとうございます。お礼を言って向かおうとしたら、どのみち同じ道だからそこまでご一緒しましょ、とのこと。
道すがら、たくさん話してくれた。大阪の古い家柄に生まれて今はお茶の先生をしていて、住んでいるのは大きなビルの最上階で、そこが自分のビルで、大阪の中心地にもたくさんの不動産を持っていてとても値上がりして、今はもう八十を過ぎて、いろいろあったけれど、結局は「自分で生きていかなきゃ、ね」とそのオンナ半生記を括り、会場まで来ると「それではごきげんよう、お元気で」と品よく腰をかがめて去っていった。。
いやいや、大阪はすごいなあ。連日、二人続けて親切の極みに接したのである。
大阪人は、人間が濃い。あの年配の大富裕(たぶん)の女性は、その世俗が濃い人間性に溶け込み調和して、心地よい人柄を練り上げている。
何か朝からとてつもなくいい経験をした気分。大阪の女性が配るのは「飴チャン」だけではない。親切や思いやりもしっかりたくさん配っているのである。
実は、大阪でのがんフォーラムはその「人間」を語り合う場になった。
私たちのフォーラムは一般的な医療フォーラムとは一線を画している。医療フォーラムの多くは、壇上の専門医からの最新の医療情報の一方的な提供を基本とするが、大阪のこのフォーラムは、「がんと生きる」というタイトルにあるようにむしろ患者の側からの視点から構成されている。
今回のサブタイトルが「患者の声と医療の言葉」としたのは、患者と医療者との間にある食い違いに焦点を当てている。食い違いというのは、患者も医療者も実はあまり意識に上らない声といってもいい。
この提起をしたのが、がんの当事者である岸田徹さんで、10年前からNPOの「がんノート」と名付けた取り組みをしている。ユニークな取り組みで、がんを経験した人のその本音を語り合い、それを動画配信して誰もが共有できる。現在、世界最大級のがん経験者のインタビュー番組なのだという。
一般にがん患者の声と言えば、その多くは自分の治療、医療に関わることである。それは現在、医療の側でも注力していて、標準医療などの情報をどう届けるのか、情報は第二の医療と呼ばれるほどに力を入れている。
ただ、岸田さんの「がんノート」で交わされるがんを経験した人の声は違う。それはあえて言えばこれまでがん患者自身も意識せずに心の中にモヤモヤと漂わせていた声である。医療者には言えない、あるいは言わない声である。
たとえば、ある女性は子宮摘出によって子供が産めなくなった。そのことは当然医療者との話し合いでコンセンサスを取り、自身も納得していた。そのつもりだった。
が、その後のがんと生きる中で、どうしても拭いきれない思いが浮き上がる。
子供が産めないということは、恋愛や結婚の支障になるのだろうか。そのことに悩み考え、その女性は岸田さんに、「わたしはなんのために生きているの」とぶちまけるのである。
映像の中で、対談相手の岸田さんはただ、うなずく。ただのうなずきを超えたピアならではの深い共感が交わされる。
岸田さんは語る。ここにあるのは「病の不安」ではない。がんとともに生きる中で個別の自身の存在不安であり、その不安は誰にも言えないことでいつしか重くのしかかっていく。だから、がんノートは、そうしたことを言える場であることが一番の役割で、何かの答えやゴールを目指すものではない。岸田さんはそう語った。
なぜ、がんを経験した人々にこうした自身の存在不安が浮き上がってきたのだろうか。
「それはがん医療の目覚ましい成果がもたらしたものだ」
フォーラム登壇者の医療者、大阪国際がんセンターの病院長の大植雅之さんは、そう指摘する。
がん医療の進歩はがん生存率を飛躍的に高め、今やがんの5年生存率は66.2%で、すでに10年生存率で見ても53%、がんによっては早期発見と対応ではほぼ治ると言っていい。
ところがこの成果によって、がんを経験した人ががんとともに生きる人生も、当然ながら随分と長くなった。
長い人生をがんと生きる、ということは同時に再発などの不安とも長く付き合うことになる。そこからこれまでにない不安や悩みを抱かざるを得なくなる。
私たちが望み、歓迎してきた医療の進歩は、その医療によって新たな不安を生むことになっているとしたら、どう考えればいいのだろう。
ここからフォーラムの語り合いは、時に大きな振幅を見せ、時には医療者と患者の立場の距離を互いに近づけようとしたり、その距離を相互確認したりで、不思議な緊張感の中を進んでいった。
医療者として登壇したもう一人、大阪大学附属病院で患者と向き合う外科医として高橋剛さんは、医療者は、がんと生きる患者の「長い旅路」の伴走者であるとし、人生を共にするような医療の姿を模索しながら、実際のがん患者との9年間の起伏ある旅路を語った。
2年前の食道がんから復帰した俳優の秋野暢子さんは、医者ががん医療のプロであるなら、患者はがんという病のプロなのだとし、互いの対話こそが必要だろうと体験を語る。
医療者とがん患者、互いの立場を保ちながら、その食い違い、ズレといったものを解消させるのではなく、むしろ推進力とし、対話しつつ認識するプロセスが、新たな医療へと進ませる。
医療は、インフォームドコンセントの時代を経て今、患者主体、患者参画を踏まえ医療者と患者との「共同意思決定」を掲げている。医療での共同意思決定とは、「医療の正しさ」ということを患者の側から「正しさとは何か」と問い直すことで成立するともいえる。
それは、がんを疾病として医療の枠だけで捉えるのではなく、「わたしはどう生きるのか」と言った不安や悩みから、「この社会はどうあったらいいのか」と言った次元へのまなざしを医療者と患者の共同意思とすることで、がんとの共生の社会へと止揚させる道筋につながる。
道に迷って途方に暮れる時、行き合った人から「どうかしましたか」と声をかけられ、何か互いに微笑むような思いにかられるのは、そこには立場や年齢や出身地を超えた「人間の言葉」の響きへの交感を覚えるからである。
「共同意思決定」とか「患者主体」といった言葉の硬さや概念臭を、医療者とがん経験者それぞれが「人間の言葉・暮らしの言葉」に置き換えることで、対話が生まれる。
思えば、あのフォーラムの最後には医療者もがん経験者も、自分の立場から離れ「人間の言葉」で語り合っていたようにも思う。