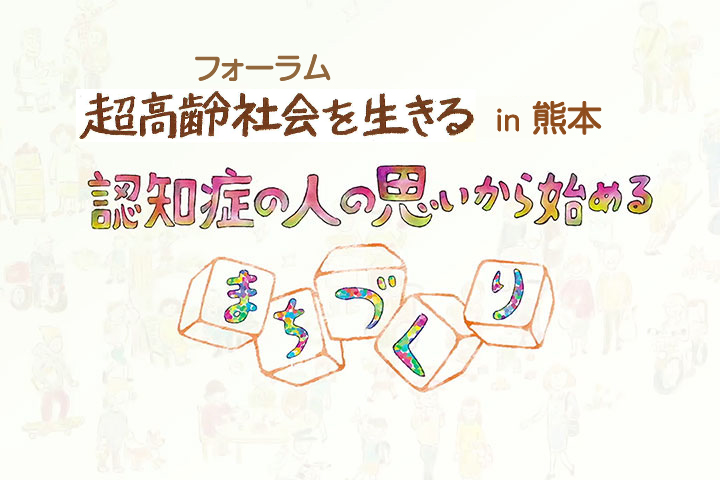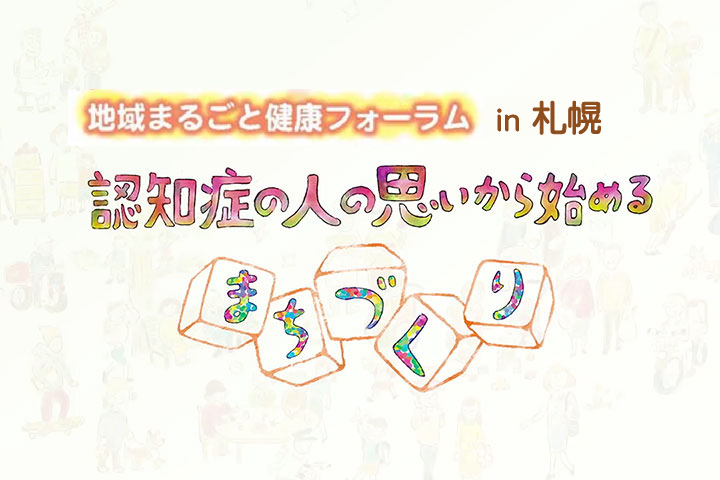▲京都で泊まったホテルの近くに、京都の人々に親しまれている頂法寺、六角堂がある。六角の御堂を回ると、受験生の祈りや願いが愛らしい鳩で奉納されていた。願い叶って、鳩たちが空に羽ばたきますように。
京都でオンラインのがんフォーラムを開いた。
フォーラムのテーマのひとつが、がんの再発だった。
国立がん研究センターが運営する公式サイト、「がん情報サービス」の「転移・再発」の項目を読むと不思議な感銘を覚える。ここにあるのは、がん医療の枠組みを超えて、人が人を語る文体で記されている。書き出しの「がんが再発していますと言われたら」の項は、このように書き出されている。
「がんの再発は、計り知れない衝撃です。治癒を目指してきた患者さんにとって、最初にがんの宣告を受けたとき以上に大きなショックを感じます」
「計り知れない衝撃」。それは、ただひとりのがんの当事者を狙い撃ちする。「どうしてなのか。これは何かの罰なのか」再発を告げられた人は、疾患のつらさを突き抜け、自分の存在を根底から揺り動され、怯え、否定される。再発。計り知れない衝撃。
がん情報サービスの再発の項は、他の疾患としてのがん情報とは明らかに違う語り口で綴られている。担当するがんの専門家たちは、それぞれが話し合い、自分たちも悩みながら一緒になってまとめたものだと断りながら、苦渋をにじませるようにして、こう続けている。
「すべて読んでいただく必要はありません。患者さんにとってはつらいと思われるような内容も含んでいます。自分にとって必要な内容を見つけて読んでください。また、あなたが読み終えたら、あなたをサポートしてくれる家族や友人にも読んでいただきたいと思います。」
この文章は、がん医療が患者の側に立つことの宣言であり、同時にまた、がんという困難を分かち合う切ないやさしさに満ちた究極の共生社会への呼びかけでもある。
京都でのフォーラムでは、ひとりのがんの当事者の映像が流された。その女性は70歳の時、ステージ4の胃がんが見つかり、抗がん剤治療が始まるがそのつらさに生きること自体を諦め、親族の集まりで「おばあさんは来年はいません」と告げたという。しかし、そこにがん医療の進歩が関わる。当時認可されて間もなかった分子標的薬がよく効き、さらに患者に負担の少ない腹腔鏡手術によってみるみる回復していく。
しかし、ようやく自分自身の人生を取り戻した実感を持てた時期を見透かすかのようにして、がんは5年後、再発する。がんは再び肝臓に転移していた。しかし、彼女は現在も新たな分子標的薬での治療を続けながら、自分の運営するケアホームに関わりながら暮らしている。
再発という「計り知れない衝撃」を彼女はどのように受け止め、そこにどんな自分を見出したのだろう。
フォーラムでは、がんに関わる最新の治療情報を伝え、そこから転じて再発した当事者の暮らしと思いにつなげていく。壇上では、この再発のケースをもとに話し合った。
実はこうしたフォーラムでがんを語ることは難しい。最新の医療情報を届けることはできても、再発に向き合うことを語るのは、答えのないそれぞれの人生を語るようなものだ。
がんと闘う人がいる。頑張らないことを選択する人がいる。それ以前に、打ちのめされ何もかも放り出したくなる人もいる。不安の底にひたすら引き摺り込まれる人がいる。
ともすれば、がんになっても明るく元気で過ごす人を、がんと生きるロールモデルのように伝えられることがある。しかし、明るく元気になれなくてもそれは自然の感情であり、人としてあたりまえであることも確かに伝えておかなければならない。
私は、がんの再発を経験した女性の映像を、編集の段階から打ち合わせまで何回か繰り返し見ている。
そこで気づいたシーンがある。その女性のリビングでの日常のシーンだ。冬の日差しが差し込むリビングの窓際に、幾鉢もの草花、プランツが置かれているのがわかる。映像は当然、その手前のがんの女性に焦点が結ばれているから、その向こうの緑の鉢は幾分ぼやけている。が、その分、窓からの逆光にやわらかに映えている。
多分、ありふれた草花の鉢なのだろう。だがその草花たちは、再発したがんと生きるこの女性の人生というものを物語っている。
朝、リビングに行くと、そこに小さな花が咲いている。何気ないいつもの風景、家事の合間に水をやることもあるだろう。花がらを摘むこともあるはずだ。暮らしの中に花と緑がある風景の中、この70半ばの女性は、がんとともに自分の今を生きている。
がんと生きるということは、言葉にするとこぼれ落ちてしまうような日常のシーンの積み重ねなのかもしれない。覚悟や決意、というより、揺れに揺れた自分の気持ちがやがてどこかにその振幅を収めていくような気づきと生き直しのプロセスなのかもしれない。映像の中で見逃してしまいがちな細部に、かけがえのない大切な思いが宿っているようだった。
私はそれを、窓際に並ぶいくつもの草花の鉢に見た思いがする。
がんを語ることは難しい。それはがんの当事者とそうではない人の間に、語らないでいること、あるいは語れないでいることがあるからだ。一番身近で大切な人であるからこそ、言えないことがある。がんの本人の家族は、これ以上本人に負担をかけたくないと聞きたいことを我慢する。大丈夫?と聞きたいけれど、そう聞けない。
本人もまた、大切な家族にこれ以上心配かけたくないから、自分の不安をそのままぶつけることを控えるしかない。互いの思いやりが、互いの空間にぎっしりと立ち込めて、寄り添うことができない。
がん患者が直面する「生」と「死」についてどう語るか。しかし、言うまでもなく「生」と「死」は、がん患者だけのものではない。がんを語る、と言うことは同時にそれぞれ誰もの「生」と「死」を考えることにそのままつながる。
実は当初、制作者側ではこのテーマでどこまで語り合えるか予測がつかなかった。誰もが死ぬとは理屈では自明のことではあっても、がんの当事者にはやはりセンシティブなテーマだ。恐る恐る設定した構成だったところもあった。
フォーラムでは、「抗がん剤のやめ時」をきっかけにしてそれぞれの対話が大きく膨らんだ。それはごく自然に「死ぬこと」と「生きること」の同一へと、和やかに話し合いが重なったのである。
「死んでいく私」を語り、そして「今を生きる私」を、まず切り出すようにして語ったのは、再発がんの当事者だった。その当事者の話から、登壇者それぞれが、それぞれの「死」を見つめ、そして「生」を語ることができた。それはやはり当事者の力だった。がんの当事者は、そうした対話を引き起こす力を持っている。
がんセンターの再発の項目の終章は、「死の経験について」となっている。
その記述は、具体的な医療の知見を丁寧に置きながら、やがて静かな人間肯定へのモノローグとなって、誰もの人生に響かせるようにして、次のように語られている。
「死の経験がどのようなものなのかは誰もわかりません。ただ死は怖いものではないと多くの人が言います。
死はあるひとつの出来事というよりもひとつのプロセスです。
体がゆっくりと「活動を停止」し始めるのです。死の床にある人が、最期の瞬間に経験することは誰も知りません。各自がそれぞれ想像しているのです。苦痛と看護から解放される瞬間であると考えている人もいます。心地よい眠りに入ることだと想像している人もいます。
もしあなたが死を迎えるとき、誰かにそばにいてほしい、こうしてほしいと思うのであれば、そのことをぜひあらかじめ伝えておいてください。
あなたの意識があるかないかにかかわらず、あなたの希望は尊重されながら最後まで見守られ、人として大切にされます。」

▲京都がんフォーラムのパネリストの皆さん。左から町永俊雄。俳優の生稲晃子さん。がんの当事者の梅田史世さんと長女の恵さん。オンライン参加の京大大学院放射線腫瘍学教授、溝脇尚志さん。在宅医の長尾和宏さん。
|第200回 2022.2.3|