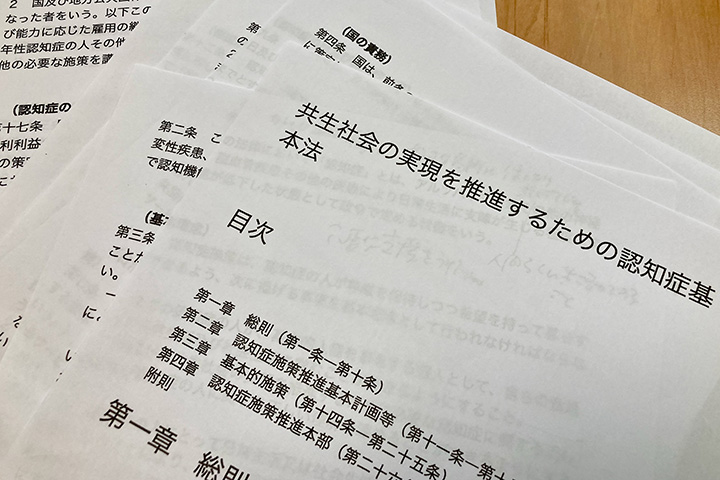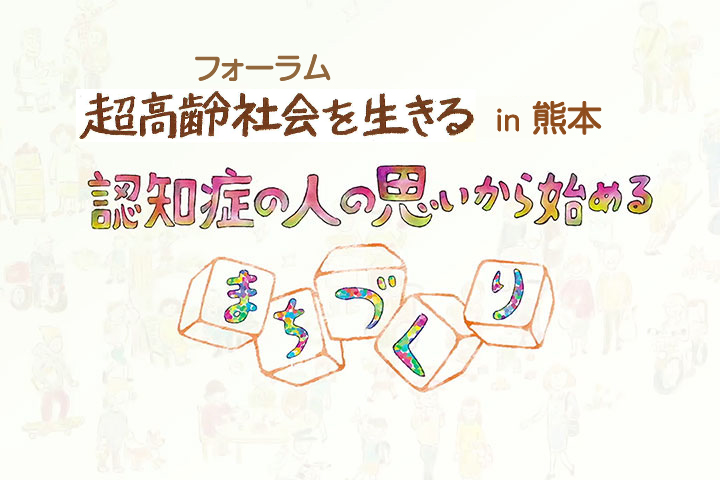▲ 認知症の本人参画を推進するための老健事業の検討委員のメンバー。認知症の取り組みは、地域の小さな自治体や街角でみずみずしく息づいている。そこでは「認知症とともに生きる」が、理念ではなく生活実感で語られる。高齢化率や認知症のデータだけを見るのではなく、地域の施策の取り組みや変化を見つめながら、「本人参画」を考えたい。
お盆前に令和元年の厚労省の老健事業、「認知症本人の意見を生かした認知症施策展開に関する調査研究事業」の検討委員会が開かれた。
このお盆前というのが、ひとつのメタメッセージでもある。
この国の風土で、人が人を想う密度が最も高まり共有されるのが、お盆なのである。精霊を隣に感じ、誰もが死と生のあわいを行き来して、時空間を超え、人を想う。
花火、墓参り、ご先祖、精霊流し、京の五山の送り火。
あの世とこの世と私とあなた、連綿の生命のつながりと社会を考える。それはつまりは、「人間」の根源的な存在を前提にしてこの社会を考えることであり、言い換えれば、霊界、現世、未来と、壮大な想像力の中、時間軸を縦横無尽に走らせた共生の社会、「とも生き」を確認する季節だ。
人が人を想う。果たして、そういう社会になっているのか。
夏の盛り、そんなことを思いながらの検討委員会なのであった。
この老健事業はJDWG(日本認知症本人ワーキンググループ)の受託なので、検討委員には藤田和子代表もいる。委員長は、都健康長寿医療センターの粟田主一氏が継続、認知症介護研究・研修センターの永田久美子氏、認知症の人と家族の会代表の鈴木森夫氏など、いつもの顔ぶれだし、各地からの認知症当事者も行政担当者も検討委員に加わる。
さて、この厚労省の老健事業はどんな役割を持つのか、その意味はしっかりと押さえておいたほうがいいだろう。
CSR(corporate social responsibility)という企業活動の新しい概念がある。
それはいわゆる社会貢献よりも広義で戦略性を持ち、企業は単に自身の利益追及だけでなく、社会全体の責任を負うというものだ。社会が滅亡すれば、企業自体も成り立たないからね。
その具体的な取り組みとして「CSRダイアログ」というのがある。
ややこしい話をして申し訳ない。つまり、企業がその社会的責任を果たすために、何をすべきかあらゆるステークホルダー(関係者)ととことん対話するというものだ。すでに企業体の発想だけでは自己変革は難しいという極めてイノベーティブな取り組みなのである。
今回の老健事業は、まさにこれを担う。
少子超高齢社会の先行きは、この国の仕組みと発想ではどうしようもないところまで追い詰められている。そこで打ち出されたのが、新オレンジプランの「認知症にやさしい社会」というシステム変更への呼びかけだった。それはその後、地域への伝播と実践の中で「認知症とともに生きる」になり、最近ではさらに「認知症とともによりよく生きる」を掲げる取り組みも出ている。
静かで、そして確かな変化だ。共生モデルの成熟の兆しと見てもいいのではないか。もちろん、全体化はしていない。しかし注意深く見れば、この国という老木の梢の先に新芽が吹き出るようにして、地域の小さな自治体に大きな変化が出ている。
それが「認知症とともによりよく生きる」なのである。
地域の自治体は、住民の暮らしの只中で機能する。地域責任において何ができるのか、住民との率直なダイアログ、対話が重ねられ、その声を吸い上げ反映させることで、実は自治体自体が変革する。
今年度の事業計画は「自治体における本人参画の取り組みを加速すること」を目的に上げている。これは、昨年度の「認知症の本人とともに進める認知症施策」をさらに具体的なものにする狙いがある。
では、その「本人参画」をどう考えればいいのか。
「参画」の字句の意味は単に「参加」ではない。「画」とは、画する、と動詞にすればわかるように企画、計画することである。本人が施策の場に参加して企画することが本人参画である。
だから、本人参画と言ったとたんに、それは「認知症の本人は、その地域社会の成員であり、主体者である」ことが成立していなければならない。
そうはいっても、行政という公的なシステムからすれば、納税者全体の福利を視野に収めて機能させるのが使命である以上、いくら認知症施策であってもひとりの認知症の個人の意見を直ちに優先的に反映していいものかどうか、地域の自治体の誠実な担当者なら当然悩むところだ。
どうすればいいか。まずは素直に、普段の窓口のルーティンとしての「ひとりの声に耳を傾ける」ことからはじめたらどうだろう。
日常、行政の担当者は窓口で多くの地域住民の声に接する。
「はいはい、どうしました?」と言った具合に。それが地域の自治体の基本動作で、ここでの声の集積が施策に反映し、制度設計につながるのである。
ところがそこに、「認知症の人の声を聴くこと」といったお達しが来たとたんに、どこか身構える。通常の住民という「個」への、無防備な、それだからこその対等な関係性に小さな亀裂が走り、間違えてはならない対応に向けて、いつものボールペンを握る手に圧力がかかり、「どうしました?」という最初の一声を噛んでしまう。
ここにはすでに「本人参画」が届いていない「お客様扱い」の認知症しかない。
窓口のその担当者が、次に用意するのは、心込めた「それは大変でしょう、おつらいですね」の言葉だ。公僕としての思いやりに満ちた担当者だからこそかえって気づきにくいのだが、そこにある行政の発想は、認知症は常に「大変で、困った事態」であるという前提がある。
それは、行政としての「課題対応」となり、それは上司の決済を経て、次の段階の「課題処理」に進む。「対応」から「処理」そして「解決」という既存システムに「認知症」を流し込めば、ことは解決どころか、それは、根深いスティグマの生産ラインのようなものである。
それではどうしたら本人の声を、本人参画の次元に引き上げられるのか。
本人参画とは、本人が施策に参画するのではない。施策が、本人の側に参画するのだ。
担当者が、認知症カフェに行ってみる。本人ミーティングの場に顔を出す。グループホームで半日を過ごす。
「本人参画」とは、必ずしも認知症の人が施策の場に出向いて、そこで施策に対して発言するという一方向でイメージすることはない。施策の側が、認知症の人の暮らしと物語に「参画」するという双方向性があっていい。それがダイアログ、対話である。対話とは面と向かってやり取りをするだけに限らない。地域にみずみずしい交流がいく筋も流れていくことである。施策がそこに参画する。
もちろん、認知症の本人参画が、直ちにブリリアントな成果につながる、といったムシのいい話であるはずがない。認知症の人の参画と、施策者の参画が交互に行き来し、丁寧に重ね合わせ、合意点を探ることも必要だ。
そうすると何が起こるか。
行政が変化する。施策が変化する。
「やり方」を変えるのではない。「あり方」を変える。
「行政が地域を変える」のではなく、「行政と地域が変わる」のである。
行政が頑張って地域を変えようとしても、その行政は変わっていないわけだから、地域資源を食いつぶすようにしてやがて行き詰まる。「やり方」の問題ではない。
「行政が(何かを)変える」という他動詞の関係性ではなく、自動詞の「行政が変わる」にすれば、そのためには行政の「あり方」を変えねばならない。それは地域を変え、新たな地域資源の誕生となり、持続性があり、地域誰もの力と思いが組み込まれた「ともに生きる私たちの地域」への方向がみえてくる。
実は、と声を潜めるようにして言っておくのだが、この少子超高齢社会の未来は、霞が関がアテにならない以上、これでしか拓けない。私はそう思う。
「本人参画」とは、認知症の人と施策者だけが頑張ることではない。誰もがこの地域社会にいかにして「本人参画」するのか、それが「認知症とともによりよく生きる」であり、そして・・
「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の、「私たち」なのである。