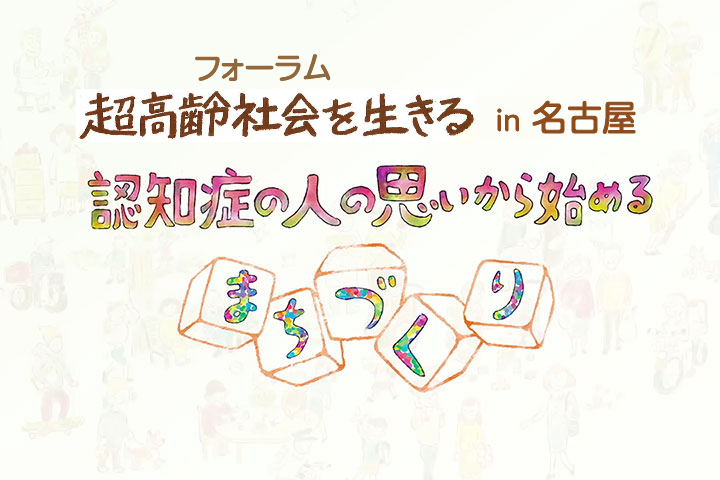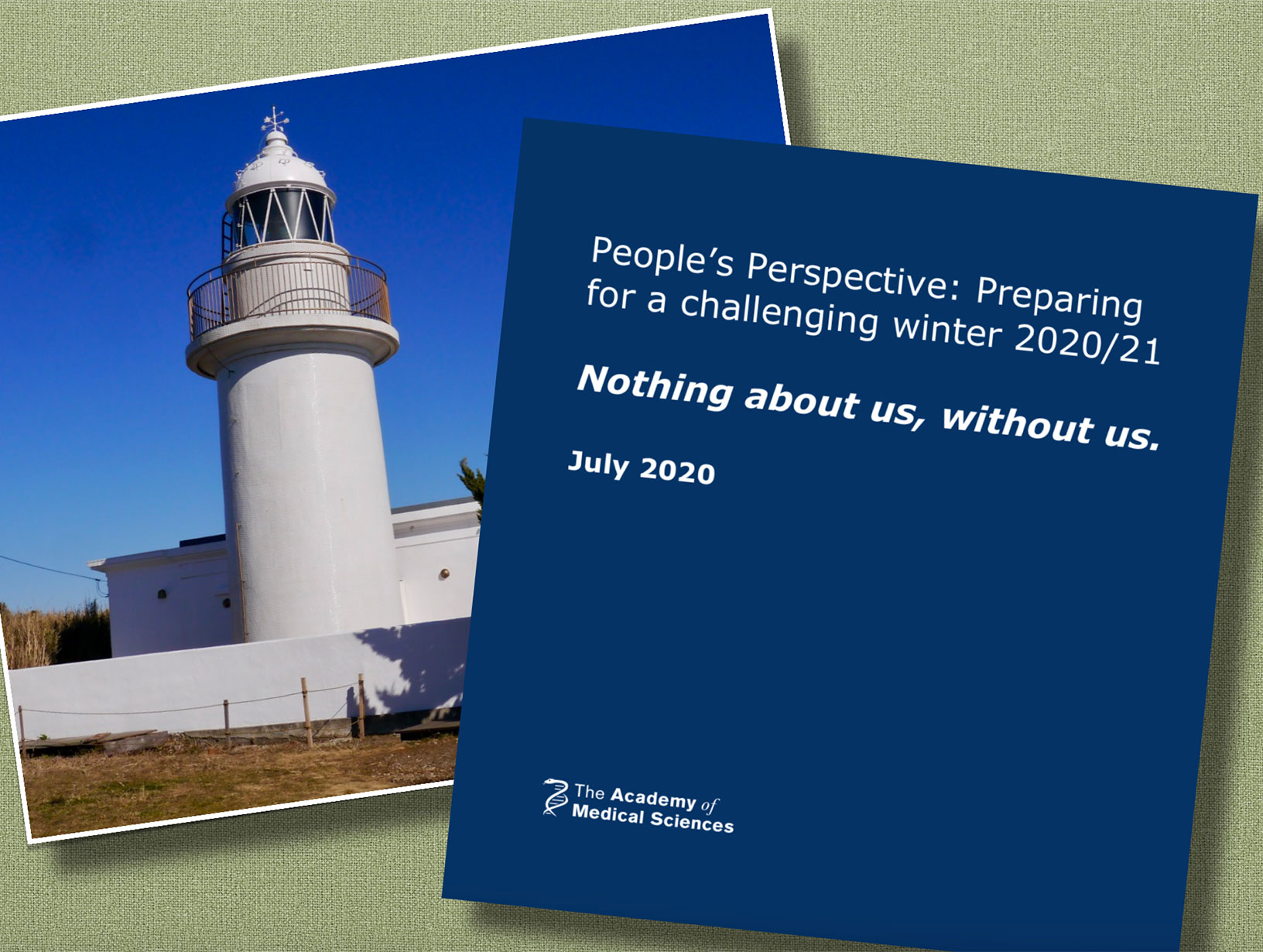
▲右のレポートは、この7月に英・医科学アカデミーがこのコロナ禍に際して出した「当事者の視点」。この事態をどう受け止めたのか当事者の言葉が掲載され、その表紙には「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の標語が掲げられている。理念は現実を照らす。コロナの時代の灯台である。
「介護崩壊を防ぐために」というオンラインの話し合いにずっとオブザーバーで参加している。
こうした介護関係者の議論の場は全国各地で様々な形で行われているようだが、私は仙台の「宮城の認知症を共に考える会」のオンラインの場に参加している。
毎週、介護関係者、医療者、専門研究者、行政者が参加して2時間を超える議論をし、そのあとに論点整理と関連する膨大な資料がメールで送られてくる。大変な作業量だろう。
6月7日に出された「介護崩壊を防ぐために(現場からの提案)」というその提案書は、第一波をしのいだ後のホッとした安堵感は微塵もなく、すぐに来るであろう第二波にどう備えるかという危機感の中での、第一波での綿密な検証が記されている。
第一波で介護施設に何が起きたのか。
関係者に衝撃が走ったのは、高齢者が利用する各地の施設で相次いでクラスター(感染者集団)が発生したことだ。
その一つ、富山市のある介護老人保健施設では、4月17日以降、入所者41人、職員18人の計59人が感染し、そのうち入所者15人が死亡した。
国も都知事も、いつも医療体制には余裕があり逼迫していないとするが、では介護現場の現実をどう捉えているのだろう。
もちろん医療体制の整備こそがこのコロナ禍での防波堤であることは論を待たない。が、介護現場というのは多様な暮らしの場を接続させている。ということは医療よりも、「くらし」という複雑な変数を抱え込みながらの命の現場なのである。
医療現場と介護現場のどちらの優先度を語るわけではない。第一波を乗り越えた事例に、医療とケアの連携というよりむしろ有機的な統合が成立した時、それが最も有効だったという報告もある。だとしたら、介護の現場で何が起きたのか。何が起こりうるかはもっと広く論じられるべきではないか。
先の富山での老健施設の大規模クラスター発生の際、富山県の医療支援チームとしてその施設に派遣された山城清二富山大学病院教授はその経験を、次のように語っている。
「医療的ケアが済んだあとは、医療より介護の力が必要で、とにかく食事と水分を取れなくなったら終わりという状況だった。とにかく食べてもらうこと水分を取ってもらうことで手一杯だった。
今回、医療支援チームに入って、現場での介護の力を実感した。
介護士が入ってきて、感染していない入所者が食事をとり風呂にも入り、介護士の力で施設の雰囲気が明るくなり、入所者が見る間に元気になっていった。
今から思えば、介護の力を自分(山城教授)が一番学び、実感したかもしれない」と語っている(6/27医療維新)。
この事態だからこそ、介護の力の果たす役割は大きい。
確かに医療は、この事態の「命の現場」の最前線であることは間違いない。と同時に介護の現場もまた「命の現場」であり、それは「命」と共に「暮らし」と「人生」の舞台である地域を含む「LIFE(命とくらしと人生)の現場」なのだ。
介護施設は今や、入所系、通所系、訪問系と様々なサービスを組み合わせる多機能化で地域の介護や医療のネットワークとつながっている。このため、ひとつの介護施設で大きなクラスターが発生すると、地域の介護事業の休業連鎖になり、多くの介護難民が生まれ、地域のくらしが崩壊する。
コロナ禍での介護現場の取り組みは感染対策だけにとどまらない。そこにはこの少子超高齢社会の現実がズシリとのしかかっている。「介護の力」は、核家族や過疎の社会を存続させるためのまさにLIFE LINEである。この国はすでに「介護の力」なくしては成り立たない形になっている。
だから「介護崩壊」は、そのまま私たちの「社会崩壊」だ。
東日本大震災の時、障害者の死亡率は、住民全体の死亡率の二倍だったというデータがある。これはNHKが主要な被災自治体を対象に調査したもので、総人口に占める死亡率は1.03%だが、障害者の死亡率となると2.06%で、地域によってはさらに障害者の死亡率が高くなっていた。
これをどう見るか。
日本障害フォーラム議長の藤井克徳氏は「なぜ障害者の死亡率がこうも高かったのか。大震災はすべての人に公平に襲いかかったが、その人的被害は公平ではなかった」と語り、障害者の死亡率の高さを「想定外の大震災で、止むを得ない」で片づけるのではなく、そこには明らかに「障害ゆえに」が横たわっていると指摘する。
それは、障害があるからやむを得なかったというのではなく、この社会の脆弱さが招いたのだとする視点である。
同じことが今、このコロナ禍で起きうるのではないか。誰もに公平に襲いかかった新型コロナウィルスの事態に、その人的被害が歪んだかたちで介護施設に押し寄せないだろうか。
それはすでに障害当事者から危惧の声が上がっている。感染拡大により医療が崩壊する事態が起きたとき、救命治療から排除される「命の選別」が起きないかという声である。
緊急事態で逼迫した人材不足や施設の限界の中、介護度が高く手間がかかる「寝たきりゆえに」「認知症の人ゆえに」と、排除や拘束や命の選別もやむを得ないとしたら、その時点で「介護」は自身の「介護崩壊」を自らの手で下すことになる。
しかし、このオンラインの議論の全体を俯瞰するようにして眺めるとき、実はそこに伏流するもうひとつの変化が見られる。それはこうした緊急事態だからこそ、見落としてはならない当事者の視点というものだ。
それまで「介護崩壊を防ぐため」と、ただその一点にきり込むようにしてクラスター発生を防ぐ手立てを議論し、国の指針である感染者の個室隔離か、それとも法人の枠を超えた応援連携による集団隔離(コホーティング)とするかという地点にまで議論が進んだ時、議論は実は質的な大きな変化を見せたのだ。
オンラインの主宰のひとり、山崎英樹医師は、ここでの議論では感染者を「隔離する」だが、一方で、感染当事者の側にすれば「隔離される」ことになると反応した。専門家だけの議論でいいのか、ふみとどまるようにして、議論に認知症の人の当事者性と人権が持ち込まれたのである。
介護崩壊のいちばんの犠牲者は、施設の高齢者や認知症の人であり、その人たちにこの議論に参加してもらうことが必要だとして、この議論は、直ちにといった迅速さで、認知症当事者の丹野智文氏や認知症の人と家族の会宮城県支部の若生栄子氏などを交えての仙台の認知症リカバリーカレッジで、「当事者が話し合う介護崩壊」として認知症当事者同士で話し合われた。
この議論の分厚さはどうであろう。私はこのような介護を語る一連の流れとその変化は実は大きな社会の転換を促す可能性を持つと思う。
それはどんな形の社会なのか。
それは「安心して感染できる社会」というものではないか。
認知症をめぐっては、「認知症になっても安心の社会」と言われてきた。が、ここには、認知症という「重荷」を抱えていることを前提に描いているのではないかという当事者の声を受け、今は「安心して認知症になることができる社会」と進化している。
だとしたら、介護崩壊を防ぐために目指す社会は同じなのではないか。
「防ぐ」ためには、「造る」ことが必要だ。それが「安心して感染できる社会」だ。繰り返すが、「介護崩壊を防ぐために」というのは、いまここにある少子超高齢社会の「社会崩壊を防ぐため」の取り組みなのである。
社会崩壊を防ぐとしたら、それに備えられる万全の医療と介護が据えられた新たな社会システム、それが「安心して感染できる社会」を「造る・創る」しかない。
もちろんこれは、勝手なふるまいをしても構わない、と浅読みされては困るのだが、そこには当然、公衆衛生的な配慮、医療介護の体制の充実、そして何より一人ひとりの新しい生活様式といったセルフケアを前提にしての事なのはいうまでもない。
このオンラインに参加する介護関係者には、認知症の人と関わる人が多い。認知症もコロナの時代も、誰もがなりうる当事者性を基軸にするしかない。試練であることは間違いない。ただその試練は介護関係者だけでなく、この社会総体が分かち合うものだ。誰もが当事者である社会の意志として。
そのように思いながら、毎回オンラインの片隅で耳を傾けている。